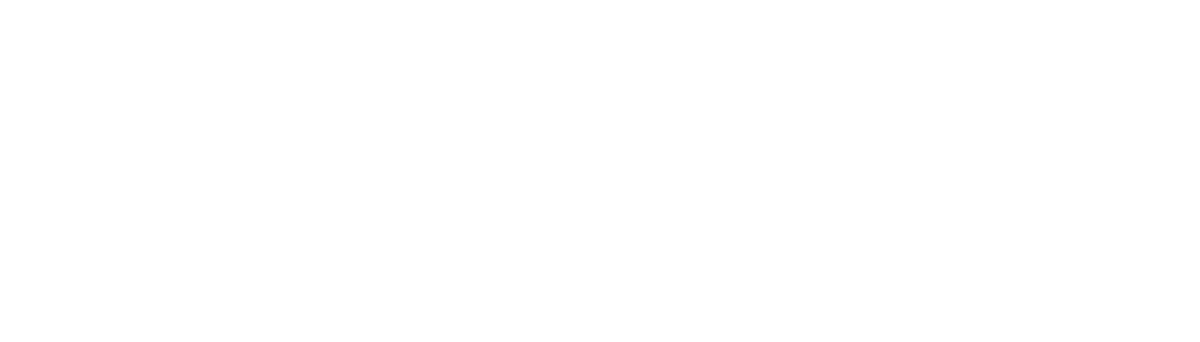INFO
24.06.30
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-七- 浮石三宙の空言(1)
著者:麻日珱
新和二十年秋、横浜壊滅。
それは、舎密防衛本部の予測速度を遙かに超えた圧倒的な侵食だった。
燈京の港から船に乗り急行した浮石三宙純弐位、源朔純弐位、安酸栄都純参位の三名は、船上からデッドマターによる侵食に黒く沈む横浜の街を為す術もなく見つめることしかできなかった。
横浜方面における侵食圧の急上昇の一報から、わずか二時間足らず。横浜に張られた元素結界を薄紙のように押し破った侵食は、海に触れたところでその勢いを止めた。
海上にはデッドマターの侵食から逃れた小型船が幾つも浮かんでいたが、人口に対して横浜を脱出した船の数はあまりにも少ない。
横浜防衛支部の職員および民間人の生存は絶望的だった。
侵食は止まったものの、侵食圧は新和十八年の鎌倉防衛戦の最高値よりも高く、現状での志献官の投入は危険かつ無意味であると判断。三宙たちを乗せた船は、横浜港に近づくことすらなく引き返し始めた。
三人は交わす言葉もなく、諦めきれぬように船の動きに合わせて船尾へと向かう。遠ざかる横浜を目に焼き付けるように立ち尽くそれぞれの顔には、やりきれない悔しさや悲しみ、憤りが滲んでいた。
(何だよ、これ......)
三宙は拳を握り締めた。
不穏な兆候は一年前からあった。元々横浜方面は侵食圧が特に安定していた地域だったが、突如異常な侵食圧の上昇が観測されたのだ。当時三宙は観測部の研修のために横浜防衛支部に出向いていて、ちょうど横浜で行われるはずだった昇位試験の日に重なった。
試験は中止になったが、境界面にほど近い侵食領域内に現れた形成体を撃破したことで、三宙と朔はその実力が認められて純弐位に昇位した、輝かしい記憶でもあった。
守り切ったと思っていた。その横浜が、今度は為す術もなくデッドマターの闇に呑まれてしまった。
「......っ」
遠のいていく横浜から無理やり視線を引き剥がし、憤りをぶつけるように足を踏み鳴らして背を向ける。強い潮風に制服の上着が風をはらんだ。まるで、見捨てるのかと横浜で消えた魂が縋りついてくるように、重たい。
強風に煽られて身体が傾(かし)ぐ。波に上下する船に身体が揺れる。
(きもちわりぃ......)
口元を手で覆う。目眩なのか船酔いなのか、唐突に酷い吐き気がした。
(オレは、こんな光景を見るために志献官になったんじゃない......)
ぎゅっと閉じた目蓋の裏に、闇に呑まれた横浜の光景が焼き付いて、いつまでも消えてくれない。
じゃあ、どうして?
何のために、こんな苦しい思いをしてまで、志献官でいるのだろう。
問うような波音の向こうから、澄んだ音が一つ、聞こえた気がした。
※ ※ ※
柔らかな余韻を残してピアノの音がとけていく。演奏を終えてふう、と息をついた三宙の耳に、パチパチと拍手の音が届いた。
「三宙すごい! 上手!」
丸い頬を紅潮させた少年が一生懸命拍手をしながらぴょんぴょんと小さく跳ねていた。その手放しの賞賛が誇らしくて照れくさい。三宙は、癖のある前髪を小さく引っ張った。
「まだ全然だよ。弾けるようになったばっかりだし、いっぱいミスしちゃったし」
「そうなの? 全然分かんなかった。すごいなぁ、三宙」
「このくらい、朔だって練習すれば弾けるようになるよ」
「そうかなぁ?」
椅子を半分譲ってやれば、隣に座る。未就学児がふたり座っても、椅子はちっとも狭くなかった。
ぽん、とピアノの鍵盤を叩いて朔はうーん、と首をかしげた。あまりピンとこないようだ。
「やっぱり僕は三宙のピアノ聞いてる方がいいや」
朔は屈託なく笑う。そんな風に言われると、次に会うときまでに別の曲を練習してびっくりさせてやろうかな、なんて思う。照れ隠しに、ぽんと鍵盤を叩けば朔も真似をしてぽんと叩いた。
「三宙は大きくなったらピアニストになるの?」
『──いいですか、三宙さん』
不意に蘇った母の声に、三宙は熱湯にでも触れたようにピアノから手を離した。朔だけが、人差し指で鍵盤を叩き続けている。
「ううん......ボクは浮石家を継ぐんだよ」
ぽん、ぽんと音を鳴らす朔は、三宙の顔がわずかに曇ったことにも気付かない。
「そっかぁ、僕はね」
「志献官になる! でしょ?」
ぱっと三宙に向けられた顔には、満面の笑みが浮かんでいた。初めて会った日から、もう何十回も聞いた話だ。いつ聞いても、朔は初めて語るような熱量で語る。
「志献官になってね、兄上といっしょにデッドマターと戦って、結倭ノ国を守るんだ。それが、一族の使命なんだよ!」
源家は代々志献官を輩出している一族だ。朔も、朔の兄である碧壱も、志献官になるために努力しているのだという。
「それでね、兄上が教えてくれたんだ。志献官ってね──」
朔が興奮気味に語る志献官の姿に引き込まれる。まるで、冒険の物語を聞いているようなわくわくが三宙の胸をいっぱいにする。
「三宙もいっしょに志献官になれたらよかったのになぁ」
不意に朔が言った言葉に息が詰まった。
「な──何言ってんの。ボクだって浮石家を継いで結倭ノ国を支えるって使命があるんだよ」
ずっと、浮石を継ぐのだと言われて育ってきた。それ以外の何かになるなんて──なれるなんて、考えたこともない。
(でも、もしも志献官になれるなら......)
静かな水面に落ちた一雫のように、三宙の心に細やかな波を作る。
「そっかぁ」
残念そうな朔の声にハッとする。朔は残念そうに口をとがらせながら、でも、とすぐに笑顔になる。
「春から同じ学校だもん。いっぱい遊ぼうね、三宙」
「うん。楽しみだな」
気を取り直して頷く。もしも、なんてあるはずがないのだから。
(──つまんね)
三宙は校門を通り抜けながら欠伸を噛み殺す。
燈京の小学校に入学してからあっという間に三年が経った。小学校ではいったいどんなことを学べるのだろうと思っていたのに、とっくの昔に家庭教師に習ったところばかりで退屈だ。同級生たちは親に何か吹き込まれたのか、必死になって"浮石家の跡取り"にすり寄ってくる。見え透いた下心に作り笑顔を返すのが社交の基本なのだとしたら、確かによき学びの場なのかもしれない。
(こんなハズじゃなかったんだけどなぁ......)
浮石家から解放されて、もっと楽しい学校生活を送れると思っていたのに、今のところ楽しいと思えることはほとんどなかった。
いっぱい遊ぼうと約束した朔とは、結局一年から三年まで、一度も教室が同じになることはなかった。一学年にたった三学級しかないのにだ。朔は朔で取り巻きの同級生たちと仲良くやれているようで、漠然と距離を感じてしまう。
幼馴染みといったってそんなものかと、最近は思うようになっていた。
「三宙! 三宙ー!」
「うわ!?」
小学校の昇降口で上履きに履き替えようとしていた三宙は、突然横から体当たりされて蹈鞴(たたら)を踏んだ。朔だ。どうやら、三宙が登校するのを今か今かと待っていたらしい。
「何だよ! 危ないだろ!」
「三宙! 兄さんが志献官になるんだ!」
熱でもあるのかと思うくらい顔を赤くして興奮気味に語る。朔の言葉はあちこち話が飛んでいたが、つまりは、来年志献官として防衛本部に行くことが決定した、ということらしい。
「しかも、純参位なんだ!」
「すげー! 志献官って、普通混位からだよな?」
「そう! 兄さんはすごいんだ!」
三宙が朔の兄、碧壱に会ったのは両手で数えるほどもない。とても落ち着いた、笑顔の穏やかな人だという印象がある。歳が離れているせいもあって、随分大人びて見えたのをよく覚えている。
「これでボクも志献官になったら、兄さんと一緒に働けるんだ!」
朔は鼻息を荒くしている。三宙はようやく上履きに履き替えて首をかしげた。
「でも、まだ因子があるかどうかも分かんないじゃん」
「あるよ! 僕だって源家の人間だもん」
朔はニッと笑って胸を張る。
志献官になるためには、元素の因子を持っていることが絶対条件だ。源家は初代の志献官にも名を連ねる名門で、男子は水素の因子を持って生まれてくることが多いそうだ。
(源家の人間、か......)
最近ふと、疑問が頭をもたげることがある。朔は、源家に生まれたことが息苦しくないのだろうか。
三宙は息苦しかった。
『浮石の者は常に完璧でなければなりません』
何かある度に母はそう繰り返す。三宙だって朔と同じくらい浮石家を誇りに思っているはずなのに、両親の期待が息苦しく、時々上手く受け入れられない。
「三宙、聞いてる?」
「聞いてる聞いてる」
朔の志献官や兄への憧れは昔から変わらない。いや、一層強くなっていた。朔が語る夢と未来への希望を聞いていると、自分の中に詰め込んで来た浮石を継ぐための全てが虚しいもののように感じてしまう。
その虚しさから逃れるように、三宙はそっと目を伏せた。
その日の夜のことだ。
洋風建築の広々としたダイニングには箸と食器がぶつかる微かな音と、壁時計の振り子の音だけが響いている。静かな夕食だった。ダイニングには三宙と両親と使用人が数名控えているが、時折咳払いが聞こえる以外は誰の声も聞こえない。
そんな中に、父の低い声はよく響いた。
「──源家の長男が志献官になるらしい」
父の言葉に黙々と食べていた三宙はハッと顔を上げた。手が滑って茶碗に箸がぶつかる音が大きく響く。口元を軽くナプキンで拭った母は、それを咎めるように一瞥して父へと視線を戻した。
「ではやはり、家門を継ぐのは次男ですのね。そうだと思いました」
母は満足げに頷く。三宙は不思議な心地でふたりを見た。視線に気付いた母が柔らかく目元を綻ばせる。
「源家の次男と仲良くしておいてよかったでしょう? 経済の浮石、政治の源と言われていますもの。いずれ、あなたたちふたりが結倭ノ国を率いていくのですよ」
つまり、朔も父親のように政治家になるということだろうか。三宙は首を振りながら箸を置いた。
「朔は志献官になるそうです」
「息子のうちひとりでも志献官になれば、源家の面目も保たれます。ふたりも志献官にするような愚は犯しませんよ」
「ですが、朔がなりたいって」
「子供の夢だ。いずれ現実が見えてくれば、どちらがより結倭ノ国のためとなるか理解するだろう」
「でも!」
「三宙。今日はいやに食ってかかるな?」
自分と同じ葡萄酒のような赤い瞳に射すくめられて、思わず目を逸らした。
「......ボクは、ただ......源家のことは、うちで決めることではないと」
「あら。源の奥様も下の子を志献官にしようとは思っていないとおっしゃっていましたよ。まあ、あちらの場合は上の子を志献官にすることで頭がいっぱいですからね。いざというとき下の子をどうするのかは分かりませんけれど」
「源が支持されているのは志献官を輩出しているからという面も大きい。志献官を出せなくなれば、支持者は確実に減る。実際、前の水素の志献官が殉職してからは、支持者は減っていく一方だったようだ。残っているのも、息子に期待している者がほとんどだと聞く」
「では、長男が志献官になってホッとしているでしょうね」
碧壱が水素の志献官になれば、実に十数年ぶりの水素の志献官の誕生となると朔が言っていた。先代の水素の志献官は朔の伯父だったらしいが、朔が生まれる前に殉職したという。だから、源家は何としてでも志献官を出さなければならなかったのだそうだ。
「......ごちそうさまでした」
料理の半分も食べ終わっていないが、三宙は席を立った。食欲がなくなったからだ。それに、これ以上話を聞いていたらまた要らぬ口答えをしてしまいそうだったからでもある。
「三宙さん」
咎めるような母の呼び声が追ってきたが、聞こえないふりをしてダイニングを出る。
(子供の夢って何だよ)
胸の中にどうしようもない感情が渦巻いている。悔しくて腹立たしいが、それを両親にぶつける度胸もない。
自室に駆け込むと、三宙はベッドに飛び込んで突っ伏した。スプリングの効いた上等なマットレスが三宙を迎える。それすら無性にムカついて、八つ当たりするように叩く。
(──他人(ひと)の人生を、勝手に決めるな)
ぷかりと浮かんできた想いに三宙は歯がみした。朔の夢を子供の夢だと否定されたことがこれほどまでに腹立たしいのは、浮石家の跡継ぎという言葉に幾つもの希望を摘み取られてきた自分が重なったからだ。
ずっと、心の奥底に沈めて見ないようにしていた感情だった。両親の示す道が正しいと、目を背けていただけで、本当はずっとそこにあったのに。
家を継ぐことは別にいやじゃない。浮石家は医療や商業など、様々な分野に手を伸ばしている財閥だ。その巨大な事業を受け継ぐために浮石家のひとり息子として努力してきたし、自負もある。
三宙の将来は明るいと、誰もがそう思うだろう。
けれど、そういうことじゃない。
三宙は"今"が欲しい。浮石家を継ぐという未来は燦然と輝いているのに、三宙には"今"がなかった。三宙がしなければならないことの全ては、将来のためにあるからだ。
でも、朔は違う。次男だからだろうか。家門の中にありながら、朔は自由だ。自分がなりたいものに憧れて、ひたむきに目指している。朔には"今"がある。
朔が志献官や兄への憧れや、将来の夢を語る度、三宙もその"今"を生きているような気がした。
両親が子供の夢と無神経に踏み躙ったのは、三宙が生きる"今"だった。
「っ......!」
突き上げるような衝動に歯を食いしばりながらベッドの上で暴れる。
全てを親から与えられた三宙には、自分の意志で手に入れたものは何もない。そう、幼馴染みでさえ。
朔は母が仲良くするのよと引き合わせた相手だった。そういう子供は他にもいた。一番気が合って、残っているのが朔だというだけで──。
「......」
息を切らして天井を睨み、三宙はくしゃりと歪む顔を両手で覆った。
幼少期の楽しかった思い出にケチがついたようだった。明日から、朔にどんな顔で会えばいいのだろう。正直に言えば、会いたくない。この苛立ちをぶつけてしまうことが怖かった。
考えるほどに深く憤りの中に沈んでいく。心の身動きが取れなくなった三宙は、翌日から数日間、謎の高熱を出して寝込んだ。
学校に復帰してからは、三宙は朔を避けた。教室が違うから、難しいことではない。将来のために源家と仲良くするようにと言い含める親への反抗でもあったし、ぐちゃぐちゃとした感情からの逃げでもあった。どうしても顔を合わせなければならないときは素っ気ない態度で突き放し、無視をする。そんな日々が続けば、朔の方からも三宙に寄ってくることはなくなった。
申し訳なさや寂しさがなかったと言えば嘘になる。けれど、朔からもたらされる憧れに同調することのなくなった心は、虚しくも静かだった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら