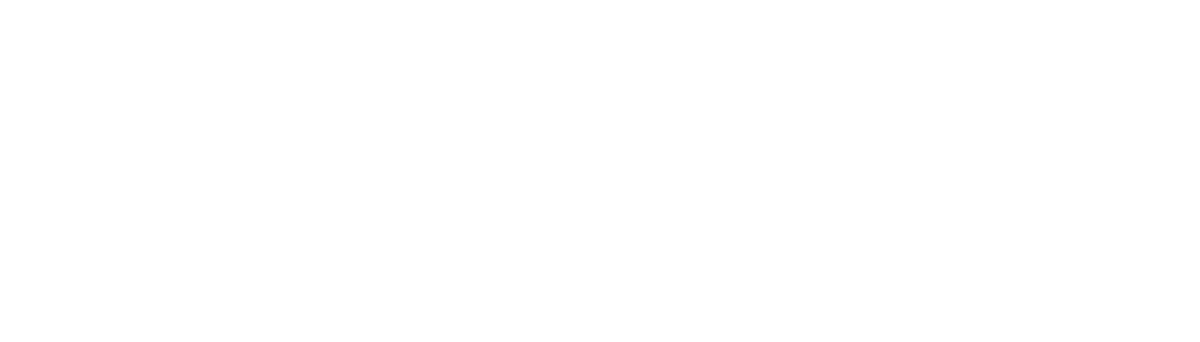INFO
24.09.01
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-九- 塩水流一那の追儺(5)
著者:麻日珱
前回「断章-九- 塩水流一那の追儺(4)」はこちら
「......」
一那は頬に飛んだ血をぐいっと拭う。ついでにマスクがずれた。手が血に濡れているのも構わず戻し、破壊し尽くされたヒトだったモノに無感動に視線を投げる。
狂乱するように頭の中で鳴り響いていた声は不気味なほどに静まり、一那は胸の内に訪れた安寧に深く息を吸う。血の臭いが肺いっぱいに入り込んできたが、腐った死体の臭いよりははるかにマシだった。
もう、何度目の任務だろうか。初めて十六夜に壊すよう命じられて人間を壊したのは、まだ暑い夏の終わり。今は寒い冬の最中だ。
(デッドマターと戦えと、言われていたが......)
結局、人間ばかり殺している。最初は人間を壊すことに戸惑いを覚えたが、もう慣れた。何を壊すよりも、ヒトを壊すことが一番破壊衝動を解消できる。下手をすると、デッドマターを倒すよりも。
「──帰るぞ」
「......」
低く声を掛けられ、一那は踵を返す。大きな刃物を連ねた扇型の武器を閉じ、切っ先を引きずるように歩いた。血の跡が足跡と平行に続いていく。
手に掛けた男がいったい何を犯したのか一那は知らない。興味もない。ただ、十六夜に殺せと言われたから殺しただけだ。
しんと静まりかえった建物の中をカラコロと十六夜の下駄の音だけが響く。いざとなれば足音など消せるのにそうしないのは、この建物の中に生きている人間がいないからだ。
建物の外に出れば、吐き出す息が白く曇る。暑さ寒さは感じるが、身体に堪えることはない。十六夜などは寒い寒いと声を上げているが、一那はその背中を無感情に追うだけだ。
「あ、そうだ。しばらく地下牢使えないから、寮に移れってさ」
「なぜ」
「おまえが牢に入ったせいで、改修作業が進まねえんだと。もう罪人でもないのにいつまでも入れておくなって、怒られちまってさ」
「......」
一那は黙って目を伏せた。一那は罪人だ。純の志献官になったって、それは変わらない。それに、ヒトの息づかいが感じられる場所に行くのはまだ不安があった。
一那が口を閉ざしていれば、十六夜は軽く続ける。
「おまえは純位だから一人部屋だし、寮に移ったって部屋に引きこもっときゃ誰にも会わない。なんか壊したくなったら適当な場所に行くくらいは、もう我慢できるだろ」
十六夜の口ぶりから、寝床を移すのはもう決定事項のようだった。嫌だと拒否したところで、里から引っ張り出された強引さで寮に入れられるのは目に見えている。
本当に寮の部屋を与えられたのは、それから数日後のことだった。机や寝台などの備え付けの家具の他は何もない。
「ま、好きに使いな」
部屋に入れられた一那がまずしたことは、カーテンを閉めることだった。ヒトの気配がとにかく近い。声や誰かの足音まで聞こえてくる。一那は寝台を使わず、床の上に膝を抱えて座り込んで衝動をやり過ごした。食べなくてもいい身体だ。食事をするために部屋を出る必要もなかった。
そうやって何日もすれば、さすがに状況には慣れた。気を張った状態ではあったが、そのおかげなのか破壊衝動も訪れることはなく、気疲れはしたもののこのままでやっていけるのではないかと一那は思った。
だから、それは魔が差したとしか言いようがなかった。
少しだけ、外に出てみようと思い立ったのだ。これからは、この防衛本部でやっていく。ならば、どんな場所であるかくらいは知っておいた方がいい。そのくらいの気持ちで外へ出た。
日が高いうちに外に出るのはいつぶりだろうか。太陽の眩しさに目を細め、そして、その温もりを感じながら本部の敷地内を歩く。建物の中に入るのは、まだ少し勇気が足りないから、周りだけをぐるりと回った。
何人かともすれ違いそうになったが、そのたびに一那は逃げて物陰に隠れてやり過ごした。
「おや。こんなところでかくれんぼかい?」
気配もなく現れた金色にぎょっとする。笑みをたたえた二十歳前後の青年は、植え込みの影に隠れた一那を引っ張り出した。
「みんな! この子がひとりぼっちで可哀想だ。遊んであげようじゃないか!」
ヒッ、と喉の奥が引きつる。青年の大きな声に、どこからともなくわらわらとヒトが集まってきた。
「舎利弗純壱位、こちらは? 志献官のようですが......見たことがありませんね」
「さあ? 今そこで見つけたんだ」
金色は、舎利弗という名前らしい。純壱位ということは、十六夜と同じ階級のはずだが、十六夜と比べてもずいぶん若い。
また別の青年が口を開いた。
「あ。もしかしてアレか? 清硫純壱位が連れてきたっていう」
「ああ......隠し子だっけ?」
「うわ、ホントにいたんだ。しかも、結構大きい」
「ん? 清硫純壱位っていくつだっけ?」
「まあ、結構遊んでるって噂だしなぁ」
「でも、あんまり似てないのな」
大人たちが口々に囁き合う。一気に取り囲まれて一那はマスクの下で喘いだ。心臓が早鐘を打ち、鼓動が速くなる。何より、声が、頭に、響いて......。
「──っ!」
呼気に塩素ガスが混じるのを感じて一那は息を止めた。
「おっと──なるほど、これはいけないな」
舎利弗はそう言って目を煌めかせると、人々の輪から一那を引っ張り出した。
「みんな、下がりたまえ。キミも、もう行きなよ。ここにいては危険だろ?」
彼を取り巻く全ての大人がきょとんとした顔をした。ずらりと並ぶその顔が、黒く塗りつぶされたように蠢いて、一那はおぞましさのあまり走り出す。
一那の胸にあったのは、破壊衝動に勝る恐怖だ。大勢に囲まれた。そんな記憶どこにもないのに、全身に注がれる視線が圧力のように感じられた。身に覚えのない、不愉快な、ざらりとした感情だった。一那は無意識に、彼らを殺そうとしている自分に気がついた。
《殺セ!》
(イヤだ......!)
自分がどこにいるのかも分からないまま、一那は走る。マスクのおかげでガスは漏れなかったが、それでも一那は焦燥を抱いたまま逃げ続けた。
「うわっ!?」
建物沿いに曲がったところで、ヒトが現れた。避けきれず肩がぶつかる。
「ゴメン! だいじょ──」
陽光に煌めく白い髪の少年が、不自然に言葉を飲んで動きを止める。
「君......誰......?」
少年の問う声が震えていた。
《殺セ、壊セ、破壊シロ!》
気がつけば、こぼれんばかりに見開かれた目が真下にあった。一那が少年にまたがっていたからだ。片手で肩を押さえ、もう一方の手で少年の首を掴んでいる自分がいた。
少年の目が恐怖に染まっていく。首を絞める一那の腕を両手で掴んでもがいた。
《コロセコロセコロセ!》
目の前が破壊衝動で真っ赤に染まる。うっすらと、マスクの下にある一那の口元に笑みが浮かんだ。
「──バケモノ」
蚊の鳴くようなか細い声が少年の口から発せられた瞬間、一那の脳裏に閃光が走るような衝撃があった。
『バケモノだ!』
『怪物が!!』
声が──破壊の発作が起こるときに聞こえるのとは違う、はっきりとした声が頭の中に響いた。少年から手を離し、頭を抱えてフラフラと立ち上がる。解放された少年がゲホゲホと咳き込んでいた。
「......っ」
形のない、やりきれない感情が胸を満たした。泣きたくなるような悔しさと悲しさが最悪の形で溢れ出しそうで、一那はマスクの上から口を手で押さえた。
(ダメだ......)
《ナゼ、イケナイ?》
いつも不快に喚いている声が、はっきりと一那に問うた。
(殺すのは、イザヨイが命じたモノだけだ)
任務だから許される。任務だから壊してもいい。任務だから──。
《バケモノ》
《カイブツ》
「ねえ──」
おずおずと窺う少年の声に弾かれるように、一那はその場を逃げ出した。
嘲笑うような、責めるような声が、ぐるぐると頭の中を巡る。これまでとは違う、あらゆる声が一那を責めた。
(違う......。いや、そうだ、オレは、怪物、だから......)
だから、ヒトとは違う。食わずとも生きていけるし、眠らなくても生きていける。誰を殺したところで痛む心はない。誰が死んだところで、悼む心もない。
(ああ、オレは、怪物だ)
怪物だ。怪物だから──。
一那は見覚えのある入り口に気付いて飛び込んだ。地下への扉を開けて、階段を駆け下りた。修理を行っていた業者がぎょっと目を丸くする。
「っ、出て、いけ」
「え?」
「失せろ!!」
一那の叫びに、業者は恐怖を覚えたのか慌てて逃げていく。一那はごちゃごちゃとしている荷物を押しのけて牢の隅に駆け寄ると、身をぎゅっと縮めた。
「ハー、ハー......」
深く息をする。やがて衝動は過ぎ去っていったが、そこから動く気にはなれなかった。
怪物には、地下牢がお似合いだ。
今すぐ誰かが捕まえに来るのではないかと息を潜め、一那は暗闇を睨んだ。
どれほどそうしていただろう。心が憔悴するほどの時間が経った頃、カラコロと聞き覚えのある足音が近づいてきた。
「何してんだ? こんなとこで」
いつもの調子で十六夜がやってくる。一那はぎゅっと強く膝を抱えた。その姿に、十六夜は首を傾げつつ、修理業者の置いていった荷物を除けながらのっそりと牢の中に入ってくる。
「ちょうど外から戻ってきたら俺の隠し子がどうのって混のヤツらが盛り上がっててさ。一那、外出たんだって? すごいじゃないの。どういう風の吹き回しよ?」
一那は少しだけ顔を上げる。十六夜は、壁から二本の鎖で板を吊っただけの粗末な寝台に腰掛けていた。
「......寮には、戻らない」
「何で?」
「怪物だから」
一那の答えに十六夜が黙り込む。
十六夜はきっと、一那の中にいる本物の怪物に気づいていたのだろう。ただデッドマターを倒すだけでは満たされない飢餓感がある。何かを壊したときほど、それが取り返しの付かないことであればあるほど、その飢えは満たされる。そんな風に感じる一那は、正真正銘の怪物なのだ。
ならば、人のふりをしないで怪物らしく振る舞えばいい。怪物らしく生きればいいのだろう。
一那は固く膝を抱えていた両手から力を抜いた。
「──イザヨイ」
十六夜がきょとんと目を丸くした。
「一那......俺のこと呼んだの、初めてじゃない?」
明日は槍でも降るかな? と冗談めかして笑っている。そんな十六夜に、一那は口を開いた。
「イザヨイ。次は......誰を殺す......?」
壊して、殺して──それが、怪物に似合いの生き方だというのならば、そう生きよう。
「......」
十六夜の口角が一度ひくりと痙攣した。十六夜は刹那の表情を消し去って、すぐににやりと笑う。
「まあ、そう逸るなって。心配しなくても、始末しなきゃならんヤツらは山ほどいるからさ」
「そうか。オレは怪物だから、好きに使え。全て、破壊する」
「......あー」
十六夜はふらりと視線を上の方へ泳がせると、首の後ろに手をやって俯いた。
「じゃ、遠慮なくそうさせてもらうわ」
十六夜の表情は窺えないが、一那はひとつ頷いた。
そのあとからだ。十六夜が少しおかしくなったのは。これまでは、食わなくてもいいのは便利だと言ってはばからなかったくせに、一那に度々食事を運んでくるようになった。そして、何を思ったのか大量の本さえ与えた。ほかの志献官に引き合わせようともした。
空腹を知らない一那に食事は無意味だと知っているはずなのに。
怪物に知識など与えたところで無駄であることも明白なのに。
そして、仲間など破壊の限りを尽くす怪物には必要ないと分かっているくせに──。
『一那、頼みがある......。私を殺してほしい』
ほら。だから、怪物に仲間なんて必要ないのだ。
怪物のココロが悲鳴を上げる。
その絶叫は、記憶を覆う白い闇の向こうから、聞こえたような気がした。
(終わり)
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら