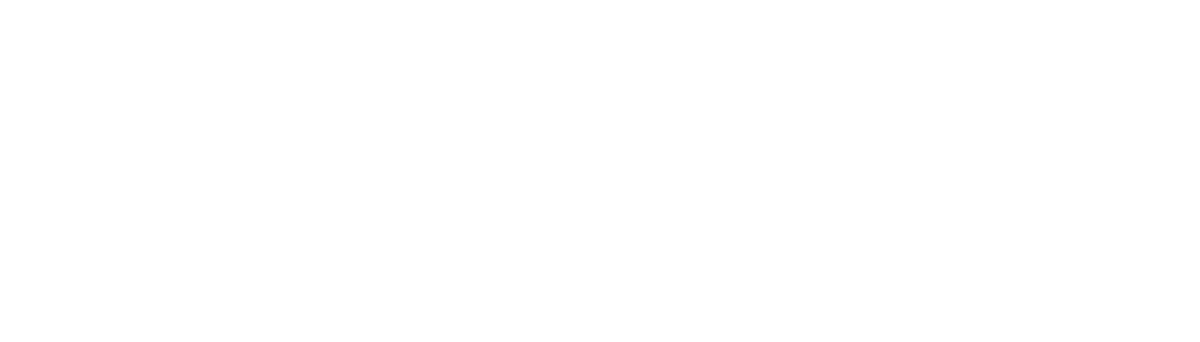INFO
24.09.08
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十- 舎利弗玖苑の結論(1)
著者:麻日珱
新和十三年、秋──。
「部隊調査中の如月人工島において、侵食圧の上昇を確認。デッドマター形成体の兆候なし。調査続行可能です」
一瞬、室内に走った緊張が、安堵の息と共に緩んだ。
舎密防衛本部転移室──防衛本部の敷地内に置かれた屋舎の中央には、巨大な元素転移装置が鎮座している。装置は六本の支柱に支えられた釣り鐘型で、上部には太さの様々な管や線が幾本も延びて、転移室の天井へと続いていた。
転移装置の周囲には、転移先の侵食圧や、転移した志献官たちの健康状態などを観測するモニターが置かれている。
天井の高い屋舎には、二階部分に相当する高さの壁際にぐるりと通路が巡らされていた。そこに座り込んでウトウトと船を漕いでいた青年は唐突に目を覚ますと、若木を思わせるすらりとした四肢を持て余すように、うんと全身を伸ばして立ち上がった。
「そろそろボクの出番かな?」
舎利弗玖苑は、手すりに身を乗り出して下を覗き込む。そこから見えるモニターの様子は、居眠りする前とほとんど変わらないようだった。
「まだか......」
落胆しつつ、玖苑はその大きな目でくるりと階下を見回し、目当ての人物を見つける。黒い制服を纏うその人は、観測部の混の志献官たちと言葉を交わしていた。
「ねえ、空木さん!」
こちらを振り仰いだ青年、空木漆理に玖苑は花咲くように笑ってみせる。その笑顔に、ほぅ、とあちこちから感嘆の溜め息が漏れた。
「やっぱりボクを派遣した方がいいと思うな?」
「まだいたんですか」
空木は混の志献官たちにいくつか指示を出すと、玖苑のもとへと上がってくる。転移の許可をくれるのかと玖苑は階段の上まで軽やかな足取りで空木を迎えた。
「いいでしょう? 空木さん」
先日、十七歳になったばかりの玖苑よりも六つか七つほど年上の理知的な青年だ。見透かすような眼差しは、玖苑を物怖じさせるほどの強さもなく凪いでいる。じっと期待するような玖苑の微笑みを静かに受け止めて、空木は小さく首を振った。
「許可はできません」
「えー?」
不満を露わにしてみせるが、空木は全く動じない。ほとんどの人は玖苑が微笑みかけるだけで熱に浮かされたように何でも言うことを聞いてくれるのだが、空木には効いた例しがなかった。
「玖苑ちゃん、玖苑ちゃん」
手すりに乗って呼ぶのは帽子にリボンを付けた観測部のモルだ。空木と一緒に上がってきたらしい。玖苑は身をかがめて目線を合わせる。
「何だい?」
「あのね、今すぐは転移装置を使えないの。第一部隊の往復分しか元素力を注入していないから、第一部隊が戻ってこないと......それにね、戻ってきても起動するだけの元素力を溜めるには時間が掛かるの」
「え? そうなのかい?」
こくんと頷くモルに目を丸くして玖苑は空木を見た。
「何で教えてくれなかったんですか?」
この春に防衛本部に入隊した玖苑とは違い、もう何年も志献官をしている空木が知らないはずがない。
「静かだったのでもう帰ったかと」
「ずるいなぁ! こんなのただの待ちぼうけじゃないか」
玖苑は教えてくれたモルをぎゅっと胸に抱くと、唇を尖らせて階段に座り込む。空木は階下の状況を気にしながらも、玖苑に小さく笑った。
「先日のやらかしがなければ、舎利弗君も行けていたんですけどね」
「先日のやらかし?」
いったいどの話だろう。きょとんと鸚鵡返しで見上げれば、空木は分からないのかと言うように玖苑に視線を向けた。
「廻遊庭園での防衛任務です」
「ああ!」
やっとどれのことを指しているのか思い当たって、玖苑は輝かんばかりの笑顔になる。話を聞いてほしい子供のように無邪気に口を開いた。
「虎を助けたんですよ、空木さん。あんなに美しい生き物がデッドマターなんかに呑まれてしまうのはもったいないでしょう?」
「報告書は読みました。檻から解き放ったとか」
「とってもいい子だったなぁ」
デッドマターの気配を感じて檻の隅で怯えていたのだ。檻を開けてやれば一目散に逃げてどこかへ行ったが、事が済んだらきちんと檻に戻ってくれた。気高く美しい獣だ。
空木は満足げに回想している玖苑に小さく嘆息する。
「命令違反をしたとの報告がありました」
「ボクの能力を全く生かせない作戦に意味なんてあります? 被害は最小限に抑えられたのに何の問題が?」
玖苑はひとつふたつと瞬きをすると、空木の答えも待たずに、そうか! と立ち上がった。
「だから、仁武だけを連れて行ったんだ! ボクを外すなんておかしいと思ったんです」
鐵仁武は玖苑と同期の鉄の志献官だ。今回の任務は当初、玖苑と仁武と、他四名の純の志献官で行われることになっていたが、直前になって玖苑だけが外されることになった。どうしてと聞いても、ちゃんとした答えが返ってこなかったのだが、ふたを開けてみればただの懲罰措置だったらしい。
「楽しみにしてたのにな」
今回の出動先である如月人工島は、湾内にある燈京よりも湾口側に位置する小さな島だ。元は海底資源開発の研究施設だったが、現在は封鎖されている。最近、その周辺で侵食圧の変動が観測された。実地調査を検討していた矢先にデッドマター形成体の発生が予測されたことを受け、侵食防衛の任務も平行して行われることになったのだ。
観測部によれば、不安定な揺らぎがあって正確な観測値ではないものの、四等級から三等級のデッドマターの出現が予測されている。当初の作戦では玖苑と仁武、その他三名の先輩志献官に加え、媒人と呼ばれる触媒の志献官の計六名の部隊編成となっていた。だが、先の理由で玖苑が外されることとなり、代わりの志献官が編成された六名での出動となったわけである。
「結合術を使う任務なんて滅多にないのに」
玖苑は、ねえ? と抱えているモルに同意を求める。困った顔をしていたのでそっと解放してあげると、足早に仕事に戻っていった。
結合術は媒人のみが使える特殊な術だ。志献官同士の精神(こころ)を繋ぎ、元素術や分子術には出せないような強力な技を使えるようにする。志献官同士が元素術を組み合わせて発動させる分子術とは違い、元素同士が反応しない元素を持つ志献官の力までをも結びつける媒(なかだち)をするのが触媒の志献官だ。
純の志献官が五人もいれば、四等級や三等級のデッドマター形成体は撃破できる。そこに触媒の志献官までもが加わったのは、念のために、という理由はもちろん、結合術の訓練も兼ねているからだ。部隊がなかなか戻ってこないのも、形成体が現れずに結合術の訓練ができていないからだろう。
玖苑自身も、純弐位に上がる前の任務で空木と結合術を使ったことがある。人によっては心の奥深くに触れられるため嫌がる者もいるだろうが、玖苑としては面白い体験だった。
(見えたものは、壮絶だったけどね)
あのとき触れた記憶のことを空木に告げたことはない。ただ、その記憶の一端を覗いたことで、空木漆理という青年への見方が変わったのは確かだ。
玖苑は、はあ、と溜め息をついた。
「帰ります。転移装置が使えないなら、ここにいる意味もないからね」
待っているのにも飽きてしまったし、と階段を下りていく玖苑に、空木が声を掛ける。
「舎利弗君」
「うん?」
振り返れば、空木がいつも以上に真剣な顔で玖苑を見つめていた。
「あなたの実力は誰もが認めるところでしょう。ですが、結合術は志献官同士の心を結ぶもの。身勝手な行動しか出来ないようならば、舎利弗君と結合術を使うことはできません」
「空木さんも?」
空木は一瞬怪訝そうに片眉を上げた。
「空木さんは個人的な感情に左右される人じゃないでしょう? それに、仁武もいるし、十六夜さんだっている。少なくとも三人とは結合術ができるじゃないですか。ボクの実力を僻んでお咎めのフリをして嫌がらせしてくるような人たちなんて、こっちから願い下げです」
「お咎めのフリの嫌がらせではなく、お咎めそのものですが」
呆れる空木に玖苑は溜め息交じりで首を振ってみせる。
「空木さん。ボクは失望しているんです。志献官ってもっと優秀な人たちの集まりなのかと思っていました。でも、半年もしない間に追い抜けるくらい大したことない人たちで驚いたんですよ」
いくら玖苑が混の志献官を経ずに純位になるほど強力な元素力を持つ志献官だとしても、入隊当初は喧嘩すらしたことのないずぶの素人だ。元素術を始めとする戦闘技術は、同じく純の志献官から入隊した仁武と共に一から叩き込まれた。
だが、そんな玖苑から見ても、先輩たちの戦い方はどこか未熟であり、結倭ノ国を護る最後の砦がこの人たちなのかと、心底がっかりしてしまった。
「ああ、空木さんは違いますよ。十六夜さんも」
玖苑が先輩志献官の中で一目置いているのは空木と、玖苑と仁武の教官である清硫十六夜純壱位くらいだ。それだって、あと数年も経てば並び立つか追い抜く自信はある。
以前それを十六夜に漏らしたところ、十年も志献官をやっているという彼は苦笑交じりに言った。
『最終賦活処置を受けられるだけで御の字だよ。ここ最近じゃ、純の志献官になれるだけの力を持ったヤツも減ってきてるし』
長く混の志献官として任務をこなしていたからといって、純の志献官になれるわけでもない。反対に、純の志献官になれるだけの力があれば、玖苑や仁武のように一日も混の志献官を経ることなく純の志献官になれる場合もある。
また、十六夜は玖苑と仁武を鍛えるに当たってこうも言っていた。
『純の志献官になれば身体能力は飛躍的に向上する。でも、だからってすぐに戦えるって訳じゃない。今のお前さんたちじゃ、形成体と戦ったところで、間違いなく何もできずにお陀仏だ。デッドマター相手じゃなくたって、賦活処置しただけの素人と、賦活処置してない達人が戦えば、達人が勝つのは道理だろ?』
三ヶ月で戦えるようにする、と豪語した十六夜が玖苑と仁武に求めていたのは、賦活処置を施した達人だった。
下積みがない分、玖苑と仁武は厳しくされた。最初の頃はさすがの玖苑も音を上げそうになったが、先輩たちの戦い方の甘さを目の当たりにすると、それがどれだけありがたかったかよく分かる。
「舎利弗君......」
空木は何か思うように目を細めると、小さく首を振った。
「──あなたの独善はいずれあなたをひとりにする。今のうちに改めることをおすすめします」
「できる人間ができない人間に合わせるんですか? それじゃあ、志献官は無力になっていく一方じゃないか」
玖苑は階下を見下ろした。玖苑の声はよく通る。先ほどから転移装置を監視している職員や混の志献官、モルたちがそれとなくこちらを気にしているのは、もちろん気付いていた。
「それに、ボクがひとりになるなんてあり得ませんよ。だってみんなボクのことが好きだろう?」
階下に手を振り笑顔を振りまくと、ふっと、場の空気が緩んだ。誰もが玖苑に好意的な表情を向けるこの瞬間が大好きだ。
そんな玖苑に、空木が深い溜め息をついた。眦が下がり、冷淡に見える表情に仕方ないというような苦笑が浮かぶ。
「ろくでもないことを言っているのに、どうしてか憎めないのがあなたのすごいところですね」
「ふふ。ありが──っ!?」
突如として鳴り響いた警告音に玖苑は手すりから階下を覗き込んだ。先ほどまで気にならない程度の静かな動作音を立てていた転移装置が、今では唸るように振動しながら、明らかに異常と分かる音を響かせている。
「空木さ──」
隣に空木の姿はなく、すでに階下へと向かっていた。
「如月人工島の侵食圧急上昇! デッドマターの人工島側の転移装置への干渉を確認! ──空木純壱位!」
観測部の志献官が悲鳴のように声を上げる。彼が振り返ったときには、空木はもうそこにいた。
「部隊の状況は」
玖苑も慌てて階段を下りる。空木に問われた観測部の志献官は強く頭(かぶり)を振った。
「先ほどから追っていますが、検知不能です」
「転移装置への干渉とは?」
「おそらく、転移装置が侵食領域下に入ったかと。こちらへの状況は未知数ですが──」
「何事もなく、とはいきそうにありませんね」
空木は職員の後ろからモニターを覗き込みながら問う。
「転移装置の緊急停止は可能ですか」
「無理です。今停止すると爆発の危険性が」
話している間にも、転移装置はガタガタと激しく振動を続けている。まるで、何かが向こうから押し入ろうとしているかのようだ。
「デッドマターがこっちに入ってくる可能性はあるのかい?」
「それは......可能性、だけならば」
玖苑が尋ねれば職員は言いよどむ。空木が考え込んだのは一瞬だった。
「全館へ通達。転移装置からデッドマターの侵入の可能性あり。志献官以外の職員及び民間人は速やかに退避。混の志献官は元素結界を準備。──舎利弗君」
「デッドマターが出てくるなら、ボクがここで倒すよ」
玖苑は鞭を手に転移装置の前に立った。
転移装置を直接破壊すれば、という考えも脳裏をよぎったが、ただでさえ爆発しそうだというのならばそれは後回しだ。さすがの玖苑も爆心地にいては命の保証はない。それならば、出てきたモノを処理してしまう方がよほど効率的だ。
「あなたも出て行きなさい」
玖苑はゆっくりと目を瞬かせた。
「──聞き間違いかな? ボクに逃げろって?」
「全員の退避が完了し次第、私の元素術で転移装置を凍結させます。窒息しますよ」
玖苑はぐっと押し黙った。窒素の志献官である空木ならば、確かにそれも可能だろう。上手く行けば、爆発もデッドマターの侵入も防げるはずだ。
「空木純壱位、部隊の皆さんが戻ってきていません!」
混の志献官の問いに空木は鋭く視線を向ける。
「防衛本部を死守することが最優先です。転移装置での救援が不可能な以上、志献官の生死は関係ありません」
空木は冷淡に切って捨てると、全員に退避を促した。室内の混の志献官、モルたちや職員が速やかに移動を開始する。その中でも観測装置にかじり付くようにしていた混の志献官が立ち上がった。
「志献官一名、帰還します!」
転移装置の振動が一層大きくなる。玖苑と空木は臨戦態勢を取った。戻ってくるのは、本当に志献官なのか。
咆哮にも似た轟音と共に目映い光が放たれたかと思うと、光の中から人影が崩れ落ちるように倒れ込む。
「鐵純弐位です!」
「動くな!」
転移装置の台の上で倒れたまま動かない仁武に駆け寄ろうとした職員に、空木が鋭く声を上げる。まるで時間が凍り付いたようだ。機械の唸るような作動音も呼吸を止めたように消えていく。
「て、転移装置、完全に停止しました。デッドマターの侵入はありません」
「──鐵君の救護を開始してください。先ほどの命令を全て撤回。警戒だけは怠らないように」
空木が言えば、息を吹き返したように皆が動き出し、仁武へと駆け寄る。玖苑もゆっくりと臨戦態勢を解いていった。
「鐵純弐位、意識ありません!」
「誰か医療班と担架を! 早く!」
慌ただしく動き回る彼らを見つめる玖苑の唇から、無意識に言葉がこぼれ落ちた。
「──みんなは?」
転移装置は死んだように沈黙している。そこから残りの志献官たちが戻ってくることは、ついぞなかった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら