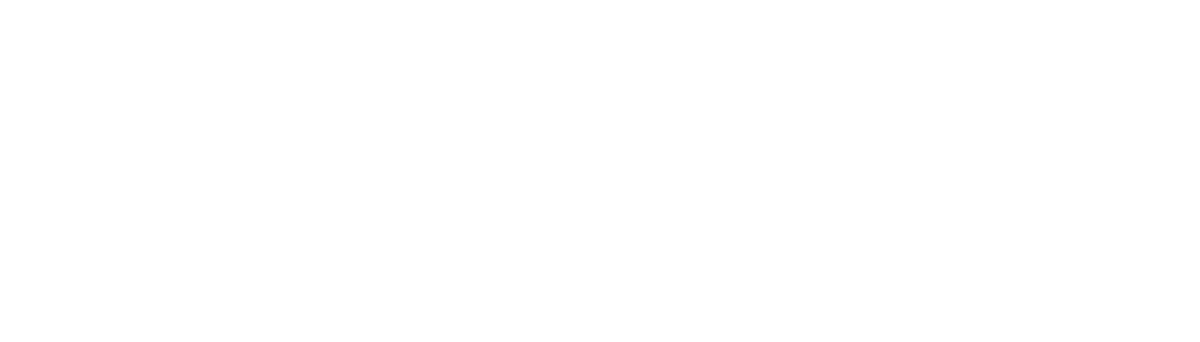INFO
24.09.11
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十- 舎利弗玖苑の結論(2)
著者:麻日珱
前回「断章-十- 舎利弗玖苑の結論(1)」はこちら
「──ちょっと留守にしてる間に酷いことになったな」
防衛本部の寮の食堂で傍らに置いた新聞を覗き込みながら十六夜がラーメンを啜る。
如月人工島での作戦から、三日が経った昼のことだった。
新聞には、燈京湾防衛戦成功の文字が大々的に躍っている。志献官の多大な犠牲者を出しながらも、燈京湾にふたをするように位置する如月人工島においてそれ以上のデッドマターの燈京湾への侵食を許さず、燈京を守り抜いたという内容の記事だ。
しかし、現実は違う。犠牲になったのは触媒の志献官を含む五名。失われた戦力の大きさは計り知れない。防衛本部の志献官や職員はそれが分かっているからこそ、憩いの場である食堂もどこか不穏な様子で浮き足立っていた。
「ねえ、十六夜さん」
十六夜の正面で頬杖をつく玖苑が名前を呼べば、フーフーとラーメンを冷ましていた十六夜がチラリと視線を向けた。十六夜とはちょうど十歳離れているが、指導教官として世話になっている分、空木よりも気安い。もちろん、本人の飄々とした雰囲気のせいもある。
数年来の仲間を一気に失ったにもかかわらず、十六夜は泰然としていた。他人事のよう、と言っても過言ではないほどだ。
「何でみんな死んだって決めつけるのかな」
防衛本部の中庭には殉職した純の志献官たちのための献花台が置かれている。玖苑も一応献花を終えていたが、仲間が死んだという実感はあまりない。
「何でってのは?」
玖苑は子供のように口をへの字に曲げた。
「だって、ボクらは志献官だ。侵食領域の中でも生きていられる。だったら、みんな、今もあっちで救助を待ってるかもしれないじゃないか」
転移装置は残念ながらあの一件で壊れてしまったが、如月人工島は燈京から船を出せばすぐに行ける場所にある。生きているかどうかを確かめに行くことは不可能ではないはずだ。実際、玖苑に助けに行ったらどうだろうかとそれとなく進言してくる者もいる。玖苑も、命令を待たずに行ってみようと港まで行ってみたが、許可が下りなかった。
「死んでるよ。残念だけどな」
「どうして?」
十六夜はすぐには答えずラーメンを啜る。今回の件で志献官の最年長になった男には、さほどの気負いもみられない。
「純の志献官は死んだらどうなる?」
「消えてなくなる」
「消えてなくなったあとは、どうなる?」
「どうって、お終いだろう?」
十六夜はちらりと周りに視線をやって、軽く身を乗り出すと声を潜めた。
「最終賦活処置で飲んだ"あれ"が防衛本部に戻ってくる」
「"あれ"って、賦活処置の"水"? 戻ってくるってどういうことだい?」
初めて聞く話に玖苑は目を瞬かせ、十六夜の方へと身を乗り出す。しかし、逆に十六夜は身を退いて片頬を上げた。
「これ以上は純壱位になってからだ」
機密だからな、と勢いよくラーメンを啜る。玖苑は拗ねるように口を尖らせた。
「そこまで言ったんだから、もったいぶらずに教えてくれたっていいだろう?」
「なに? 一緒に空木に怒られてくれんの?」
それはあまりよろしくない。空木は他のみんなとは違い、簡単に絆されてはくれないのだ。
「じゃあいいよ。ボクもすぐに純壱位になるから」
「お前さんなら今日にでも純壱位になれそうだけどな」
十六夜の言葉に玖苑はキラリと目を輝かせた。
「だよね? 十六夜さん、どうにかできない?」
「空木と交渉してみたら?」
「......十六夜さんの方が志献官歴も歳も上じゃないか」
「責任感が下だからかなぁ」
「そっか。だったら仕方ないね......」
今回の燈京防衛戦で命を落とした志献官のひとりは、純の志献官の所属する作戦部をとりまとめる代表の志献官だった。その彼の役職を急遽引き継いだのが、空木漆理純壱位だ。最年長となった十六夜ではないのは、司令からの信頼が十六夜よりも篤かったからだと聞いている。
玖苑が深く頷けば、十六夜はクツクツと喉の奥で笑った。
「お前の昇位は来年な。この一年は純弐位で経験積んどけ。純弐位参位は大して変わんねえけど、純壱位は重いぜ?」
「......」
「なーに、その疑わしそうな目は」
「別に? 十六夜さんにできるんだから、ボクにだってできると思ってね」
「指導教官になんつー言い草よ。それより、お前さんは平気か?」
「何が?」
「仲間がいなくなったのは初めてだろ」
「ああ......」
玖苑は軽く目を伏せた。
「よく分からないんだ。ボクは彼らの最期を見たわけじゃないから、実感が湧かない。それほど親しくもなかったし」
「そんなもんかね?」
「十六夜さんこそ、本当は強がっているんじゃないのかい? ボクよりもずっと付き合いは長かったろう?」
十六夜は苦笑すると首を振った。
「こんなご時世だ。いちいち落ち込んでちゃ、志献官なんてやってらんねえよ」
「そんなもんかな?」
「そんなもんさ」
頷いてから、十六夜はクッと笑った。自分の問いに自分で答える形になったのがおかしかったらしい。
「そうだ。聞いたか? 仁武が自分の部屋に移ったって」
「何で早く言ってくれないんだい?」
玖苑は勢いよく立ち上がる。ガタン、と椅子が立てた音に、周囲の視線がこちらを向いた。それににこりと笑顔を向ければ、反射のように笑顔が返ってくる。それを当然のものとして受け止めると、玖苑はテーブルに両手をついて身を乗り出した。
「十六夜さんはお見舞いに行った? まだなら一緒に行こう!」
仁武が目覚めたのは騒動の翌日のことだったが、面会が禁止されていた。その間、司令と空木による聞き取り調査が行われ、異常事態での転移による身体への影響がないか、精密検査が行われていたのだ。
自室に戻ったということは、身体に影響はなく面会が解禁されたのだろう。
「はいはい。これ食い終わってから行くから、先行ってな」
了解、と応じて玖苑は足早に仁武の部屋へと向かう。犠牲になった志献官の死に関しての実感はあまりないが、そこに仁武が含まれていたらさすがに玖苑も悲しい気持ちになっただろう。
玖苑は到着するなりノックして、返事も待たずにドアを開けた。
「やあ、ボクだよ! 仁武、元気かい? うわ、暗いな。カーテンくらい開けなよ」
「......玖苑」
うめくような声が闇の中に響く。
カーテンが閉め切られた部屋は陰鬱だ。夜でもないのにこうも暗くては、気分まで暗くなる。玖苑は窓際の寝台にある人影にチラリと視線を向け、ずんずんと部屋を横切った。足下のバーベルに気をつけてカーテンを片方引き開けると、高く澄んだ秋の空が広がっていた。
「ほら、見てごらん。いい天気だ! 怪我はどうだい? 命に別状はなかったって聞いてるけど、検査の結果は──」
「閉めてくれ」
ひび割れた声に玖苑は口を閉ざした。パチパチと目を瞬かせて仁武を振り返った。
「仁武?」
寝台に身を起こし、額を抑えて俯いている。大きく呼吸をしているのが、ゆっくりと膨らむ背中で分かった。志献官は怪我の治りが常人よりもはるかに早いのだが、やはりまだつらいのだろうか。
「大丈夫かい? 今回は大変だったね。でも、キミだけでも戻ってこられてよかったよ」
仁武の肩がピクリと跳ねる。
「......よかった?」
のろのろと上げられた仁武の顔に、玖苑はわずかに眉根を寄せた。この数日でだいぶ窶(やつ)れたようだ。生気がなく、感情という感情が抜け落ちている。暖かな色をしていた瞳は錆び付いたように濁っていた。
「そうだよ。よかったろう? 生きて戻れたんだから」
「......けど、俺以外は」
「志献官っていうのは、そういうものだよ。残念だとは思うけどね。ボクらはそれを承知でここにいるんじゃないか。それに、キミが生きているから、あちらで何が起きたのか分かるんだ。真実すらデッドマターに呑まれたなんて、そっちの方が最悪だよ。あの人たちも意地悪しないでボクも連れて行けばよかったんだ。そうすれば──」
「そうだろうな。お前だったら、皆助かってた」
「当然さ! ボクだからね」
「......ハッ」
まるで嘲(あざけ)るように短く笑い、仁武は両手で顔を覆った。
「ひとりにしてくれ。......お前とは、話したくない」
「落ち込んでいるときは打ち明けた方が気持ちが軽くなるって、母さんも──」
「頼むから」
淀みの中から聞こえてきたような声だ。そこに込められた憎しみにも似た嫌悪に、玖苑は息を止める。
「出て行け」
両手の下からどろりとした眼(まなこ)が玖苑を睨む。卑屈で、劣等感にまみれた目。こういう目をよく知っている。玖苑は浮かべていた笑みを消し去って──それどころか冷ややかに、その眼差しを受け止めた。
「はあ......どうやらまだ混乱しているみたいだね。お望み通り出て行くよ」
防衛本部に置いて行かれた玖苑とは違い、仁武は作戦に参加して壮絶な光景を目の当たりにしたのだ。ひとりだけ生き残って深く傷ついているのだろう。
(だからといって、そんな目を向けられるいわれはないけどね)
部隊が仁武を残して全滅したのは玖苑のせいではない。単純に、彼らの力不足だ。
労ろうという気持ちにケチがついたようで不愉快だった。それでも、仁武の置かれた状況はいつもとは違うのだからと、自らに言い聞かせて踵を返す。扉を開けると、ちょうどやってきていた十六夜が目を丸くして軽く身を引いた。
「っと。玖苑、もう帰るのか?」
「虫の居所が悪いみたいだ」
「はあ?」
ひょいと肩をすくめてみせる。十六夜は怪訝そうに玖苑と部屋の中を見比べた。玖苑は何か言いたげな十六夜の身体を押しのけて、その場をあとにする。
「──あ」
ぶらりと廊下を歩き出して気がついた。
「お腹空いたな」
そういえば、さっきも食堂にいたのに食べていなかった。お昼は何にしようかなぁ、と鼻歌交じりに食堂に着く頃には、仁武の部屋でのことなどすっかりどうでもよくなっていた。
それから仁武は、まるで人が変わったように訓練に打ち込んだ。それこそ文字通り、朝から晩まで。自分を痛めつけるような訓練だ。自分の力のなさを、相当悔いているらしい。だが、自分の弱さを嘆いて何もせず、グズグズと引きこもって落ち込むよりもずっとマシだと玖苑は思った。
「仁武、少し根を詰めすぎだよ」
玖苑が声をかけても、神楽武術堂でひとり刀を振るっていた仁武は一瞥(いちべつ)もしなかった。それだけ集中しているとも取れるが、あれは周りが見えなくなっているのだ。
(がむしゃらだなぁ)
刀が纏う元素力は、強いがそれだけだ。あんなもの、簡単に打ち砕かれるだろう。
玖苑は先日仁武と共に行った防衛任務を思い出した。
(この訓練の成果が"アレ"とはね)
全く、呆れてしまう。
デッドマターを前にして、それまでかみ合っていたはずの連携が一切取れなかった。仁武が玖苑を一切見ていないからだ。ならば、と玖苑が合わせようとしても、余計なことをするなと言わんばかりの戦いぶりだった。言葉を失ったかのように口を利かないし、玖苑と目も合わせない。
まるで、ひとりで戦う、お前にもできるんだから俺にもできるという声が聞こえてくるようだった。
「なんてつまらない人間になったんだ」
ぽつりとこぼせば、ピタリと仁武が動きを止めた。
なんだ、と思った。
聞こえてるじゃないか。
仁武は荒く肩を上下させながら玖苑を見た。強い眼差しは鋼のように冷たい光を帯びている。その奥には、あの日見たどろりとした劣等感が未だに──いいや、あのときにはなかった明確な敵愾心(てきがいしん)までもが宿っていた。卑小な人間の眼差しだった。
「どういう意味だ」
「そのままの意味だよ。毎日こんなに訓練をしているわりに、全く進歩が見られないようだけど」
仁武の顔が強ばる。玖苑は仁武の元まで歩いて行くと、その長身を見上げた。仁武はただ口を真一文字に引き結んでいた。
「言いたいことがあるなら言いなよ。キミの口は何のためについているのかな? 睨まれたところで怖くもなんともないね」
仁武は玖苑の同期だ。たった一歳違いで、同じように混の志献官を経ずに純参位で登用された鉄の志献官。ぎょっとするほど背が高いというのが第一印象だった。十六夜のもとで、共にゼロから志献官としての訓練を始めたところ、仁武は切磋琢磨するに相応しい好漢だと分かり、一緒に訓練しているのも楽しかった。仁武は時々融通が利かず、けれど面倒見がよかった。少し要領が悪いところはあったけれど、それだって、"玖苑に比べれば"と枕がつく。実力は申し分なく、これから長い付き合いになるのだろうという確信があった。
(勘は冴えてる方なんだけどな)
滅多に外すことはないのだが、今回は大外れだったようだ。仲間を失った直後ならば仕方がないと飲み込んだが、まだ続いているとなると今後もこれが続くのだろう。
(結局、仁武も同じか)
あの時もここだったな、と玖苑は神楽武術堂を見回した。卑怯者たちが結託して玖苑を傷つけようとした場所だ。
この世には、能力でも容姿でも、自分が玖苑と比べて劣っていることを恨んで、勝手に劣等感をぶつけてくる有象無象がいる。幼い頃はそんな相手とも仲良くしようと試みていたが、大抵ろくなことにならない。しかも、玖苑が関わろうと関わるまいと、勝手に潰れてどこかへといなくなるのだ。
いつからか、そういう輩は玖苑の目の前を通り過ぎる風景のような存在になった。ほんの一瞬、視界の端に映っては不快な気持ちを残して去って行くだけの存在。そんなものは、気に掛ける価値もない。
それが、今の仁武だ。
玖苑は、はあ、と溜め息を付いた。
「仁武、キミってなんてつまらないんだい?」
その錆色の目がゆるゆると見開かれる。玖苑は最後に仁武の肩をぽんと叩いた。ただの風景にそれ以上言うことはない。
神楽武術堂を出た玖苑は、秋の空の高さに目を細めて街へと繰り出す。玖苑に気づいて手を振る通行人に手を振り返し、途中で街の人に焼きたてのパンをもらったり、お菓子をもらったり、花をもらったりしながら歩いている内に、すっかり気分も良くなった。
「やっぱり、こうでなくちゃね」
不愉快な相手にかかずらっていたところで、心はひとつも豊かにならない。つまらないことは楽しいことで忘れてしまうに限る、と玖苑は寄り道をして帰ることに決めたのだった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら