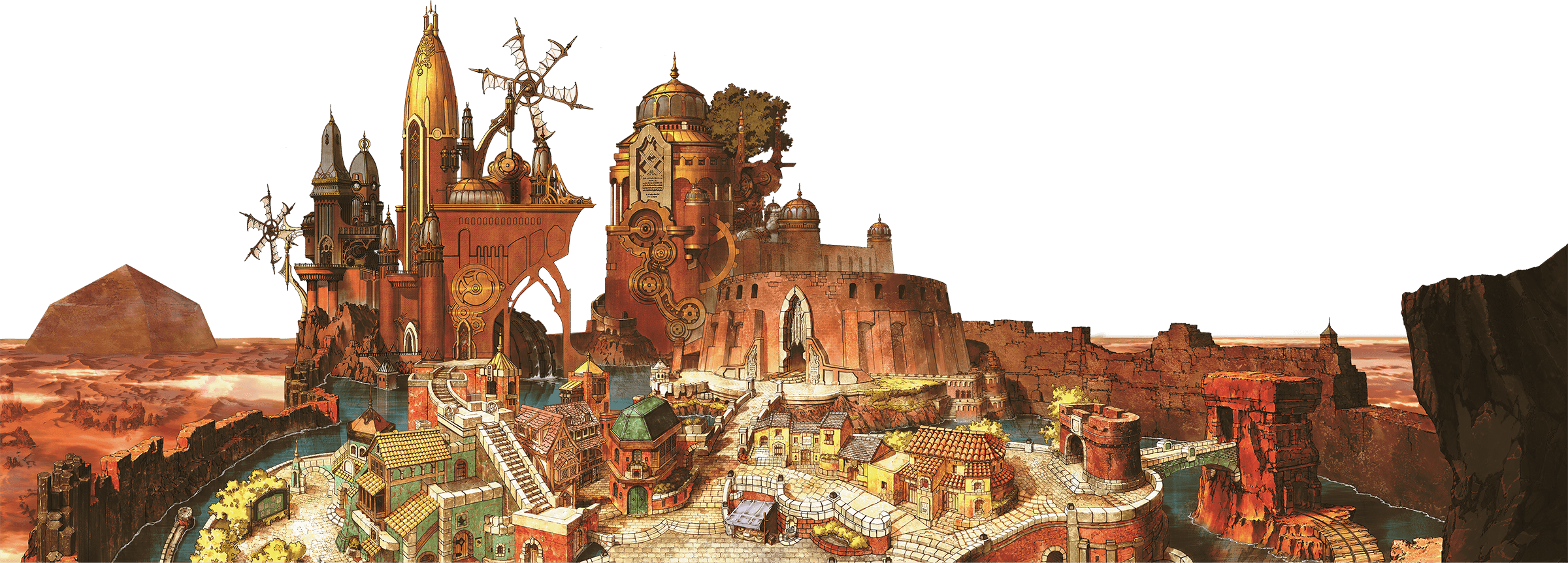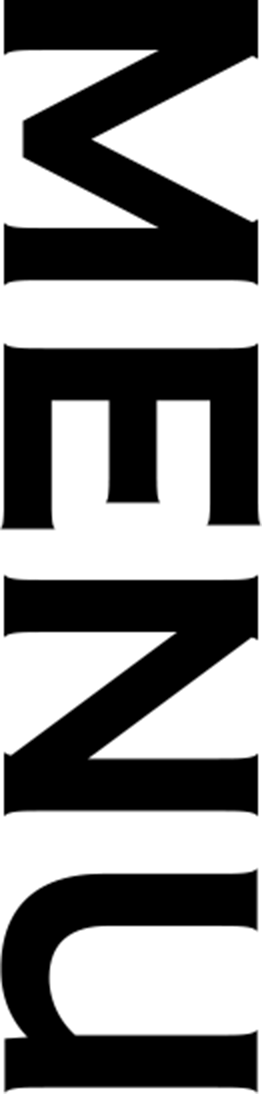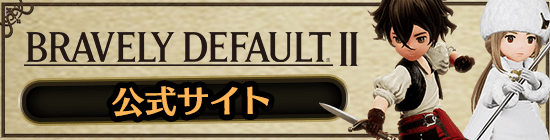BRAVELY DEFAULT BRILLIANT LIGHTS
REPORT錬⾦ゼミ活動レポート
[第008章] 8-15
もうひとつの真相
時折遭遇する魔物と戦いながら、薄暗い回廊を歩いていると、先頭を歩いていたスティールが立ち止まった。
(また魔物?)と身構える僕たちに、小さくかぶりを振ってそうではないことを示したスティールは、身をかがめて石床をしげしげと見つめる。
「ところどころバハムートの足跡がなくなっているんだ」
スティールの特技ともいえる『足跡読み』によると、ドモヴォイ最高司祭の足跡はずっと続いてて辿れるのだが、バハムートの足(と尻尾の)跡は、時折長く途切れているというのである。
ドモヴォイ最高司祭の足跡は、以前からのも含めてそれこそ無数にあるのでバハムートの足跡を主に辿ることになる。
それが途切れると、かなり動揺するらしい。
「バハムート、飛ぶからな...」
オミノスさんが、何を今さらとばかりにつぶやく。
「あんなボッテ...」と言いかけ、あの性格に難がありそうな顔つきで睨まれた僕は、慌てて「ポッチャリした体で?」と言い換える。
オミノスさんのアドバイスを受けたスティールは、目を細めて少し離れた床を眺めると、
「おう! たしかに、少し向こうにバハムートの足跡があるな」
...と、そう言って小さくうなずく。
僕たちは、再び奥へと歩き出した。
***
ひと際明るく暖かな祭壇の前にドモヴォイ最高司祭とバハムートの姿が見える。
「ふむふむ、神竜様は余の善政を喜んでおられるというのじゃな?」
まるでバハムートとの会話を楽しむかのようにうなずいているドモヴォイ最高司祭に対し、(おじいさん何を言ってるの?)とばかりに首をかしげるバハムート。
「それで? 神竜様は、民に何を望むと仰っているのじゃ?」
バハムートは、(ぼくをオミノスのところに帰して)と、バハバハ訴えるも、
「おお、そうかそうか。もっと神竜様へ祈りを捧げよ、と...。そうじゃろうそうじゃろう」
...と、まるで話が噛み合っていない。
***
「バハムートはそんなこと言ってないのに...!」
ドモヴォイ最高司祭とバハムートのやり取りを物陰から眺めているオミノスさんが声を押し殺してつぶやく...。
いいとこ「オミノスのところへ帰して」ぐらいだろう? ...と予想したスティールは、むしろこの状況であんな思い違いができているドモヴォイ最高司祭の方がおかしいのだと断じる。
それはまるで、バハムートがそう言っていると信じたがっているようにも見えた。
***
再びドモヴォイ最高司祭とバハムート...。
「...バハよ、そなたは優しいのう」
ドモヴォイ最高司祭の声色が、どこか悲しみに染まってる。
「そなたのいうことなどわからぬ余に、それでも何かを伝えようとしてくれておる...」
ドモヴォイ最高司祭は、自身の言葉がバハムートに通じていないことを知っていた...。
それでもなお、バハムートとの会話に執着した理由はなんなのだろう?
ドモヴォイ最高司祭は、ぽつりぽつりと語りだした。
「...50年前、あれほど理想に燃え、仲間たちと世界を巡ったというのに...、火のクリスタルは余に啓示を与えなかった...」
「失意に打ちひしがれた余は、故郷のライムダールに戻り神官として精進し
修行に励んだ」
「しかし...、いくら修行に励んでも、いや、位階を昇れば昇るほどに、神竜様の声はおろか、民の声まで...まったく聞こえぬのだ...」
ドモヴォイ最高司祭はがっくりと肩を落とし、優しいバハムートはそれを慰めるようにバハバハ言っている。
やがてドモヴォイ最高司祭は驚くべきことを口にする。
「あの女がもたらしたオクラルのアスタリスクと...ヘリオがもたらした火のクリスタル...」
ミューザで奪われた火のクリスタルが、ここにある!?
僕たちは、弾かれるようにそれぞれの顔を見合わせる...。
(ヘリオ審問官が、火のクリスタルをもたらしただって...?)
ミューザで支配人と呼ばれた男が、「火のクリスタルを奪っていったのは、導師のアスタリスクを持つ糸目の男で司祭とあだ名されていた」と言っていたことを僕たちは知らない。
しかし、マルグリットさんや町の人たちが口々に神竜の御子が現れてから寒さが緩んだように思えるようになったと言っていたことや、教団が町の各家・各施設に中央管理型の暖房を敷設できていること、なによりもルミナの祈りによってこの時空に僕たちが転移されたという事実が、すべて火のクリスタルの存在を物語っていた。
「そしてバハ、お前がいれば、余にもきっと...。今はまだお前の言葉はわからぬ...しかし、いつの日か、いつの日か...」
ドモヴォイ最高司祭が見上げた視線の先には、赤く輝く火のクリスタルが鎮座していた...。
***
「おい、バハムートの好物は?」
スティールが小声でオミノスさんに問う。
「え? あ、...僕のファイア、ファイラも...」
急に聞かれてオミノスさんが慌てて答える。
「攻撃が好物なのかよ」
「ファイアドゴンは、炎を吸収すんだよ」
2人の小声のやり取りが続く。
「炎を主食にするなんて、効率いいんだな」
そう感心するスティールに、オミノスさんが食って掛かる。
「主食なわけないだろう!! バハムートにとって炎はあくまでもミルクみたいなもんさ。お前らだって大人になったらミルクだけでは満足しないだろう?」
バハムートは、人間と同じように何でも食べる雑食らしい。
見るからに大食漢のバハムートが、ライムダール正教がふるまった山海の珍味に手を付けずげっそりしたというのも、オミノスさんと離れ離れになって寂しくて寂しくて...といったところか。
「なるほど。よし、じゃあできるだけ静かにバハムートにファイアを放つんだ。できるか?」
スティールの問いに、オミノスさんは無言でうなずく。
火のクリスタルは、今は放っておく。
ドモヴォイ最高司祭がよそ見をしている隙に、好物の炎を合図にしてバハムートをおびき寄せる。
バハムートがいなくなれば、また誰かにかどわかされたかと探しに行き、あの火のクリスタルが鎮座する祭壇はもぬけの殻になる...という寸法らしい。
オミノスさんが指先から出した小さな炎は、ゆっくりと空中を漂い、バハムートの逞しい背中に当たった。
「バハ...!!」
バハムートがのっそりとこちらの方へ振り返り、オミノスさんの姿に気づくと嬉しそうに小さな羽をパタパタと羽ばたかせる。
ドモヴォイ最高司祭は、まだうつむいて何かをボソボソ言っている。
巨大なバハムートが目の前で浮かび始めているのにも気づいていない。
「よし、バハムート! そのままこっちに来い...!」
バハムートが、物音ひとつ立てずにボヘボヘと飛んできて、オミノスさんと再会を果たす。
「バハムート、無事でよかった。心配したんだぞ~!」
「バハッ、バハ~~~ン...」
2人はなるべく音を立てないようにじゃれ合っている。
「よし、あの爺さんがどこかに行くまで、しばらくどこかで時間をつぶすぞ」
僕たちは、火のクリスタルとドモヴォイ最高司祭が残る祭壇を後にした。
***
火のクリスタルがあった広間にドモヴォイ最高司祭を残し、僕たちは身を隠すべく薄暗い回廊を進んだ。
「おっと...」
スティールが急に立ち止まり、うつむいて小さくかぶりを振る。
「すっかり忘れていた存在を思い出しちまったよ...。俺たちと一緒にこの世界にやってきたヤツらがいるだろう?」
...そう言うやいなや、すっと息を吸って、前方の通路の曲がり角に向かって怒鳴る。
「そこで待ち伏せしていやがるザレルのヤツら~! バレバレだぜ~。出てきやがれ!!」
(ああ、いたね~そういや...)
***
回廊の曲がり角から、少しだけばつが悪そうに現れたのは、火の将王麗とその配下たちだった。
僕たちの会話を聞いていたらしく、火のクリスタルの在処に関しても、もう知っているらしい。
「じゃあ、なんで俺たちを黙ってやり過ごさなかったんだよ」
スティールに痛いところを突かれたのか、火の将王麗が忌々しげに扇を振り下ろす。
「あなたたちに、先日のお返しと、一言いっておきたいことがあるのよ!!」
そう叫ぶと指輪を掲げ、僕たちごと光が包み込んだ...。
***
(最近、この石柱を見てばかりだ...)
僕は、あの宙空を音もなく浮遊する巨大な石柱を眺めていた...。
「オミノスさんたちは、入ってこれなかったみたいね」
「ったく、いったいどんな内緒話をしたいんだろうねぇ」
クレアがカバンのフタのベルトを外しながら、サンディが指をポキポキ鳴らしながら話している。
スティールも足の屈伸をしていると、王麗の配下はあの見慣れた壺を持ってきて王麗の傍らに置いた。
「おいおいおい...、それって魔封じの壺じゃねぇか!」
「あら、ザナ・ウルスの奥地に伝わる秘術中の秘術、『魔封じの壺』を知っているなんて...」
以前、S・ビリーが「ひと月ほど前に略奪した村で手に入れた」と言っていたが、ザナ・ウルスといえば、確か風の将ナンナンの故郷ラヴィヤカを侵攻しているザレル・ウルスの兄弟国だったはず...。
S・ビリーは、そんな東方にまで進出していたということか...。
「割ったら光の球が出てきて、そこから魔物が出てくるんだろう?」
スティールのその言葉を待っていたかのように、王麗は壺を叩き割る...!!
***
「アンギャァ~~~~~~~~ッ!!」
光の球がスパークした後に出現したのは、赤い竜...サンディによるとルクセンダルクのサラマンダーというドラゴンだった。
「ったく、ドラゴンが1匹しかいない大陸の神竜信仰の国に、何ややこしいヤツ出してんだよ!」
スティールの言い分も最もだったし、王麗もまたそう思ったようだ。
真っ赤にした顔を隠すように、手にした扇をばっと前方に差し出した。
「う、うるさいわねっ!! さあ、ブラスの者たちよ、覚悟しなさい!!」
***
激戦の末、サラマンダーの巨体が大きな音を立てて地に伏し、霧散した...。
「や、やるわね...!! さあ、休ませなんかしないわよ~!」
僕たちが休む間もなく、王麗とその配下たちが襲いかかってきた!!
***
ずいぶんと長く続いていた戦闘が、火の将王麗が片膝をついたことで一旦終わりを告げた。
王麗の肩は、荒れる呼吸で大きく上下している...。
(お前もな...)
(ルーファスは両膝ついてたねぇ、そん時...)
(うんうん。腕もダラーンとして両手の甲も地面についてたわ)
(他人のレポートに口出しはやめてもらいたいんですけどー)
「この間の仕返しは失敗に終わったなぁ、王麗さんよ」
そう語るスティールの息も弾んでいる...。
(いやだからな...)
(ぅるっさいな~もう!)
余裕をもって「前に俺がした質問に答えてくれねぇか?」などとかましたスティールであったが、火の将王麗が、「旧クランブルス王国宰相ランケード伯を知っていた」と答えると少なからず驚き、微かに身構えたようにも見えた。
「そ、そうかい...。それで、いや、やっぱ最低最悪の男だったのか?」
「最低最悪の、とは...?」
心なしか、スティールの方が不安げに、王麗の方が静かな怒りを湛えているようにも見える。
「そりゃそうだろうよ。幼王と王都の民を棄て、保身のためにザレルの陣営に走った男だ」
敵側の王麗からも同じような反応が返ってくるとばかり思っていたスティールだったが、
「...クランブルス側には、そんな風に伝わっているのですね...」
王麗の表情にさっと悲しみの色が走ったためか、軽く狼狽えている。
もう、2人とも息は収まっている。
僕は、まだ...。
2人の話に聞き耳をたて、内容を理解するのに精いっぱいだった。
***
王麗は、20年前の出来事を思い出すように話し始めた。
「...あの日、ザレル側が数か月前に宣戦布告をしていたというのにクランブルス王都は、実に穏やかなものでした」
「ザレルの一撃目で王都の隔壁が...、二撃目で城門が破られ(あまりの無抵抗ぶりに逆に罠の危険性を感じたため)わが軍は一度兵を退きました」
「そこに宰相ランケード伯の馬車がやってきたのです」
そこまで聞いて、スティールが肩を落とした。
「そうか...、やっぱりな...」
その姿を見た王麗の表情が再び険しくなる。
「何を勘違いしているのです...」
「ランケード伯は、わが軍の非礼を詰りに来たのですよ?」
意外な言葉に、スティールはまなざしを上げる...。
ランケード伯とその従者は、屈強なザレルの諸将が居並ぶザレル大王の幕舎に通された。
血の気の多い猛将たちが、口々に伯に罵声をあびせ、嘲笑う中、伯はその小柄な体からは考えられぬほどの大音声で諸将らを一喝し、ザレル軍のクランブルス王都の奇襲についてその非を並べ、反論する大王の幕僚たちをひとりひとり、丁寧に論破してゆき、ついにはその場は水を打ったように静かになってしまったという。
王麗がなぜそれを知っているのか...。
実は、ザレルの重臣であった王麗の父親王嵐は、ランケード伯と激論を交わし論破された者のひとりになるという。
ランケード伯の到着からどのくらいが経ったことだろう...。
すっかり静まり返った幕舎の中にようやくザレル2世が登場した。
先ほどの騒ぎをまん幕の陰で聞いていた御年17歳の少年大王は、ザレルの諸将をたったひとりで遣り込める敵の宰相に興味を抱いていた。
本来ならば、首だけを従者に持たせ王都に返すところを、大王自ら引見し、あろうことかランケード伯を登用しようとしたというのだ。
忠臣...王麗は、この言葉を強調して言った。
「しかし、忠臣のランケード伯は、首を縦には振らなかった...」
ザレル大王がどれだけ財物を積もうが、どんな地位を約束しようが、
「私は、クランブルス王の臣でございますれば...」
...と、静かに、胸を張って答申したのだという。
それでもなお...大陸の西方一帯を支配しようとしている自分になびかぬわけはあるまい...そう過信したザレル大王は、さらに高位の役職をもって伯の心変わりを望んだが伯は、
「私は、クランブルス王を、王都の民を裏切るわけには参りませぬ...! それは、大王の重臣や将軍たちが、(財貨や役職などにつられて)大王を決して裏切らぬようにです!!」
...と言い放ち、隠し持っていた短刀を喉にあて、大王が止める間もなく、地に伏し、絶命したのだという。
(僕たちが聞かされていた巷の噂と、まったく違うじゃないか...)
目を伏せたスティールが、小刻みに震えている...。
勇敢なるクランブルスの忠臣、ランケード伯の死を悼んだザレル大王は、王都攻撃の停止を命じ、3日間の喪を発した。
クランブルス王都へは、3日後にあらためて宣戦布告した。
大王が王都の土を踏んだとき、王都の約半数がいずこかへ去り、半数がザレルに投降したという。
「スティール、あなたの御尊父は、民のため、そして幼い王子を落ち延びさせるため、たったひとりで敵陣に赴き、堂々たる論陣とその命をもって、我が軍の総攻撃を遅らせたのですよ」
まるで師のように、そして姉のように...王麗がスティールに言い聞かせる。
「あれほど見事な貴族は、後にも先にも会ったことがない」
それは、王麗が今でも憶えている、父王嵐のつぶやきであるという。
***
配下に促され、王麗は引き揚げを決めた。
立ち尽くしたスティールは、一言も発せずにいた。
去り際、王麗は、スティールにというよりは僕たち全員に向かって言った。
「...そうだ。クランブルス四家には気をつけなさい」
ザレルの宣戦布告は、当時王国の実権を握っていた四家宛てにしっかりとしたはずなのに、王都の防備はまったく間に合っていなかった。
そして、ランケード伯の忠烈な自裁についても、ザレル大王から四家の筆頭、アルデバイド家に報告がいっていたはず...。
「それなのに...」
口惜し気に一度目を伏せた王麗は、いつものような、よそ行きの笑顔を作って優雅に去っていった。