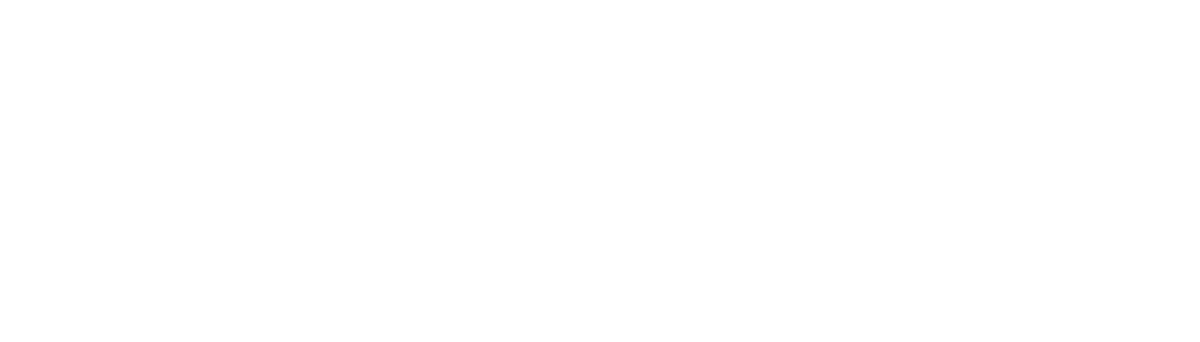INFO
24.07.07
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-七- 浮石三宙の空言(3)
著者:麻日珱
前回「断章-七- 浮石三宙の空言(2)」はこちら
パン、と掌が容赦なく頬を打つ。
家に戻った三宙を待っていたのは、母の平手打ちだった。身構える間もなかった。
叱られることは覚悟していたが、まさか弁明も許さず叩かれるとは思わず、じんじんと痛む頬を抑えて呆然と母を見上げた。どんなに厳しくても、これまで一度だって手を上げられたことがなかったからだ。
「愚かなことを!」
眦(まなじり)を決した母の、見たことがないほどの恐ろしい形相に三宙は首をすくめた。
「因子検査を受けたのですか!」
「受けてなんて......」
「嘘をおっしゃい。この母は騙せませんよ。いつからそんな嘘つきになったのです」
嘘つき、という言葉がずんと胸に伸し掛かる。
(嘘なら、もうずっとついてる)
何も考えず、言われるがままに浮石家の跡を継ぐこと。それを受け入れている自分は嘘まみれだ。
「......教えてください。なぜ、ボクにひと言もなく因子検査を拒否したんですか」
「必要がないからです」
「でも、もしもあったら......」
「関係ありません。浮石家は志献官の義務を免除されています」
「......免除?」
知らない話だった。三宙は目を瞠った。母は痛ましそうな顔で熱を持つ頬を撫でた。自分が打ったことなど忘れてしまったように。
「三宙さんはまだ知りませんでしたね。浮石家は源家同様、代々リチウムの因子を持つ家系なのですよ」
「......は?」
母は呆然とする息子をそっと抱き寄せた。
「志献官は危険な仕事です。どうか、母の気持ちを分かってください」
「じゃあ、お母様はボクに因子があるって知っていたんですか」
「お父様もそうですもの。予想はしていました」
「どうやって、免除なんて......」
「浮石家ともなればいかようにもできます。この世にはお金で解決できないことはありませんし、誰も浮石に逆らおうなどとは思いませんから」
三宙は震えた。自分に絡みつく腕が途端に不快になる。母の肩を押して思い切り遠ざけた三宙は、後退しながらぎこちなく首を振った。
「そんなの、間違ってる」
「浮石は間違いません。ひとり息子をあんな危険な組織に捧げるわけがないでしょう」
「お母様!」
母がぐっと三宙の肩を掴む。三宙は威圧するような眼差しから目を逸らした。
「己の命を賭して戦うなど、浮石のすることではありません」
「やめてください、お母様......」
「たとえ三宙さんに適性があろうとも、志献官にはさせません。あなたは家を継ぐのです。分かっていますね?」
「......いやです」
「なんですって?」
三宙は肩を握りしめる母の手を振り払った。
「いやだ! オレだって志献官になりたい!」
はっきりと口にしてやっと、その感情がストンと三宙の中に落ちてきた。
「三宙さん、あなた......ああ」
母は息を呑み、わなないた。よろけたところをそばに控えていた使用人の女性がさっと支える。母は着物の袖で顔を隠し、その影から恐ろしい物でも見たような目を三宙に向けてくる。
「あの子のせいね」
「え?」
「源の次男です、あの子のせいでそんな世迷い言を」
「それは......」
言いよどむ三宙の肩を、母は再び強く掴んだ。
「あの志献官狂いの源が、三宙さんを唆(そそのか)したのよ」
聞いたこともないほどの低い声は、まるで呪詛のようだった。ぞっと背筋が寒くなる。
「志献官狂い......?」
あまりの言葉に目を瞠る。源家が志献官狂いなら、浮石家は何だ。浮石、浮石浮石とそればかり。狂っているというのなら、金にものを言わせて義務を逃れるこの家こそが狂っている。他人を嘲笑える立場ではないはずだ。
「今後、源家の次男とは距離を置きなさい。いいですね?」
「お母様、ボクは──」
「口答えは許しません。あなたは浮石なのです。志献官などという野卑な職に就くような人間ではないのですよ」
狂気じみたその目に唖然とする。
「──浮石じゃないオレに、価値はありますか?」
それは無意識に出た言葉だった。母が怪訝そうな顔をする。それで全部分かってしまった。
「お母様は、オレの人生なんてどうでもいいんですね。浮石のメンツが保たれれば何だっていいんだ」
三宙の人生は、生まれたときから三宙のものではない。浮石家という大きな存在を維持するだけの部品。そこに自分の意志はなく、ただ相応しいカタチに当てはめられるがまま、動かされるままに設置されるばかりの人生だ。浮石家が上手く回れば誰でもいい。浮石家の血統に拘っているから、三宙でなければならないというだけ。
その程度の部品だ。
「オレが出来損ないだったら? 勉強も身につかなくて、何をしてもうまくできなくて、家を傾かせるだけのどうしようもないろくでなしだったら? それでも、オレに価値はあるんですか?」
「そんな人間は浮石にはいません」
「だからっ──!」
三宙は歯を食いしばった。母の眼差しは静かで、三宙の言葉などひとつも届いていないようだ。
悔しさで涙が込み上げた。ゆらゆらとこぼれそうになる涙を乱暴に拭う。
「──オレは志献官になります」
「三宙さん!」
追いすがる母の腕を振り払う。奥様、と慌てた使用人の声がしたが、三宙は振り返らなかった。
『僕は志献官になるんだ』
幼い日の朔の声が浮かんで消えた。あんな希望に満ちた決意ではない。ただの子供の癇癪だ。分かっている。でも、もう我慢できなかった。
「──三宙」
二階の自室へ向かおうとして、低い声に呼び止められた。父だ。今日は帰ってくるのが早い。使用人に帽子とインバネスコートを預けながら三宙を見ている。
「......」
三宙は口を固く結んだまま、お帰りなさい、さえ言わなかった。父が怪訝そうに眉をひそめ、口を開こうとする。
「あなた! 三宙さんを止めてください」
父の視線が母の叫びに向いた瞬間、三宙は階段を駆け上がった。
後ろ手に部屋の扉を閉めて、ずるずると座り込む。いっそ声を上げて泣きたくなる感情を、荒く息をついて押さえ込んだ。
「ふざけんな......」
何が浮石だ。こんな家に生まれたくて生まれたんじゃない。譲れるのなら譲ってやりたいくらいだ。
膝を抱えてうずくまっていると、コンコン、と扉が叩かれた。
「──三宙。私だ」
父の声だった。母から事情を聞いて叱りに来たのだろうか。三宙は無視をして黙り込む。
「少し出かけないか。話をしよう」
(......話)
三宙はゴシゴシと顔を拭ってゆっくりと立ち上がると、細く扉を開けた。隙間から見た父は、少なくとも怒っている様子はなかった。
「......お母様は?」
「興奮しているようだから落ち着かせているよ」
おいで、と促されてとぼとぼとついていく。玄関を出れば、車止めに止められた自動車のドアを運転手が開けた。
「どこに行くんですか」
「乗りなさい」
促されて渋々乗り込む。父もそれに続いた。運転席の後ろに座るのはいつも父だったから違和感がある。運転手がドアを閉めれば、息苦しさが車内を支配した。三宙はただ膝の上で握り締めた両拳だけを見つめる。
父は口数の多い人ではなかった。少なくとも、家族の前では。家にいることも稀で、ふたりきりになることはもっとない。こんな逃げ場のない場所でこれから説教されるのかと思うと身が縮むようだった。
「因子検査を受けたそうだな」
「......!」
三宙はハッと顔を上げた。父は窓の外に視線を向けている。その横顔から感情を読み取ろうとしたが、淡々とした顔には何の感情も出ていない。だが、母に話を聞いたのならば父も三宙を叱るつもりなのだろう。嵐の前の静けさのようで緊張はいや増した。握り締めた両手にじわりと汗が滲む。
「──三宙には浮石家と防衛本部について、まだ話をしたことがなかったな」
「え?」
予想に反する言葉に三宙は虚を突かれる。父は記憶を探るように一度目を閉じた。
「初代の志献官たちが燈京を再生させたのち、防衛本部を設置し、結倭ノ国が建国された。このとき、経済的に多大な貢献をしたのが浮石家だ。浮石家にリチウムの因子があると判明してからも、経済的支援の謝礼のひとつとして志献官になることが免除されたのだ。以降、浮石家の血筋にリチウムの因子が出やすいと分かってからは、支援と引き換えに志献官の義務が免除されることになっている」
「......お母様は、違う言い方をしていました。まるで、義務の免除をお金で買ったかのような」
「間違ってはいないだろう? 経済支援とは名ばかりの買収だ。だが浮石家は結倭ノ国を支えている。そう易々と次代を担う後継者を差し出すことはできない」
三宙はぎゅっと口を閉じた。父がドアに軽く肘をつく。相変わらず、表情の読めない顔で窓の外を眺めていた。
「私の子供の頃は、志献官どころか、防衛本部の存続自体が危ぶまれていた」
遠くを見ていた父の視線がゆっくりと三宙を捉える。四十路を前にした父は、その眦に小さく皺を寄せて目を細めた。
「デッドマターの侵食も沈静化し、このまま収束を迎えると思われていた時代だった。以前の生活を取り戻そうと、皆が復興に立ち上がった頃だ。浮石家も、燈京や横浜の発展に力を入れたよ。今では考えられないほど、平和だった。だから、防衛本部はもう必要ないと──志献官という、特別な力を持った存在に対する忌避感も、今よりもっと酷かった。志献官になろうなどと思う人間はほとんどいなかったんだ。もちろん、私も例外ではない」
初めて聞く話だった。朔もそんな話はしたことがない。興味深く耳を傾けながら、三宙はこくりと頷いた。
「だから、志献官になど憧れたこともなかった。私よりも下の世代は防衛本部が盛り返したあとだから、また違うのだろうが──」
父は物憂げに視線を窓の外へ戻して口を閉ざす。そのまま目的地に着くまで父は一言も喋らず、三宙も質問できなかった。
自動車はどんどん人気のないうらぶれた地域へと向かっていく。前方を見れば、目隠しなのか、広く高く張り巡らされた幕が壁のように立ちはだかっていた。
「......お父様、ここは?」
問いかけている間に車が止まる。何も答えずに車を降りる父のあとに慌てて続き、三宙はぽかんとそれを見上げた。でかでかと安全第一と書いてある。工事現場だろうか。
「浮石家(うち)で請け負っている現場だ」
父が幕を上げて待っている。三宙は急いで父の腕の下をくぐり抜けると、ぎくりと足を止めた。
「もう何年も前にデッドマターの侵食でやられた場所だよ。未だ、復興の目処は立っていない」
「......こんな」
三宙が燈京にいる間にこんな被害が起きたとは聞いていないからそれ以前だろう。
地面や建物が所々不自然に丸く抉られている。心なしか色あせて、まるで、生命力を吸い取られてしまったかのように寂れていた。
「ここに住んでいた人たちは?」
「生き延びた者は他の場所に移り住んでいる」
生き延びた者は。つまり、亡くなった者もいるのだろう。三宙は小さく身震いをして無意識に父のそばに身を寄せた。
「デッドマターと戦うということは、これと向き合わなければならないということだ。憧れだけでなるものじゃない」
父を仰げば、少し困ったような眼差しとかち合う。そのとき、三宙はようやく志献官を諦めさせるためにここへ連れてこられたのだと気がついた。現実を見せに来たのだ。
母に頭ごなしに否定されたときよりも感情は落ち着いていた。それでも絶対志献官になるのだと意固地になるほどの覚悟はない。
「でも......朔は志献官になるって」
父は目を瞬かせて怪訝そうに眉を寄せた。考え込むように空を眺めて、いや、と小さく首を振る。
「それは難しいだろう」
「どうして?」
父の大きな手が三宙の頭に乗った。くしゃりと癖のある髪を撫でる。
「碧壱君がいるからな」
父はそれ以上口を開かず、三宙を現場から連れ出した。兄がいるとなぜ難しいのか答えを得られないまま、父子は家路についたのだった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら