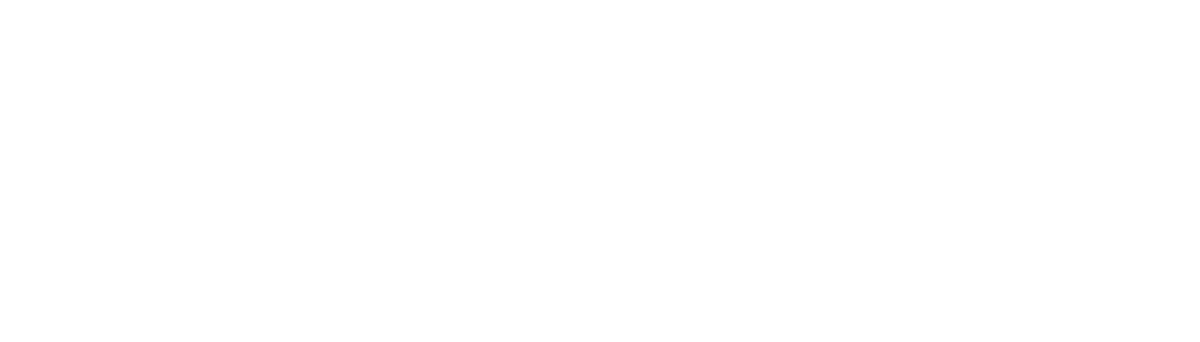INFO
24.07.10
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-七- 浮石三宙の空言(4)
著者:麻日珱
前回「断章-七- 浮石三宙の空言(3)」はこちら
「浮石くん。源くんが呼んでるよ」
「え?」
ある日の休み時間、教室で雑誌をめくっていた三宙は顔を上げた。教室の後方の出入り口に、固い顔をした朔が立っている。無視してもよかったが、詮索するような同級生の視線が煩わしくて三宙は席を立った。
「何?」
「今、ちょっといいか」
「別にいいけど......」
三宙が頷くなり、朔はさっさと背を向けて行ってしまう。付いてこいということだろう。従うのも癪に障ったが、それよりもどこか様子がおかしいことの方が気になった。
朔はひとけのない場所まで三宙を連れてくるとようやく足を止めた。三宙に背を向けたまま、大きく深呼吸をしているのが、上下する肩で分かった。
「──僕には志献官の適性がないらしい」
「は?」
聞き間違いだろうか。適性があった、ではなくて?
朔は意を決したように三宙を振り返る。堪えるように唇を引き結び、朔は自分に言い聞かせるように口を開いた。
「僕は、志献官にはなれない」
「なんで......だって、簡易検査のときは」
「分からない。ただ、防衛本部で受けた適性検査で、志献官になる資格がないって、言われた」
「本当に?」
思わず聞き返した三宙に、朔は力なく頷いた。
そんなことがあるのだろうか。三宙が簡易検査のときに話した防衛本部の職員は、簡易検査でも間違うことは滅多にないと言っていた。しかも、朔は源家の血筋だ。簡易検査の結果が誤りだなんて不自然に思える。
だが──。
三宙は咄嗟に口元を覆った。ピクリと口角が上がったのを感じたのだ。幸い、目を伏せていた朔は気付かなかったようで、悄然としている。
「じゃあ......これからどうすんの?」
志献官になって兄と共に防衛本部で働くのは朔の最大の夢だ。その夢を取り上げられたら、朔はどうするのだろう。やはり源の人間として政治の道へ進むのだろうか。
朔は一瞬途方に暮れたような顔をしたが、迷いを振り払うように首を振って前を向いた。
「考えたことがないわけじゃないんだ。父上も因子を持たない人だったし、もしも僕もそうだったらって。そのときは、志献官にはなれなくても、職員として兄さんを支えていこうって、思ってた......けど、現実になると、やっぱりきついな」
「......何でわざわざオレに言うんだよ」
朔は答えを探すように視線を泳がせて俯いた。
「なんとなく。三宙には言っておいた方がいい気がしたんだ。呼び出して悪かった。聞いてくれてありがとう。一番の夢は叶わないけど、僕のやりたいことを見つけてみる」
「おう......」
朔は言うだけ言うと、どこかスッキリとした顔で去って行く。三宙は真っ直ぐに背筋の伸びた後ろ姿を見送って立ち尽くした。
(オレ、サイテーだ)
朔が志献官になれないと聞いて、嬉しかった。これから三宙の両親が言っていたように源家の跡を継ぐことになって三宙と同じようにままならない感情を抱いたまま家に縛り付けられるのだろうと思った。
けれど、朔は夢に破れても、自分のやりたいことを見つけると言う。
「......何やってんだろ、オレ」
ぽつりと呟いて中空に視線を彷徨わせる。
毎日が退屈だった。それでも、口を開けば"浮石家の跡取り"が何たるかを言い聞かせる母といるのが窮屈で、それより学校の方が自由と思えるからここにいる。
何かやりたいことがあるわけじゃない。習い事も、勉強も、必要だからやっている。志献官になりたいと思ったのもその親への反抗心からで、源家のようにこの国を守りたいという気持ちはなかった。因子がないと分かったら、やっぱりそうだよなと簡単に諦めがつく程度のことだった。
三宙に"今"がないのは、やりたいことがないからだ。"自分"がないからだ。浮石家の跡取りという以外に何もない。その浮石家の跡取りという肩書きだって、両親が取り上げようと思えば簡単に消えてしまう程度のものでしかない。
もしも、取り上げられてしまったら?
『じゃあ......これからどうすんの?』
朔に投げかけた問いが跳ね返ってくる。考えても、考えても、浮かんでくる将来の形はない。
(あ──オレ、空っぽなんだ)
拳を握り締め、立ち尽くす三宙の耳に予鈴が届く。三宙はのろのろと教室に戻り、席に着いた。
机の上に乗ったままの雑誌をしまい、教科書を出す。何もかも頭に入っているから教科書は配布された四月と変わらない綺麗さで、ほとんど取らないノートは新品も同然だ。
新しい学びもなく、ぼんやり座っているだけの授業時間に、何の意味がある?
媚びて上っ面だけの付き合いを望む同級生たちに囲まれている自分に、何の価値がある?
急に何もかもが遠くなった。授業前のざわめきも、気だるげな午後の空気も。
世界がひっくり返ったように、何もかもが苦痛だった。
「っ!」
勢いよく立ち上がる。ぎょっとしたように近くの同級生が三宙に顔を向けた。ちょうど教師が入ってくるのを横目に見ながら、三宙は教室の後ろから出ていく。
「浮石君? どこに行くんだ」
三宙は教師を無視して廊下を走った。階段を駆け下りて、靴も履き替えず校舎を飛び出す。
これから来る冬を予感させるひやりとした風が頬を刺した。三宙はただがむしゃらに、学校を飛び出した。
「はあ......はあ、はあ......」
心臓が壊れそうなほど強く胸の中で暴れている。両膝に手をついていた三宙は、汗をぐいっと拭って背中を伸ばした。
「はっ。マジか......」
煉瓦街だ。学校のある地区からここまではかなり距離がある。ここまで止まらず走ってきたことも驚きだし、迷わず来られたのも奇跡だ。
三宙は渇いた喉に唾を飲み込みながら、ふらふらと通りを進んでいく。足は疲れでガクガクと震えていた。
「っ、ハハ......」
思わず笑みがこぼれる。何が解決したわけでもないが、爽快な気分だった。こんなに思い切り走るなど、体育の授業以外ではあり得ない。
三宙は暑さと息苦しさに制服の襟元をくつろげながら、ふと、横を見た。街角に並ぶ店の飾り窓には、姿勢も悪く、汗まみれで髪もぶわぶわと広がって、くたびれた自分が映っている。足下など上履きのままだ。顔に浮かんでいる笑みは、疲労で力なく口元が緩んでいるように締まりがない。
「──カッコ悪ぃ」
どう見ても、浮石家の跡取りとは思えない。
けれど、悪くない気がした。かっちりと息苦しく着込むよりも着崩していた方がしっくりくる。
三宙は、深く息をした。まだ呼吸は荒く、息苦しいことには変わりないのに、ようやくちゃんと自分で息をした気分だった。自然と視線が上がる。秋の空は高く朗らかだ。夏よりも低い日差しは暖かい色をして、煉瓦街をきらびやかに照らしている。
(ああ、いいな)
今、この瞬間、三宙はただの三宙だった。誰の監視もなく、誰の関心もなく、学校を脱走したただの子供として、街を目的もなくぶらついている。
煉瓦街には三宙も両親に連れられてよく来た。浮石家の経営する百貨店があるからだ。いつもは車で百貨店に向かうか、目当ての店の前に車をつけるかのどちらかで、ゆっくりと歩いて散策するなど想像したこともない。
だって、それが浮石家だったから。
疲れた足を労りながらゆっくりと歩いていれば、車に乗っていては目に付かなかった物が見えてくる。
種々の食料品店はもちろんのこと、お洒落なカフェや、パーラーやレストランなどの飲食店。小洒落た装身具などを売っている宝飾店、紳士服専門のテーラーや、婦人服専門のブティックなどの衣料品店に、生活雑貨を売る店や、本屋や、文具店、旧世界から運び出した骨董品を売っている店。看板を見た限りでは何屋かまるで分からない、ちょっと覗いてみたくなるような店まで、挙げていればキリがない。いちいち足を止めていたなら、一日あっても足りないほどのあらゆる店が、街中にある。
目にする物全てが新鮮だった。百貨店から遠ざかれば遠ざかるほど、個性的な店が増えていく。路上に商品を広げたアクセサリーの露天商は、無一文の三宙でも気兼ねなく覗くことができた。
「ふは! キミ、もしかして脱走してきたの?」
片膝を抱えるようにして座っていた、男か女かよく分からない赤い髪の若者が三宙に話しかけてきた。声も低すぎず、高すぎずで、話し方も軽い。今までに会ったことがない類いの人間だった。
「だって、ホラ。上履きだもんね。それにその制服、坊ちゃん学校じゃん? ワーッてなっちゃった感じ?」
「えっと......その......」
上手く返せずにいると、若者はいいよいいよ、とひらひらと手を振った。その全ての指に指輪がはまって、細い腕輪がシャラシャラと音を立てる。羽織った派手な柄物の着物の袂が、ゆらゆらと揺れた。
「脱走記念に、何でも好きなの持ってっていいよ」
「え......でも......」
「気に入らないなら仕方ないけどねー。好きじゃない人にもらわれたって不幸だからさ。こーゆーの、嫌い?」
「嫌いじゃない!」
とっさに言葉が飛び出た。ハッとして口を押さえる三宙に、若者はにぃっと笑う。
「うちのアクセはぜーんぶ一点物だよ。ちゃんとしたお店で売ってんのに比べたら、全然安モンではあるけどさー」
「......あなたが作ったんですか?」
質問すれば、若者の顔がパッと輝く。
「そそ! こーゆーの好きだから趣味で作ってたら、作る方が俄然楽しくなっちゃって。気づいたらめちゃたくさん出来ちゃってたんだよ。せっかくだから、見てもらうついでに売ってんの。欲しいなら二個でも三個でも持っていきな?」
「そういうわけには......お金もないし」
「変に遠慮するねぇ! あげるって言ってんだから、ありがとって笑ってもらっときゃいーの! それが子供の特権ってヤツよ」
ぽいっと何かが飛んでくる。キラリと輝いたそれをとっさに受け取って、三宙は目を丸くした。
「もうそれキミのだから。返品不可でーす」
三宙はそっと手を開いた。ころりと小さな金色が転がる。
「それ、イヤーカフね。耳に穴開けなくても付けれるから、親にも怒られないよ。ちょっと気分上げたいときとか付けてみな。てか、付けたげる」
おいでおいでと手招きされて、三宙は戸惑いつつも若者のそばに膝をついた。カラフルな爪で三宙に渡したのとは別のイヤーカフを抓んだ若者は、さっと三宙の耳殻(じかく)にそれを付けて鏡を見せてくる。どさくさ紛れにふたつ目をもらってしまった。
「ね? いいでしょ」
「......うん」
耳元で小さなひとつがチカチカと輝く。それだけで、何かが変わった気がした。
「本当に、もらっていいんですか?」
「いいからいいから。それよりホラ! 何か言うことあるんじゃない?」
両手の平を上に向けて指先を招くように動かしながら、若者は三宙に耳を突き出してくる。三宙はぷっと吹き出して、イヤーカフをぎゅっと握りしめた。
「ありがとうございます」
「はーい。いいスマイルもらいました! 毎度アリー!」
大きく手を振る露天商と別れると、三宙は歩きながら耳に触れた。小さいけれどその存在感がとても気になる。ドキドキするような、そわそわするような。何だかむずがゆくてくすぐったい感情が胸の中いっぱいに広がっていた。
「そこの坊や。ちょっといいかな?」
呼びかけられて振り返る。二人組の警官だ。制帽のつばに軽く手を当てた警官たちは、三宙を見て頷いた。
「浮石三宙君だね?」
三宙はとっさに耳に触れていた手でイヤーカフを外した。
「はい」
三宙が頷けば、警官は安堵したように表情を綻ばせた。
(──ここで終わりか)
けれど、思ったよりも落胆はしなかった。耳に残った引っ掻くような痛みと、掌の中にある小さな小さな──そう、小さな自由があったから。
家に帰り、母に叱られている間も三宙はそれを握りしめていた。
しおらしく反省するふりをして部屋に戻る。怒られている最中に唇を引き結んでいたのは、口角が上がらないようにするためだ。
いそいそと姿見の前に立ち、体温と同じ温度になったそれを少し戸惑いながらも耳に付けてみた。
「──」
鏡に映った自分を見て頬の力を抜けば、にまにまと口角が上がる。
何だろう。ただ小さな装飾品を付けただけで、こんなにも嬉しい気持ちになるなんて。
ああ、見つけた。
「これが、オレのやりたいこと......かも」
自分らしく生きること。それが、三宙のやりたいことだ。
現状、三宙が家を継ぐことは避けられない。ずっと家を継ぐために生きてきたのだ。その考えは三宙の中心に根強くある。けれど、だからといって三宙が自分らしさを捨てる必要はないはずだ。家を継ぐことと、自分らしくあることは両立できるはず。
三宙は鏡の中の自分と真っ直ぐに向き合った。
母は三宙に二度とこんなことはしないようにと約束させたが、一度知った自由の味を忘れることは難しそうだ。
「次は──」
三宙はイヤーカフに触れた。
もしも次にやるならば、今度はもっと上手くやろう。
そんなことを、思いながら。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら