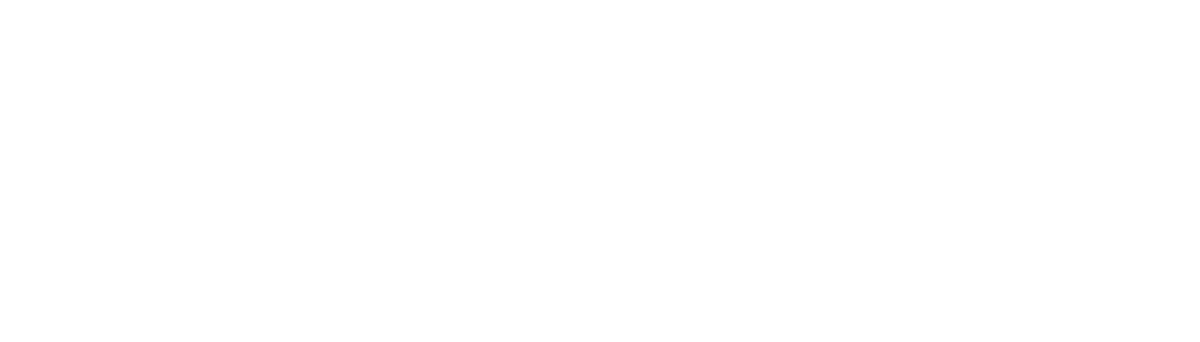INFO
24.07.14
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-七- 浮石三宙の空言(5)
著者:麻日珱
前回「断章-七- 浮石三宙の空言(4)」はこちら
新和十七年──。
最終学年に上がった頃には、三宙の学校での印象は"不良"になっていた。一度学校を脱走してからというもの、気分が乗らなければ授業には参加せず、遅刻も早退も平気で繰り返したからだ。
母は苦々しい顔をして、ならば学校を辞めなさいと口にしたが、三宙がそれでもいいと言うと黙り込んだ。素行不良で自主退学した経歴など、浮石家の跡継ぎには相応しくないとでも思ったのだろう。学校の授業をサボっていても好成績を出してみせれば、もはや干渉もしてこなくなった。両親の意志に従って品行方正にしていたのが馬鹿らしいほどだ。だからこそ、授業がどれだけ退屈でも通っていたと言ってもいい。
その年、小学校の六年間で初めて朔と同じ学級になった。朔は三宙の素行に眉をひそめ、三宙はそれまで通り極力関わらないように距離を取る。
周りからは、仲が悪いと思われていたようだが、もはやそれ以下だ。
一学期はひと言も口を利かないまま夏休みになった。
夏休みに入れば、三宙は両親に有無を言わさず横浜の実家へと連れて行かれた。習い事や家庭教師との勉強を詰められる。反発心はもちろんあったが、ここは突っぱねない方がいいという勘はよく働いた。
それでも、もう唯々諾々と従うつもりはない。交渉の結果、三宙の自由にできる時間を勝ち取り、これまでのどの夏休みよりも有意義な夏を過ごしていた。
「死んだ? 碧壱サンが?」
不協和音が長く響く。流れるようだった美しい旋律の余韻はどこにもない。
思いも寄らない報せを聞くと、人はただぽかんとするらしい。不協和音が空気に溶けていくように、数秒掛けて母の言葉が脳に浸透していく。まるで自分が馬鹿になったような気分だった。
「死んだ?」
もう一度聞き返したときには、心臓がバクバクと脈打っていた。どっと汗が吹き出る。
今日は勉強や習い事など一切ない休息日だ。一日何をしてもいい日だったが、外があまりにも暑いため外出する気にならず、かといって自室に閉じこもっていても息が詰まる。気晴らしにとリビングでピアノを弾いていたところで、母はどうでもいい世間話のように三宙に碧壱の訃報を告げた。
呆然とする三宙をよそに、母はソファーに座って使用人に紅茶を持ってくるよう言いつけている。訃報を伝えたとは思えない落ち着き払った態度だった。
三宙は急くように向かいに座り、母に話の続きを促した。
「お母様、碧壱サンはいつ......」
「詳しくは分かりませんが、旧新宿を奪還しようとした作戦がこの前あったでしょう。そのときという話です」
「新宿......」
その記事なら読んだ。万全の体制で向かったが多大な被害を出して撤退した防衛本部に対する批判的な記事だ。元々新宿はデッドマターの侵食領域内にある。人的被害の全ては防衛本部の志献官たちだ。その中に、碧壱もいたのだろうか。
(でも......純壱位だろ?)
三宙と朔がそれぞれ違う理由で志献官になれないと嘆いている間に、碧壱はトントン拍子に昇位していった。純壱位といえば、志献官の中でも最高位に当たる。簡単になれるものではないということは、外部にいる三宙にも察せられた。
その碧壱が、死んだ?
三宙は小さく身震いした。自分でもこれだけ衝撃的なのだ。幼い頃から憧れて、目標にしていた兄を失った朔は、どれだけ──。
「言ったでしょう? 志献官になどなるものではないのですよ」
三宙はハッと息を呑んで顔を上げた。母は真っ直ぐに三宙を見据えている。まるで唾棄(だき)するように言葉を続けた。
「源家は何人も犠牲になっているというのに学ばないのですから。愚かとしか言い様がありません」
「それが、結倭ノ国を守って命を落とした人の家族に言う言葉ですか......?」
三宙は目を瞠った。これほどまでに愕然とするのは久々だった。息子の衝撃を受けた姿を目にしているはずなのに、母は素知らぬ顔をして続ける。
「三宙さん。命を賭けることは決して高潔な行いではありません。生きてこそ価値は生まれるのです。どんなに高い志を持っていたとしても、死ねばそこで終わり。それ以上、何の利益も生みません」
「そんなこと......」
使用人が静かに母と三宙のふたり分の紅茶を入れていく。花柄が描かれた白磁のティーセットは旧世界の遺産だ。母はその香りをじっくりと堪能し、唇を湿らすように口にする。母が微かに眉根を寄せた。何か不満があったのだろう。控える使用人を静かに睨めつけた。
「淹れ直していらっしゃい」
「申し訳ございません。今すぐお持ちいたします」
使用人が慌てて出て行く。
あまりにも焦れったい。三宙は苛々と膝を揺すった。落ち着いてお茶を飲んでいる気持ちの余裕などない。
ポーン──遠い日にたどたどしく鳴ったピアノの音が脳裏に響いた。嬉しそうに兄を自慢して、自分も志献官になるのだと夢を語った、幼馴染みの顔が浮かんでは消えていた。
「──話がないなら失礼します」
三宙が立ち上がると、母は紅茶を淹れ直してきた使用人への小言を諦め、ティーカップをそっと置いた。
「どこへ行くのですか」
「燈京に戻ります」
「なぜ」
「なぜって......」
三宙は言葉に詰まった。数年前、自分勝手な感情で朔を遠ざけたのは三宙の方だ。もう友人とも呼べないのに、今の三宙には駆けつける理由がない。
立ち尽くす三宙に母が冷たい声を掛ける。
「志献官に未練があるのですか」
「......」
的外れな問いだったが、黙り込んだ三宙の答えを是と取ったのだろう。母は、少し苛立った様子で溜め息をついた。
「まだ分からないのですか。源の長男は防衛本部に使い捨てられたのですよ。燈京を守って死んだならばともかく、すでに侵食された地を奪還しようとして返り討ちに遭ったのです。それでも取り戻せていたならばまだ意味があったものを......犬死にというほかないでしょう?」
「お母様! それはあんまりです!」
「事実ではありませんか」
声を荒らげる三宙にも母は動じない。それどころか、眼差しは冷えていくばかりだ。
「源の奥様も長男を失って気を病んでしまったとか。本当に愚かだこと。こうなることは分かっていたでしょうに。最初から志献官にするべきではなかったのです」
「......」
三宙は唖然と母を見つめた。いったい何度失望すればいいのだろう。
昔から、母は源家を──志献官を蔑んでいた。源家との付き合いは尊敬や親しみを持ってのことではない。ただ、それが浮石家の利益になると考えたからだ。それでも、たとえ口では何と言おうと、人として最低限、悲しみに寄り添って悼む気持ちがあると思っていた。
だが、母にはそれすらもない。志献官を輩出する源家というものに利を見出しておきながら、その志を悪し様に言う姿に吐き気がする。
「......行かないと」
三宙は踵を返した。
源家は今悲しみの最中にあるだろう。その中で、母親が気を病んでしまったならば、父親もそちらに気を取られているはずだ。真面目な朔のことだから、自分がしっかりしなければと考えているに決まってる。そうして意地を張って、誰にも頼れず寄る辺なく呆然としている姿がありありと浮かんだ。
朔がどれだけ兄のことを慕っていたか、三宙は誰よりも知っている。
「──誰か。三宙さんを部屋に連れて行きなさい」
どこからともなく現れた使用人たちが、部屋を出ようとした三宙を阻む。
「っ、どけ!」
「決して出さないように。いいですね」
強行突破しようとすれば、簡単に肩に担ぎ上げられる。どんな抵抗も無駄だというように部屋の中に押し込められて、三宙は扉を叩いた。
「出してください! お母様! っ、出せよ! こんなのおかしいだろ!」
叫び声が虚しく響く。三宙は舌打ちをして窓を振り返った。扉から出られないなら窓から出ればいい。二階で多少高さはあるが、どうにか抜け出せない程でもないだろう。
「──っ」
階下を覗き、一瞬恐怖に身がすくむ。しかしそれ以上に、下に立つ使用人の姿に背筋が震えた。
「本気で、閉じ込めるつもりなのかよ......」
ずるずると座り込む。たとえ庭に人がいなくても門で捕まるだろうし、そこを突破できたとしても燈京に行くには船か汽車に乗らなければならない。徒歩を選んだとして、子供の足でどこまで逃げられるというのだろう。
自分はあまりにも無力だった。三宙から自由を奪おうと思えばいつだってできるのだと思い知らされるようだった。
夏休みが明け、朔は静かな表情で同級生たちのお悔やみの言葉を受けていた。そのときの何かを諦めてしまったような落ち着いた姿は、少なからず三宙に衝撃を与えた。
もう、何もかもが手遅れのような気がした。今の朔に掛ける言葉の一つも、三宙は持ち合わせていなかった。
結局、朔と面と向かって話ができたのは十二月になってからだった。
朔がデッドマターに襲われたと聞いて、気が急いた。もしも助かっていなければ、いつが最後の会話だったのかも分からないまま、二度と会えなくなるところだった。
その会話さえ、喧嘩別れに終わってしまったけれど。
(志献官に、なるなんて......今更、そんなの......ズルいだろ)
三宙は固く拳を握り締めながら、とぼとぼと夕暮れの学校の廊下を歩く。
朔はデッドマターから志献官に救われた際、志献官になる力があるのだと言われたのだそうだ。
そんな言葉を真に受けるなんて、朔は本当に馬鹿だ。
「なれっこねーよ......」
朔にもぶつけた言葉を呟く。震える声は、祈るような響きで誰もいない廊下に静かに消えていく。
『うるさい! お前には関係ないだろ!』
朔の反駁(はんばく)が深く胸を刺した。思い出して、なお傷む。
関係ない──関係ないなら、どうしてこんなに惨めな気持ちになる? 置いていかれるような気分になるんだ。
三宙は自分の右手を見下ろした。咄嗟に引き止めたくて伸ばした手が掴んだのは、腕でも肩でもなく朔の髪だった。
だからだろうか。翌日、校門で長い髪をバッサリと切り、晴れやかな顔で現れた朔を見たとき、まるで自分が切り捨てられたような気分になったのは。
「これが俺の覚悟だ」
朔は真っ直ぐに三宙を見据えて宣言すると、あとは振り返りもせずに去って行く。
残された三宙の手の中に掴んだ髪の感触が甦る。あるはずもない幻影を握り潰すように、三宙は強く拳を握り締めた。
その数日後には、朔は本当に防衛本部に行って志献官になる未来を勝ち取ってきた。違和感を覚えるほど溌剌としている。朔の明るい表情に気づいた取り巻きたちに話しかけられれば、卒業後は志献官の道に進むのだと語ってみせた。
(......本当に分かってんのかよ)
その憧れの志献官の道で兄が命を落とし、自分自身デッドマターの侵食に呑まれそうになったというのに。夢が叶うということに浮かれて、ことの重大さを飲み込んでいるようには思えない。
「バカじゃね」
「何だと? 三宙」
挑発すれば案の定、朔は三宙の誘いに乗ってきた。放課後、浮石家から来た迎えの車に乗って目的地へ向かう。
以前、三宙が志献官を諦めるようにと突きつけられた侵食の被害に遭った地域だ。
地面や家屋は丸く歪に削られた侵食跡地には、生活の痕跡が生々しく残る。父に連れられてきたあとで調べたところ、ここは燈京ができて以降、最大の被害を受けた場所らしい。
朔は小さな草履を拾い上げて言葉もないようだ。志献官になるということは、常にこの現実と向き合うということだ。これで現実が分かっただろう。
三宙が思い知ったように──。
「──感謝するぞ、三宙」
「は?」
「今、俺の決心は確かになった!」
幻聴か? と振り返った三宙に、朔がずいっと近づいた。
「これ以上こんな被害を出さないためにも、俺は志献官になる!」
(マジか......)
何を言っても無駄だ。幼い日と変わらない真っ直ぐな眼差しを見せられては、もう言える言葉はなかった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら