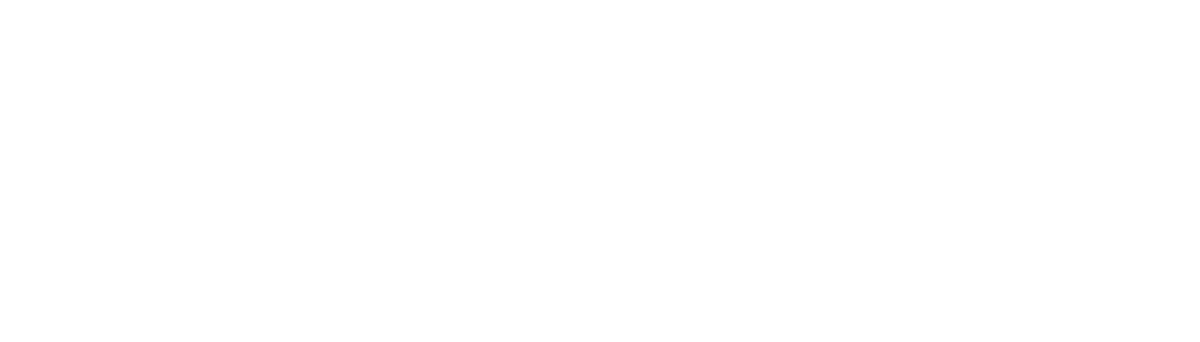INFO
24.07.21
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-七- 浮石三宙の空言(7)
著者:麻日珱
前回「断章-七- 浮石三宙の空言(6)」はこちら
新和二十年──。
横浜にたどり着くこともできず寄港した船から、三宙と朔、栄都の三人は無言で降り立った。固い地面に足が触れても、波に揺られていた名残がつきまとう。ふらつくような違和感を堪えながら、三宙は視線を巡らせた。
防衛本部の船と同じ頃に入港した船からは、横浜から逃げてきた人々が複雑そうな顔で下りてくるのが見える。
だが、それだけだ。船の数に対して、港にいる避難してきた人々の数が少なく思えた。
(もうどっか行ったのか?)
避難してきた人々を降ろしている船以外の船は、ほとんどが浮石家所有の船だった。その事実を怪訝に思いながらも、三宙は小さく息を吐く。
(──あとで、確認しねえと)
横浜の侵食を目撃したときにはあんなにも荒れていた感情が、凪いだように静かだ。
今日両親がどこにいたかは定かではない。最近は横浜と燈京を行き来しているとは聞いている。しかし、仮にいたとしても浮石の船があれだけ出ているのだ。きっと逃げ出したに違いない。
少しでも多くの人と逃げ延びていてくれればいいのだが......。
余裕ができたら一応確認をしておこう。
そう思った数時間後には、三宙は燈京の屋敷へと走っていた。
(どういうことだよ......)
港湾を管理している防衛本部の職員の話では、浮石家の船に乗っていたのは全て浮石関連の人間だったそうだ。対応した浮石家側の人間は避難の状況を確認しようとした職員にそう告げて引き上げていったらしい。どうりで、浮石の船の周りに避難してきた人々がいなかったはずだ。
(これじゃあまるで、浮石家が横浜を見捨てたみたいじゃねーか)
三宙は、普段実家を避けていることも忘れて屋敷へと乗り込む。洋風建築の広間には、横浜の本家にいた祖父がどしりと構え、行事でしか顔を合わせたこともないような親戚、会社の重役たちなどが、落ち着かない様子でうろついていた。
父はいない。代わりに使用人たちに指示を出していたのが母だ。三宙は息も整わないまま母に詰め寄った。
「お母様!」
「三宙さん! ああ、良かった......戻ってきてくれたのね。安心なさい。お父様も無事──」
「横浜にいる人たちを......見捨てたというのは本当ですか!?」
母は、奥様と声を掛けてきた使用人を軽く手で追いやると、三宙についてきなさいと言って歩き出す。連れてこられたのは三宙の使っていた部屋だった。埃臭さがないのは、定期的に掃除されているからだ。
母は三宙の勉強机に指先を置いて目を伏せた。
「今でも鮮明に思い出せます。あなたがこの家を出て行った日、どれほど辛く悲しかったか」
「......そんな話をしに来たんじゃありません。横浜には浮石の病院もあったはずです。多くの患者が入院していた......あなたたちは彼らを見捨て、自分たちの命惜しさに逃げたのですか!?」
「──母が無事だったと喜んではくれないのですね」
母は揚巻に結った束髪ほつれた髪をそっと指先ですくいながら、ゆっくりと振り返る。その冷淡な目に三宙は拳を握り締めた。すでに身長は母を追い抜いているのに、上から見下ろされているような気持ちになる。
「現実をご覧なさい。病院にどれほどの人間がいると思っているのです。誰を救うのですか? 誰ならば取り残して良いと?」
「それは......ですが、逃げ出す前にできることがあったでしょう! 最後まで諦めずにひとりでも多くの人を救うのが──」
母は三宙の言葉を遮るように強く息を吐き出した。
「はあ......以前も言わなかったかしら。英雄を志す者は、容易く死ぬと。あなたは母や浮石家の人間に死ねと言うのですか?」
「そんなことは言ってない!」
「同じことです」
ぴしゃりと断じられて言葉を呑む。母はただそこにいるだけなのに、威圧感に圧されて後退った。
「浮石の者が命を落とす必要はありません。私たちと下賎の者は命の価値が違うのですよ」
「命の価値に優劣などない。強きは弱きを助け、導くものじゃないのか......」
「では、本来弱きを助ける防衛本部(あなたたち)は何をしていたのです」
無意識に足を引く。すぐ後ろの扉にぶつかった。
「オレ、たちは......志献官は、可能な限り迅速に緊急出動をしました。けれど、それ以上にデッドマターの侵食が速くて」
「みっともない言い訳はお止めなさい」
「っ!」
母はフンと鼻を鳴らした。ゆっくりと部屋を見回しながら、着物の袷をそっと手で押さえる。よく見れば、いつも隙のない母の姿がくたびれて見えた。横浜から逃げてきたのなら当然だった。
「浮石家は防衛本部を訴えるつもりです」
「何だって......?」
「当然でしょう。デッドマターから結倭ノ国を守るという職分も果たせず、みすみす土地を奪われたのですから」
「やめてくださいそんなこと!」
憤りでどうにかなってしまいそうだった。母は埃除けの白い布が掛けられているベッドに浅く腰掛けると、ふっと小さく笑った。
「デッドマターが横浜を襲う数時間前、横浜の屋敷に横浜防衛支部から連絡がありました。万が一に備え、浮石家に病院の患者や地域の民間人の避難誘導をする協力要請です。ですがお断りしました」
「......は?」
何を言い出すのかと三宙は耳を疑った。
「デッドマターの侵食があることを告げれば混乱は必至。以前も肩透かしを食らいましたからね。本当に危険なのかも分からない。病状の異なる病人たちを逃がすのは困難です。誰を逃がしたところで遺恨は生まれる」
「だから、浮石家の人間だけで逃げたのですか? 知っていたのに見殺しにした......!」
「浮石は防衛本部の手先ではありませんもの。そんな要請に従う理由がありますか?」
「アンタ、人の命を何だと思ってんだ!」
大股で詰め寄るが、母の表情は静かなままだ。
「母の言葉を忘れたようですね。言ったでしょう。結倭ノ国の経済を支えているのは我ら浮石なのです。下賎の者はすべて路傍(ろぼう)の石と思いなさい──と。路傍の石がどれほど砕けようと、浮石家が残れば良いのです」
「......イカレてる」
「あなたのせいでもあるのですよ。三宙さん」
「......オレの?」
「あなたが志献官になどならなければ、協力もやぶさかではなかったのに」
「どういうことですか」
「浮石家が志献官の義務を免除されることは防衛本部と浮石家との取り決めです。それを破ったのは防衛本部でしょう? なぜ約束を破られたこちらが防衛本部に従わなければならないのです」
「オレのせいにすんなよ! 協力してたら、被害を最小限に抑えられたかもしれないだろ!」
みんな死んだ。医者も、患者も、街の人々も、横浜防衛支部で世話になった人たちもみんな死んでしまった。失った命はもう戻らない。
「駆けつけることさえできなかった志献官に、私たちを責める権利があるのですか?」
「っ!」
母は大儀そうにゆっくりと立ち上がった。静々と近づく姿に純粋な恐怖が込み上げる。怯える三宙の目の前で、母は綻ぶように笑って見せた。
「三宙さんは浮石家ならばできると思ったから、何もしなかったと怒るのでしょう? 防衛本部は何もできなかったのに......。ならば、どちらにいるのがあなたの志を成せるか分かったのではありませんか?」
「違う。オレは......」
「あなたが戻って浮石を継ぐというなら、防衛本部の責任を問うのはやめます。簡単でしょう?」
伸びてきた手を振り払う。目の前にいるのは怪物だ。この浮石家という家は、醜悪で汚らわしい、人の形をした何かの住み処だ。
「いやだ。こんな家には戻らない。こんな家......滅びればいい!」
やっと自分の居場所だと思える場所にいるのだ。こんな家に戻って、染まって、怪物になんかなりたくない。
母は伸ばしていた手を引くと、三宙に背を向けた。
「......そうですか。もうお行きなさい。これ以上話すことはありません」
「......」
もう、一秒だっていられなかった。もつれそうになる足を必死に動かして屋敷を横切る。使用人たちの目が、家を継がない三宙を責め立てるようで恐ろしかった。
「はあ、はあ......」
家を出た夜。振り返った屋敷は黒く大きく恐ろしかった。けれど、太陽の下に佇む今は、それ以上におぞましく感じる。
足を止めれば捕まってしまいそうな気がして、三宙は一心不乱に防衛本部へと駆け戻った。
笹鬼司令が引責辞任を発表したのは、横浜壊滅から一ヶ月も経たない頃のことだった。防衛本部は横浜の壊滅を手をこまねいて見ていただけだ、横浜の住民を見殺しにしたのだと、世論が吹き上がったからだ。その矛先は、鎌倉防衛戦での不安と鬱憤も巻き込んで、笹鬼司令に突きつけられた。
防衛本部の者は皆、笹鬼の辞任を惜しんでいた。防衛本部に長くいる職員があんなに志献官を大事にする司令も珍しいと言うほど、笹鬼は志献官のことを考えてくれていた。
「──笹鬼司令」
笹鬼がひとりなのを見計らってやっと掛けた声は、自分でも情けないほどに震えていた。
「浮石家(うち)のせいっすか」
「浮石純弐位......」
「浮石家がなんかやったんすよね?」
笹鬼は泣きそうな子供を安心させるように、くしゃりと笑った。
「それは違う。誰かが責任を取らなければならない。それだけさ」
「でも!」
「私ひとりの首で民衆が納得するならば安いものだ。君たちとは背負っているものが違うだろう? 君たちは何にも代えがたいが、私など辞めたところでどこぞの窓際に追いやられるのが関の山だからな」
「司令......」
ぽん、と分厚い手が三宙の肩に乗る。
「不甲斐ない司令で申し訳なかった。結倭ノ国の国民として、君たちが志を果たすことを祈っている」
そうして去って行った笹鬼司令の訃報が届いたのは、引責辞任からわずか一週間後のことだ。
笹鬼は早朝、駅裏近くの水路に転落しているのが発見された。目立った外傷もなかったことと、飲酒の形跡があること、死亡したのが深夜だったことから、警察は酔っ払って足を踏み外し、過って転落した事故であると結論づけ、早々に捜査は打ち切りとなった。
笹鬼というひとりの人間の、あまりにもあっけない幕切れだった。
(もしも──)
笹鬼の葬儀の帰り道、ひとりとぼとぼと歩く三宙は思う。
もしも、自分が志献官の道を選ばなかったなら、たくさんの命が今も失われずに済んだのではないだろうか。
浮石家は横浜防衛支部に協力をして市民の避難を誘導し、笹鬼は辞めさせられることもなく、事故に遭うこともなく指揮を執っていたはずだ。
(オレのせいだ)
グラグラと目眩がする。横浜の侵食を目の当たりにしてからこちら、ずっと調子が悪い。たたみかけるように発覚した事実が消化できないまま今日まで来てしまった。ろくに食事も喉を通らない日々が続いていた。そこに笹鬼の訃報だ。心身ともに憔悴しきった三宙は、葬儀場から戻って防衛本部の寮の部屋に戻ると、深々と溜め息をついた。
制帽を脱いで、ネクタイを緩める。普段は滅多に着ない正装だ。以前これを着たのは、三宙と朔が防衛本部に来てからずっと世話になっていたモルのモルGが死んだときだった。たった一年前だ。あっという間にあのときの最悪な気持ちまでもが腹の底に甦ってくる。
「......っ」
寝台に座り込んで両手で顔を覆った。去年、横浜に行くかどうか決めかねていた三宙は、朔との喧嘩の果てに横浜に行くことを選んだ。逃げたのだ。あのまま一緒に居続ければ、いずれ酷いことを言ってしまいそうで──。
コンコン、と控えめに扉がノックされる。ぎくりとした。まるで一年前に引きずり戻されたような感覚に頭が混乱する。
「──三宙。いるんだろう? 少しいいか」
居留守を使うこともできたが、三宙は扉を開けた。いつの間にか広がった身長差で見下ろす形になる。
「何?」
「最近、様子がおかしいだろう。大丈夫か?」
「別にヘーキだよ」
ああ、サングラスをかければよかった。そう思ってももう遅い。三宙は朔から目を逸らし続けた。
「横浜のことは、お前が一番ショックだったと思う。ご家族は無事だったんだろう?」
「......まあな」
ホッと朔が息をつく。ずっと何か聞きたそうにしていたのはそれか。三宙は帽子を被っていたせいで変に癖のついた髪にくしゃりと指を通す。
「そうか。よかったな」
「......」
三宙は口を噤んだ。よかった──喜ぶべきなのだろう。本来は。
朔は三宙の複雑な心境も知らずに続ける。
「横浜のことは残念だが......いつかデッドマターから横浜を取り戻したら、お前が再興すればいい。浮石家を継ぐんだから」
「......は?」
朔が不器用に言葉を選んでいるのは顔を見れば分かる。だが、どうしても受け入れられなかった。
「継がねーよ。誰が継ぐかよ、あんな家!」
「三宙?」
声を荒らげた三宙に、朔が丸く目を見開く。
「昔、言ってたじゃないか」
途方に暮れた眼差しや口調、その表情全てが癇に障った。
「昔? いつのこと言ってんだよ。いつまでも馬鹿みたいにガキの頃の夢にしがみついてるわけねーだろ!」
「っ、何なんだ、急に」
朔はあからさまに不快をあらわにする。三宙は小さく舌打ちをして溜め息をついた。
「はあ......もういい。お前と話してるとバカになる」
「何だと? どういう意味だ」
閉めようとした扉を朔が掴んで止める。
「離せよ」
「断る。一年前もそうだった。そうやって勝手にひとりで腹を立てていたじゃないか。あのとき、もう知っていたんだろう。モルGが......」
「黙れ」
「やはりそうか。また何か隠しているんだろう。実家のことか? 横浜の侵食で何か──」
ブチッと、頭の中で何かが切れた音が聞こえた。
「っせぇな! モルGが死んだのがテメェのくだらねえ意地のせいだって聞けたら満足か!?」
「なっ......」
「何が一族の使命だ。鎌倉で! 昇位試験の時、お前がさっさと諦めて出てこねえから、モルGが侵食領域に入ったんだろうが! モルGが死んだのはお前のせいだ!」
ヒュッと朔が息を呑む。三宙はハーハーと肩で息をして、片手で目元を覆った。すぐに後悔が押し寄せてくる。
「くそっ。言わないってモルGと約束したのに......」
「あのとき言いかけていたのはそれか......」
朔の声は、それほどショックを受けているようには聞こえなかった。呆然としているのだろうか。ショックを受けた顔を見るのが怖い。しかし、朔は淡々と口を開き始めた。
「モルGが死んだのが、俺のせいなら......ならば余計に、俺が一族の使命を果たさないと」
「──は?」
三宙は顔を上げた。朔の真剣な眼差しは、三宙に向けられているのにどこか遠いところを見ているようだった。
「何言ってんだ、お前」
呆然と呟く。三宙が感じたのは恐怖だった。一族の使命に異常なまでに執着する姿は、母のそれにも重なった。
「使命だからって、なんでそこまで思えるんだ」
「お前だってそうだっただろう。家を継ぐことに誇りを持っていた。それを放棄するだなんてどうかしているぞ。まさか──浮石家を継ぐという使命から逃げるために志献官になったのか? そんないい加減な理由で?」
軽蔑を含んだ疑心の目が三宙を睨む。三宙はゆるゆると首を振った。
「どうかしてんのはお前だよ」
扉を押さえている朔の胸を強く突き飛ばす。蹈鞴を踏んで後ろに倒れそうになった朔を無視して、三宙は素早く扉を閉めた。
扉の向こうでしばらく朔がたたずむ気配がしたがやがて隣の自室へと帰って行った。
パタン、と朔の部屋の扉が乱暴に閉まる音が聞こえた瞬間、三宙は自室の扉に背中を預けてずるずると座り込んだ。
「くそ、何なんだよ......」
髪をぐしゃぐしゃにして頭を抱える。自分を守るようにぎゅっと身体を小さく丸め、三宙はじっと息を潜めた。
「絶対に......」
三宙は部屋の中を睨んだ。自分らしさで彩った部屋だ。三宙だけが自由にできる場所だった。
「絶対に、オレは囚われたりしない」
朔や母のように家などというものに囚われず、自由に生きてやる。
その対抗心と決意こそが、より一層三宙を浮石家へと雁字搦めに縛り付けることを、本人はまだ気付けないでいた。
(終わり)
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら