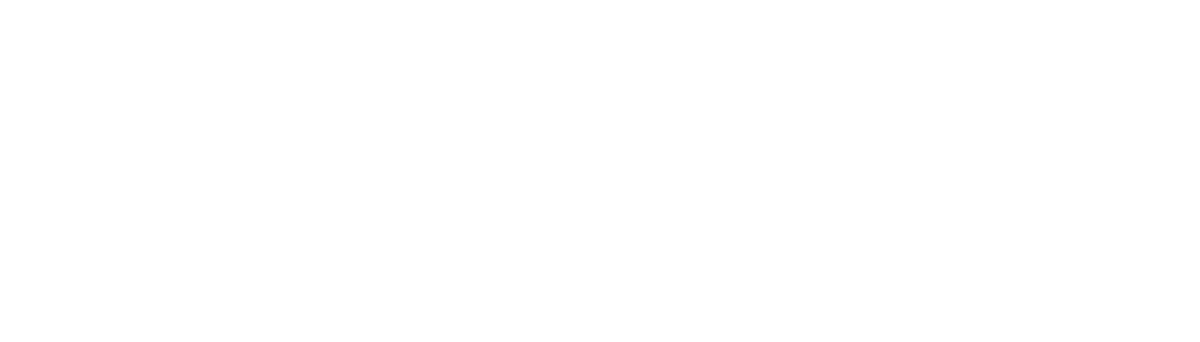INFO
24.07.31
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-八- 凍硝七瀬の氷消(2)
著者:麻日珱
前回「断章-八- 凍硝七瀬の氷消(1)」はこちら
しとしとと降る雨を七瀬はぼんやりと眺めていた。わずかに開けた窓から、ひゅぅ、と入り込んできた湿った冷たい風が頬を撫でる。コホコホと、隣の部屋から母の空咳が聞こえた。七瀬はそっと障子窓を閉める。蝋燭や油など贅沢ができない家だ。天気が悪ければ昼間といえども部屋の中は陰気に暗い。
梅雨に入ってから、母は再び体調を崩した。医者を呼んでなんとか熱も下がったが、もう何日も母は布団から起き上がれないでいる。
七瀬は母がいる奥の部屋へと続く襖をじっと見つめた。風邪が移るから近づいてはいけないとの言いつけを守って、しばらく顔も見ていない。
父はといえば、こんな雨の日にも街まで行っている。なかなかよくならない母のために、もう一度医者を呼びに行っているのだ。父ちゃんが不在の間は何かあったら隣に言いに行くんだよと、七瀬は何度も言い含められていた。
元来、七瀬は家の中でひとり遊びをしていても苦でないような大人しい子供だったが、それでも長く外に出られないのは退屈だ。
外に行くことも、母に甘えることもできない。手持ち無沙汰になった七瀬は、これまで集めてきた河原の石を、すっかり白茶けた畳の上に広げた。
「......キレーな石あげたら、かーちゃん、げんきになるかなぁ」
本当ならすぐにでも探しに行きたいが、雨が降っている間は川に近づいちゃいけないと厳しく言われている。七瀬はそれを固く守っていた。
コホコホ......コホコホ......。
時折聞こえる咳がどうしても気になる。七瀬は部屋を仕切る襖をそっと開けた。
四畳半の部屋の中には箪笥が一棹(ひとさお)ある以外はがらんとして、寒々しい。布団に横たわった母は、襖が開いた気配にこちらを向いた。
「かーちゃん」
母は七瀬のか細い呼び声に、重たそうに身体を起こす。つやを失った長い髪が、背中に流れるように落ちた。
「──七瀬、おいで」
座った母が七瀬を手招きする。おずおずと近づいていった七瀬は、母のすぐ側にぺたんと座った。
「かーちゃだいじょうぶ?」
母は七瀬の頭をそっと撫でた。
「大丈夫。お家にばっかりいるの、つまらないね。ごめんね」
ううん、と七瀬は首を振る。外に出られないのは母のせいではない。雨のせいだ。
「お日様が出てくる頃にはきっとよくなってるから、そうしたら、遊びに行こうね」
「うん。はやくおひさまでてこないかなぁ」
口を尖らせて母の手を両手で握りしめていれば、ガタン、と玄関の戸が開く音がした。古い家だ。立て付けが悪くなっていて、開けるのにはこつがいる。
「ただいまぁ」
「とーちゃん!」
狭い家だ。玄関は七瀬が元いた部屋からすぐの場所にある。ととと、と駆けつければ、土間に以前も来てくれた老医が立っていた。その後ろから雨水を払いながら父が入ってくる。
「とーちゃ、おかえり」
「ただいま、七瀬。お医者様にこんにちは、は?」
「こんにちは」
「はい、こんにちは」
医者は好々爺然と笑った。父はちゃんと挨拶のできた七瀬の頭をくしゃくしゃと撫でると、医者と共に居間へ上がり、奥の部屋へと向かっていった。
「未央。起きてて大丈夫か?」
布団が敷かれている部屋にふたりも大人が集まれば手狭になる。七瀬は邪魔にならないようにと部屋の外から中を覗いた。
「大丈夫。寝てるのも疲れちゃう」
言って、咳き込んだ母の背中を父がさする。お願いします、と医者を促して下がると、七瀬を連れて襖を閉じてしまった。
「とーちゃん、かーちゃ大丈夫?」
「お医者さんが来たからもう大丈夫だよ」
父の膝に乗せてもらいながら診察が終わるのを待っていれば、やがてすらりと襖が開いた。医者の表情が硬い。
「......母ちゃんのところに行っといで」
トンと背中を流され、七瀬は再び横になっている母の側に座る。背後で閉じられた襖の向こうからぼそぼそと声が聞こえるが、何を言っているかまでは聞き取れない。
「七瀬、おいで」
布団の中に招かれて七瀬は転がるように入り込む。久しぶりの母の温もりだ。ほっと安心した七瀬は、母の胸に抱かれてまどろんだ。
その部屋の外で父が絶望に立ち尽くしていることなど、七瀬は知るよしもなかった。
今日もまだ雨が降っている。
「......おひさま、まだいない」
七瀬はしょんぼりと口をとがらせる。
医者を呼んでから数日、幸いにも母はゆっくりと快方に向かっている。起きている時間も長くなって、咳もほとんど治まった。
七瀬が安堵したのも束の間、今度は父が長く家を空けるようになった。
雨が降っていては仕事にならないと畑仕事を辞め、毎日毎日、朝早くから夜まで街に出稼ぎに行っている。時には数日帰らないこともあった。
そんな父に頼まれて七瀬と母の様子を見に来てくれたのは近所の親切な人たちだ。小さい子がいるんだから、身体が弱いんだから、と何くれと世話を焼いてくれる。
どうして働き方を変えたのか、父と母が話しているのを七瀬は聞いたが、あまりよく分からなかった。
父が言うには、街にも村にも、医者にさえも、もう薬がないのだそうだ。
七瀬の住んでいる地方は首都のある燈京から遠く離れているが、時折物資が船に載せられて一括で海辺の港町へと運び込まれる。そこから物資が内陸の街や村へと分配される仕組みになっていた。その中に医薬品も含まれているのだが、昨今搬入数が激減し、分配されなくなったそうだ。
『どうして、そんなことに?』
尋ねた母に、父は憤りを吐き出すようにため息をついた。
『分からない。医者は、もう見捨てられたんだろうって言ってたけど......』
『そんな......』
母が溜め息を付く。父は、でも、と少し声を明るくして言った。
『君の病気は燈京の病院ならどうにかなるかもしれないと言ってたんだ。だから、どうかな?』
『燈京......』
母の呆然とした声に不安がかき立てられて七瀬がぐずったところで、両親の会話は終わった。
それからだ。父が働き詰めになったのは。
「......」
七瀬は卓袱台に頬をぺたんとつけて、蒐集(しゅうしゅう)した石をコロコロと転がした。河原で拾ったときにはあんなに綺麗だと思っていたのに、今では何でこれを選んだのかも分からない。キラキラしているわけでも、つるつるピカピカしているわけでもない、ただの河原の小石だ。
「七瀬、どうしたの?」
「石、きれーじゃない」
「ん?」
母が七瀬の手元をのぞき込む。
「綺麗じゃないの?」
「うん」
むくれる七瀬に母が小さく笑う。病み上がりの母は、一層細くなったように見えた。
「......おひさま、まだかなぁ」
雨が止んだら、もっともっと綺麗な石を見つけて、母にあげるのだ。
そうしたら喜んでくれる。きっと、病気もよくなるはずだ。
七瀬は卓袱台に転がした石を拾い集めて両手いっぱいに載せる。ぽろぽろこぼれ落ちるほどたくさんあったが、やはりどれも綺麗には見えなかった。
その日も、父の帰りは遅かった。
長雨が続き、家の中は梅雨冷えで肌寒い。眠っていた七瀬は、夜半になって小さく身震いをして目を覚ました。
「......かーちゃん?」
隣を見れば、一緒の布団に寝ていたはずの母の姿がなかった。ぼんやりと首を巡らせれば、細く開いた襖の向こうから漏れた明かりに気付く。
その細い隙間から、微かに父と母の声が聞こえた。寝ぼけ眼をこすりながら、明かりの方へと這っていく。父にお帰りを言おうとした七瀬だが、襖に伸ばした手をびくりと止めた。隣の部屋から聞こえるふたりの声の調子がいつもと違うことに気がついたからだ。
「最近、根を詰めすぎじゃない? こんなんじゃ、あなたも身体を壊しちゃう」
七瀬に話しかけるのとは違う、少し低い母の声に、父が軽く笑って答えた。
「なんてことないさ。丈夫なのは知ってるだろ?」
「でも......」
「燈京行きの船に乗せてもらうためだ。もっと稼がないと......。向こうでの生活もあるし、医者代だってかかる」
「......私のことはいいよ」
「よくないだろ! 治るかもしれないんだ!」
「シッ。七瀬が起きちゃう」
息を詰めるようにふたりは黙り込む。七瀬は起きているとも言えずにただそこで固まった。話の内容は理解しきれなくても、その空気が七瀬の身体を凍り付かせていた。
「......燈京の病院なら、君の病気を治せる。そうしたら家族三人で生きていける。だろう?」
「そうかもしれないけど......」
母が言いよどみ、再び静寂が落ちた。父も母が何か言うのを待っている。恐ろしいほどの沈黙を、母のため息が破った。
「......やめよう。こんな話、虚しいだけだよ」
「どうして」
「だって、病気が治ったってそのあとは? ここに戻るの? 燈京で暮らす? 家は? 働き口は? 私たち、何もないじゃない」
「っ」
「──燈京に行って私を治療するお金があるなら、あなたと七瀬だけでも逃げてよ」
母の声が潤む。ハッと父が息を呑んだ。ざわざわとした不安に七瀬は胸元を握り締める。
「そんなこと、言わないでくれ」
置いていけるわけないだろ、と父は絞り出すような声で言った。父と母が泣いている。七瀬はその場にうずくまり、ぎゅっと唇を噛み締めた。
「......うー」
うめき声がひとたび漏れたら、もうだめだった。涙も泣き声もこぼれ落ちて止まらない。わずかな沈黙ののち、慌てたように襖が開いた。
「七瀬」
頑なに丸めた小さな身体はいとも容易く抱き上げられて、父の腕に揺られる。七瀬はその胸元をぎゅっと握った。一日中働いてきた父は、汗と雨の匂いがした。
その日、母は朝からニコニコと上機嫌だった。いつもならば七瀬が目を覚ました頃にはもう仕事に出かけている父もいて、おはようと挨拶できたことが、七瀬は嬉しかった。
寝間着から真新しい藍色の着物に着替えさせてもらう。母が体調のいいときにコツコツと縫っていた着物だ。少し大きめに仕立てられている着物の着慣れない感覚に落ち着かない気持ちになる。七瀬はどうして着物をくれるんだろうと思いながら母を見上げた。
「今日は七瀬のお誕生日なんだよ」
「おたんじょーび?」
自分の誕生日が七月十四日なのはちゃんと覚えているが、普段日付の感覚がない七瀬は言われてもピンと来なかった。
「四歳のお誕生日、おめでとう」
父と母が嬉しそうに笑っている。七瀬も釣られて笑った。四歳になったという実感はない。三歳の昨日も、四歳の今日も、七瀬にとって変わりはなかったから。それでも、両親が喜んでいる姿を見ていると心がウキウキしてくる。
ここしばらく薄曇りが続いていたのが嘘のように、七瀬の誕生日はよく晴れていた。抜けるような青空が広がって、絶好のお出かけ日和だ。
母と父が握ったおにぎりを持って、三人で河原へ向かう。途中、街に連れて行ってあげたかったんだけど......と母が眉を下げた。川向こうの街は、成人男性の渉が歩いても一時間以上掛かる場所にある。強い日差しの下を長々と歩いて行くには、母だけでなく七瀬も体力が足りない。それに、街に行ったことがない七瀬にとっては無理に遠くへ出かけなくても、父と母がニコニコ笑って一緒にいてくれるほうがずっと嬉しかった。
通い慣れた河原だ。川の流れる音は涼やかで、川面を吹き抜けてきた風は強い日差しに焼かれる肌を優しく冷やしてくれた。
七瀬は早速、いつものように石探しを始める。川は長雨のせいで増水していたが今は落ち着き、転がっている河原の石の顔ぶれも変わっていた。
せっせと石探しをする七瀬を、小さな木陰で寄り添うように座って眺めながら、夫婦は切なく目を細めた。
「──大きくなったな。少し前まで、赤ん坊だと思ってたのに」
「それ、私も着物を縫ってるときも思った。冬用の着物も、お下がりをいただいたから仕立て直そうと思ってるの」
「あまり無理するなよ」
「無理じゃないよ。私がしてあげたいの。いつまでやってあげられるか分からないから......」
元々の病とは別に、風邪を引いたり体調を崩したりするたびに、未央は自分の命が削られていくのを感じていた。病は少しずつ、確実に、未央の身体を蝕んでいる。
「......本当に、燈京に行かなくていいのか?」
「また言ってる」
未央は笑うと、風で頬をくすぐる髪をそっと耳に掛けた。七瀬はあまり川面に近づかない場所でしゃがみ込み、石を拾っては眺めて捨てて、と繰り返している。病弱な未央とは反対に、滅多に熱を出したりしない強い子だ。医者や産婆からは子供はすぐに熱を出すものだと言われていたが、酷い熱を出すようなこともなく元気にすくすく育っている。
未央は眩しく目を細めて呟いた。
「──行きたいって言ったら、行けるの?」
「それは......なんとかする。船にさえ乗れれば、なんとかなるよ」
渉に燈京のことは分からないが、仕事を選ばなければ働き口はいくらでもあるはずだ。暮らす場所だって、きっとどうにかなる。諦めて死を待っていることなどないのだと、渉は未央を説得した。
「......」
未央は何か考えるように遠くを見つめている。何を考えているのかは、渉には分からない。どうか行きたいと言ってくれと切実に願いながら、渉はその横顔を見つめた。
「......もう少し、考えさせて」
長い沈黙のあとで口を開いた妻に渉はホッと息をつく。また七瀬とふたりだけで行ってと言われるのではないかと緊張していたのだ。
「きっと、燈京行きの船に乗れるようにするから」
「かーちゃん、とーちゃん」
渉が決意を新たにしていると、子供特有の高くて澄んだ声がふたりを呼んだ。石に足を取られながらも、危なげなく向かってくる我が子の姿に顔をほころばす。
「みてー、きれい」
七瀬の小さな掌に載るだけの大きさの石だ。七瀬のお眼鏡に適った石は、ころりと丸く赤みがかっている。
「ほんとだ。綺麗だね」
「もいっこある」
七瀬が反対の手を開くと、薄い水色の帯が入った石が載っていた。
「お。いい形」
薄い綺麗な楕円形の石だ。水切りをしたらよく跳ねそうな形をしている。
「あげる」
「いいの? ありがとう」
母には赤みがかった石を、父には楕円形の石を渡して七瀬は満足そうだ。
「よし。七瀬、父ちゃんについておいで」
「なにー?」
立ち上がった父に七瀬はちょこちょこと付いてくる。渉は川縁に立つと、七瀬にもらったのとは別の平たい石を拾い上げた。
「見てな?」
川面になるべく平行になるように小石を投げる。水面をリズムよく跳ねた石は、向こう岸に到達する前に勢いをなくして川へと落ちた。
「っ! とーちゃすごい! いっぱいぴょんぴょんした!」
それこそ七瀬自身が小石のように跳ねて喜ぶ。渉は得意になりながら、しゃがみ込んでちょうどいい小石を探す。
「水切りって言ってな? さっきの父ちゃんみたいにやってごらん」
七瀬の手にもちょうどいい石を渡してやれば、七瀬はその石を振りかぶって投げた。ぽちゃん、と水しぶきを上げて近い場所へと落ちる。
「とーちゃ、ぴょんぴょんしない」
「あはは! 上投げじゃダメだよ。横から投げなきゃ。もう一回見てな」
渉は先ほどと同じように石を投げる。二回目はもっとよく飛んだ。
「んー!」
七瀬も真似したつもりだろう。一応横投げではあったが、ただぽいと放るだけだ。当然、水しぶきを上げてボチャンと落ちる。
今度は父の補助を受けながら投げてみたが、なかなか思い通りには跳ねない。何度繰り返しても、ポチャン、ボチャンと大きな水音ばかりが立った。
「もうヤ!」
七瀬は丸い頬を膨らましてぷくりとむくれる。渉はその頬をつつきながら相好を崩した。
「もうちょっと大きくなってからかな」
「......ぼくもできる?」
「練習すればね。でも、川以外には石を投げちゃダメだぞ?」
「うん......」
しょんぼりしてしまった七瀬に渉はしまったと内心思う。喜ばせたかっただけだが、裏目に出てしまったようだ。
「お腹空いたろ。母ちゃんのところに戻っておにぎり食べよっか」
俯く七瀬の背中を押して振り返れば、妻が呆れたような顔をして顔をしかめた。片手を顔の前に立ててゴメンと謝る。せっかくの誕生日なのに落ち込ませて、という声が聞こえてきそうだ。
「かーちゃん......」
「上手だったよ、七瀬。大丈夫大丈夫、すぐ父ちゃんより上手くなるからね」
ぎゅうっと七瀬は母に抱きつく。きろりと妻に睨まれた父は、ただひたすら七瀬の機嫌を回復するために務めたのだった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら