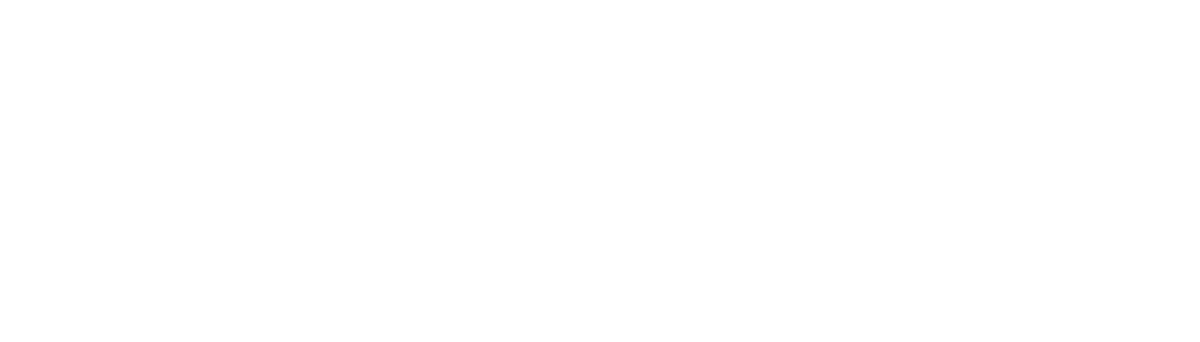INFO
24.08.04
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-八- 凍硝七瀬の氷消(3)
著者:麻日珱
前回「断章-八- 凍硝七瀬の氷消(2)」はこちら
未央の体調がまた悪くなったのは、それから幾日も経たない頃のことだった。
「......それじゃあ、七瀬と妻をお願いします」
今日も、父は近所の小母さんたちに声を掛けて仕事へ向かう。ふわふわと優しかった誕生日がまるで夢か幻のように遠くなっていくのを、七瀬は肌で感じていた。
母は寝付いて、父は家にいない。家の中に満ちた不安を消し去りたくて窓を開け放てば、ムッとするような蒸した夏の熱気が部屋の中に入ってくる。
昼間は暑く、夜も暑さの名残で眠れない。べたりと張り付くような夏の気配が不安と重なって、落ち着かない。安心出来るはずの我が家は、いつの間にか、そわそわと不安を生み続けるだけの場所になっていた。
弱っていく母とふたりでいるのは、大好きな母だからこそ怖かった。押しつぶされるような不安に耐えきれずに外に出れば、日差しの強さに少し怯む。
『七瀬に綺麗な石もらうと元気になっちゃう』
母の言葉を思い出し、七瀬は決意したようにぎゅっと両手を握り締めた。
陽炎が立つほどに外は暑い。立っているだけでじわりと汗を掻く。あちこちから聞こえてくるアブラゼミの鳴き声は、まるで音の雨のようだ。七瀬は空を見上げた。雲ひとつない青空が広がっている。太陽は燦々と輝いて、七瀬の影を濃く地面に落としていた。
(かーちゃん、げんきになるって言ってた)
七瀬は、面倒を見てくれている小母さんたちに見つからないように、河原へと向かった。母のために何かせずにはいられなかったのだ。
真夏の太陽の下、七瀬はせっせと石を探す。いつもならいいところで石が見つかるか、母が止めてくれるのだが、ひとりぼっちで河原にいる現在は、時間も忘れて没頭した。
きっと、綺麗な石を見つければ、母は元気になってくれる。
そう信じて。
「──ななちゃん!」
不意に、近所の小母さんの声が聞こえた。七瀬はぼんやりする頭を揺らして顔を上げ──世界が真っ暗になった。
はふはふと息をしながら七瀬は目を開けた。身体が熱い。誰かが額や首、腕などに当てる冷やした手拭いが、押し当てられた端からぬるくなる。少し塩味のする水を口に含まされて、七瀬は懸命にそれを飲み込んだ。
「七瀬、大丈夫?」
母が今にも倒れてしまいそうな青い顔で七瀬の髪を撫で付けた。七瀬はゆっくりと瞬きをして、かーちゃ、と微かに呼んだ。
どうやら、ここは家の中らしい。パタパタと風を送っているのは、隣の家の小母さんだ。意識が無くなる直前に七瀬を呼んだ声も、隣の小母さんのものだろう。
「お水飲める? ななちゃん」
小母さんの言葉にこくりと頷く七瀬を母が支えて起こす。身体を動かすのも億劫な七瀬の代わりに母が水を飲ませてくれた。
「もう一杯持ってくるね」
コップの水を飲み干すと、小母さんは安堵したように息をついて立ち上がる。パタパタと軽い足音を聞きながら、七瀬は母を見上げた。
「かーちゃ。これ」
固く握りしめていた手を開けば、意識が途切れる寸前に見つけた石が握られていた。ちゃんとそこにあったことに、よかった、と胸をなで下ろす。
先ほどから母は何か言いたげに口を動かしては、短く息を飲み込んでいた。言葉の代わりにこぼれてきたのは、ぽろぽろと流れる涙だ。
「っ、ごめんね、七瀬......ごめんなさい......」
どうして母が謝るのか分からない。なぜ泣いているのかも、分からない。
ただ、七瀬のせいで母が酷く悲しんでいることは分かる。
けれど、どうしたらいいか七瀬には分からなかった。
(泣かないで......)
言葉にしたいのに、喉からは微かな息が漏れるばかりだ。
ぎゅっと七瀬を抱き締める母の身体は、熱を持つ七瀬にはひやりとして心地がいい。その心地よさに揺られながら、七瀬は再び眠りへと落ちていった。
その夜、七瀬はふと目を覚ました。身体は重だるく、動かすことも億劫で、昼の名残のように身体が熱い。
「──行こう。燈京」
母の声が聞こえる。決意した声だ。七瀬のすぐ横で、母が父と話をしている。いつかのように隣の部屋ではないことに安堵した。
「今日、怖かった......この子が死ぬかもしれないって、実感したら......」
母の手が七瀬の頭に触れる。耳は聞こえているのに、目蓋は鉛のように重たく開かない。
「......分かった。絶対になんとかする。絶対、燈京に連れて行くから。それまで、頑張ってくれ」
祈るような父の言葉に母は声を涙で滲ませながら、何度も何度も頷いていた。
そうして、時は流れていった。
父は相変わらず忙しく、母の病状は一進一退を繰り返しながら、少しずつ悪化していく。
不安と寂しさを抱えながら七瀬にできたことといえば、母のために石を拾うことだけだった。夏の間はまた倒れてしまうのではないかと母も小母さんも警戒していたが、秋が深まり暑さも和らいでいくにつれて、警戒も少しずつ緩んでいった。
冬が来る前には、たくさんの綺麗な石が窓辺を飾った。それを見るたびに母が微笑んでくれたから、きっと石が母を元気にしてくれるのだと七瀬は信じた。
やがて雪がちらつくような寒い冬がやってくると、家の中には隙間風が吹き込んだ。毛布を重ねても凍えるように寒く、夜は母と身を寄せ合って眠る。時折、ふと目を覚ますと帰って来た父親に母親共々抱き込まれていることがあった。けれど、朝になると父はいなくなっているので、それが夢か現実なのかはいつまでも分からないままだ。
ただでさえ質素だった食事は、さらに貧しくなった。燈京に行くための資金を集めるためだと切り詰められていったからだ。母の容態はそのせいで急激に悪化していったが、燈京に行ければきっと大丈夫だという盲信と、早く燈京に行かなければという焦りが、父と母を過度な節約に走らせた。
日々の食事は近所から分けてもらったお米で作ったお粥がほとんどで、七瀬は毎日お腹を空かせていた。時折近所の人が分けてくれるおかずがあると、七瀬はごちそうが出てきたような心地で一心不乱に掻き込んだ。両親が忙しさや病のせいで正しく教えることのなかった箸はいつまでも握り箸のまま、持ち方を矯正されることもなかった。
年越しは静かに、けれど、正月にはささやかなお祝いをして過ごした。来年は燈京で年を越せたらいいねと語る痩せ細った母の頬には、淡い笑みが浮かんでいた。
「──燈京に行けるぞ!」
父がそう言って駆け込んできたのは最も寒さの厳しい頃のことだった。
父は痩せこけた頬に無精髭を生やし、目だけ爛々と輝かせている。いつもはふらつきながら仕事から帰ってくるのに、その顔は喜びと生気に満ちあふれていた。
「本当?」
病床からかすれた声で未央が問えば、渉は膝の上に七瀬を乗せ、妻の手をぎゅっと握りしめた。カサカサと乾いて少し熱のある妻の手に泣きそうになりながら、渉は笑顔を作った。
「前に言ったろ? 燈京にこっちの人を移住させてくれる船が出てるって。今日会ったお客さんで、その船に乗せてくれる人を紹介してくれるって話になったんだよ」
「その人に、会えたの?」
「ああ! うちの事情を話したら、特別に乗せてくれるって。移住計画も今回で一旦打ち切りらしい。これは、神様がぼくらにくれた贈り物なんだ!」
興奮して話す父に、母の痩(こ)けた顔がほろりと緩む。こぼれた涙を父が拭った。
「未央も、今は調子がいいって言ってただろ? もう大丈夫だ。燈京に行って、病気を治して、きっといい働き口が見つかる。運が向いてきたぞ」
なー? と父が求める同意に七瀬は大きく頷いた。こんなに嬉しそうな父を見るのは久しぶりで、七瀬は膝の上で小さく跳ねる。痩せて骨張った父の膝の上はあまり乗り心地がよくなかったが、気にしなかった。暗い空気ばかりが漂っていた家の中に訪れた明るい雰囲気がただ嬉しかったのだ。
「よーし。それじゃあ、準備をしよう。ああ、未央は何もしなくていいから。七瀬、お手伝いお願いします」
「はい!」
改まった物言いに元気に頷く我が子にひげ面で頬ずりをして嫌がられながらも、渉はキビキビと動き始めた。
「──そうは言っても、あんまり持って行く物はないか」
荷物をまとめようとしていた渉は一瞬寂しげに微笑んだ。家の中の物で売れる物はほとんど売った。家に残っている物は、薄っぺらい布団が二組と、最低限の着る物。欠けて罅の入っている茶碗などがせいぜいで、金目の物は何もない。今から身ひとつで置いて出て行ったところで惜しくもないものばかりだった。
「ねえ、これも、入れてくれる?」
未央が横たわったまま並べられた石を指さした。七瀬が、母が早くよくなりますようにと拾ってきた石だった。
「そうだね。これも入れよう。燈京じゃ新しい石は拾えないかもしれないしね」
「そーなの?」
燈京とはどんなところなのだろう。七瀬はちょっとだけ、行きたくなくなってしまった。父ちゃんも行ったことないから分からないけど、と父は石を荷物に入れる七瀬の頭をくしゃりと撫でる。
「ねえ......今のうちに、七瀬にこれを着せてあげて」
未央がだるい身体を必死に動かしてたぐり寄せたのは、夏から少しずつ縫ってきた七瀬の着物だった。
「内側に名札も縫い付けておいたからね。燈京で、迷子になったときはこれを見せるんだよ」
母の言葉に、父が裏を返して七瀬に名札を見せてくれる。七瀬には文字がまだ分からなかったが、名前と生年月日が書いてあるのだと父は教えてくれた。
「この着物、大きくなっても着られるように少し大きめに縫ったから、何年か着られるはずだよ」
母が言うとおり、着せてもらった着物は夏の着物同様七瀬には少し大きいようだった。渉は泣きそうな顔で微笑んでいた。未央はその着物に一針一針未来を託していたと知っていたからだ。
(けど、もう大丈夫だ)
渉は噛み締めながら、ほとんど荷造りとも呼べないに荷造りを終える。急な話だったが、今日がこの家で過ごす最後の日だ。小さくて古い家だったが、家族のいない渉と未央が初めて家族になった家だ。愛着がないわけがない。
一抹の寂しさを覚えつつも、振り切るように首を振る。
「今日はもう寝よう。明日朝早くから迎えが来てくれることになってるんだ」
明日は、橋の向こうまで車で迎えに来てくれる手はずになっている。歩いて移動しなくていい分、未央の負担にもならないはずだ。
父がフッと火を吹き消した。三人で身を寄せ合って布団に潜り込む。外はガタガタと家を揺らすほど風が強く、隙間風がヒュルヒュルと音を立てて家の中に入ってくる。それでも、七瀬はへっちゃらだった。両親に挟まれて感じるぬくもりは、何物にも代えがたい。
(──あったかい)
幸せな気持ちで眠るのはいつぶりだろう。七瀬は布団に潜り込んでクフクフと笑った。
まるで胸の中がくすぐられているように、心がふわふわと嬉しかった。父が明るく笑って、母もいつもより元気そうで、しばらく忘れていた家族団欒が戻ってきたようで嬉しい。
「楽しみだね、七瀬」
夜の闇に溶けていきそうなほどに静かな声で母がささやきかける。七瀬はうんうんと頷いてぎゅっと母にしがみついた。
とん、とん──一定の間隔で背中を叩かれるたびに、七瀬はうとうとと深い眠りへと誘われていく。
「七瀬──おやすみ」
自分を呼んだ母の声を最後に、七瀬は眠りへと落ちていった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら