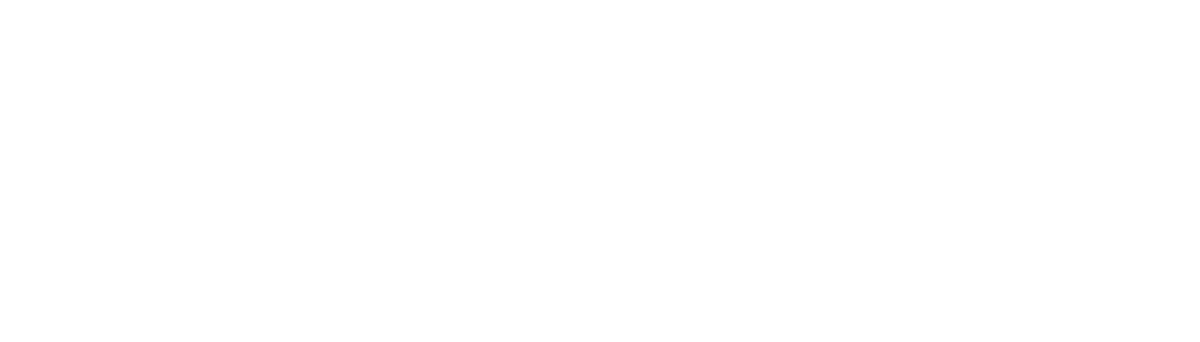INFO
24.08.14
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-八- 凍硝七瀬の氷消〈補遺〉
著者:麻日珱
新和二十二年──。
「何を考えているんですか!」
司令室で非難の声を上げた鐵仁武を煩わしげに見遣り、舎密防衛本部司令の塚早は顔をしかめた。
「今言ったとおり、養成所の凍硝七瀬を窒素の志献官として作戦部に加えることにした。あとのことはそちらでいいようにしてくれ」
「凍硝が今いくつだと? あんな年端もいかない子供に、デッドマターと戦うなんて危険なことをさせられるはずがありません」
「養成所からの報告では、それなりに優秀だそうだが? 年齢に目をつむれば、すぐにでも純位に上げられる水準にあるというではないか」
「ですが!」
「私は笹鬼とは違う。使えるものは何であろうと使う。それとも、何かね。司令の決定に従えないと?」
「限度があります」
仁武は低く唸った。一瞬、塚早は怯んだように頬を引きつらせたが、執務机の上で両手を組み合わせて仁武を見返した。
「ならば私を殺すかね? その怪物のような能力で」
仁武は身体の横できつく拳を握り締めた。ここで激高してしまえば、塚早はここぞとばかりに仁武を責め立てるだろう。ひいては、志献官全体を。それだけは避けなければならない。
「以前、鍛炭に賦活処置を行ってどうなったか、覚えておられないのですか」
「ふん。賦活処置で力が暴走するなど、前代未聞だと聞いている。鍛炭の心の弱さが招いたことではないのか」
塚早は、いや、と皮肉に口元を歪めた。
「鍛炭は自分の力を誇示しようとしたのではないか? 人ならざる力を手に入れて、万能にでもなったつもりだったんだろう。子供にはありがちなことだ。そのおかげで鍛炭は一足飛びに純位の志献官になれたのだから、むしろ喜んでいるはずだ」
「塚早司令!」
賦活処置で力を暴走させ、同僚の志献官を傷つけたことで六花がどれほど気に病んでいるか、塚早はまるで理解していない。興味もなかったのだろう。
「鐵純壱位。こちらにも我慢の限界というものがある。君たち志献官はいったいいつになったらデッドマターを消し去るんだ。どれほど民間人を犠牲にすれば気が済む? まさか、自らの活躍の場がなくなるからと、デッドマターを野放しにしているのではないだろうな?」
「ふざけたことを......これまで我々志献官がどれほど命をなげうってきたか!」
「デッドマターに対抗するために志献官は存在するのだ。命を捨てて戦うなど当然だろう」
「っ!」
食いしばった歯がぎりりと音を立てた。怒りを抑え込むために大きく息を吸う。
「そうだとしても、凍硝を純の志献官にすることは別の話です。せめて混の志献官から始めるのでは──」
「のんきに成長を待つ猶予があるのかね? 他に純位に足る力がある者がいるのか? ならばその者を純の志献官にすればいい。戦力はあればあるだけいいからな。だが、そういった報告は受けていないが?」
「それは......」
仁武は言葉に詰まった。
戦力はあればあるほどいい。その理屈は分かる。
去年、塚早の命令で臨時に行われた昇位試験では、混四位の数を増やすことには成功したが、純位になったのは暴走事故を起こした六花だけだ。現状、純の志献官になれる水準にある者はいない。
分かってはいるが、それでも仁武は首を振った。
「あんな幼い子供を戦力と数えるのは反対です」
塚早は深々と溜め息をついた。
「鐵純壱位。私は君の意見など聞いていない。既に凍硝七瀬に窒素の最終賦活処置を行うよう指示は出してある」
「......は?」
「君が何を喚(わめ)こうと。凍硝七瀬は純の志献官として作戦部の所属となる。これは決定事項だ」
「何を勝手なことを!」
ついに声を荒らげた仁武に塚早は不快そうに顔を歪めた。
「勝手? 司令はこの私だ。それとも何か? 笹鬼がいないからと、自分が司令にでもなったつもりかね?」
「そんなこと......っ」
仁武は小さく首を振った。ここで感情的になってはいけない。
「凍硝と共に戦うのは我々です。笹鬼司令ならば、まず、作戦部の皆に意見を聞いたと......」
「それこそ笹鬼が無能だという証ではないかね?」
「っ!」
「つまり、自分で判断を下せないから君たちの意見を頼ったということだろう? 自分が決めたことではないからと、責任を逃れたかったのではないかね?」
「違う。笹鬼司令は、我々志献官の命を軽んじなかった。だから、俺たちの声を聞いたんです」
「はっ。その結果がどうなった? 鎌倉では志献官を多く失い、横浜は目も当てられない惨状ではないか。笹鬼を美化するのも結構だが、現実を見たまえ」
「......」
黙り込んだ仁武に塚早は勝ち誇ったように鼻を鳴らした。
「化け物が人間らしく扱われた程度で容易(たやす)く懐きおって。貴様らもいずれ分かる。私の判断が正しいのだとな」
仁武はふつふつとわき上がる怒りを必死に抑え、唸るように口を開く。
「あなたは、笹鬼司令の足下にも及ばない」
「──何だと?」
「俺たちは命がけで結倭ノ国を守っています。怪物と罵られようと、化け物と恐れられようと。あなたは志献官の上に立って指揮する人間です。我々を恐れるよりも信じるべきだ。それなのに、どうして......っ、そんなに志献官を嫌悪しているのなら、なぜ司令になんてなったんだ!」
「誰が好き好んで司令になどなるものか!」
ドン、と拳を机に叩きつけて塚早は立ち上がる。
「今、この時代に防衛本部の司令になりたい者などいない! ここは墓場も同然だ。デッドマターを討ち滅ぼす目処も立たず、負け戦を繰り返し、責任ばかり押しつけられる。貧乏くじもいいところだ! 笹鬼を見ろ。無様に死んだぞ。あれこそ犬死にだ。それもこれもすべて、司令なんぞになったせいだ! 違うか? 貴様らがデッドマターと遊んでいるから、子供すら戦いに出さなければならなくなったんだ! それが私の責任か? 貴様ら志献官が役立たずだからこうなったのだろうが!」
「っ、ふざけるな!」
気がつけば、塚早の胸座を掴んでいた。執務机に乗り上げた塚早は苦しげに顔を歪めながら、ギラギラとした目で仁武を睨む。
「殴るのか? 作戦部の立場が危うくなっても知らんぞ」
「......俺たちがデッドマターとの戦いから手を引けば、困るのはそちらの方だ」
苦々しく吐き出せば、塚早は目を剥いて嘲笑した。
「ハッ、とうとう本性を現したな! 戦うことでしか役に立たない怪物風情が! デッドマターが滅べば貴様らに居場所はない。だからこそ、戦いを長引かせているんだろう!」
「仲間(とも)が死んだんだ! そんなはずないだろう!」
仁武は肩で息をすると、舌打ちをして塚早を突き放した。蹈鞴(たたら)を踏んだ塚早は、尻餅をつくように椅子に沈み込む。
「もういい。あなたには何も期待しない」
「それでも貴様らは司令たる私に従うんだ。分かっているな。鐵純壱位!」
「......」
仁武は鋭く塚早を一瞥すると、無言で踵を返して司令室を出た。
廊下にいた職員たちが、ぎょっとしたように道を空けていく。よほど恐ろしい形相をしていたのだろう。
デッドマターに対抗するため、さらなる戦力が必要なのは分かる。なりふり構っていられないほどに状況が切迫していることも、他に戦力になりそうな志献官がいないことも。頭では分かっているが、感情がついてこない。
行き場のない憤りを燃え余したまま足早に廊下を行く。防衛本部の奥にある賦活処置室へと足を向ければ、途中で栄都に出くわした。栄都もまだ知らないはずだ。
「あれ? 仁武さん、どうしたんですか? 怖い顔して」
「栄都、ついてこい」
「はい? なんで......」
疑問を口にしながらも、栄都が小走りでついてくる。仁武は固く拳を握り締めたまま、重々しく吐き出した。
「凍硝が、純の志献官として作戦部に入る」
「え? 七瀬が? どうして......純の? なんで、だって、まだ志献官にもなってない」
「塚早司令の決定だ。既に賦活処置を行うよう命令が下されている」
「そんな、まだ小さいのに!」
「ああ。だが、もしかしたらまだ──」
ふたりは頷き合って、賦活処置室へと走り出した。
小さく未熟な両の手に、朱塗りの盃がひとつ。中にはなみなみと透明な液体が湛えられている。最終賦活処置のための"水"だとの説明があった。元素と魂を結びつけるための"水"だと。
七瀬は横目で側に控える人をチラリと見やった。
端座する七瀬の側には、白い浄衣(じょうえ)姿の人影がひとり。顔を布で覆い、七瀬の斜向かいでこちらを向いて同じように背筋を伸ばして座っている。
「──どうぞ」
低く落ち着いた男の声とともに、促すように掌が向けられた。
事前に教わっていたとおり、数度に分けて飲み干し、目の前の三方に盃を返す。
味のない冷たい"水"がするりと喉を滑り落ちていった。へその辺りからじんわりと全身に広がるような不思議な感覚に、七瀬は小さく身震いをする。
「これにて、最終賦活処置──元素との魂結(たまむす)びの儀は相成りました。このほどより、凍傷七瀬様は窒素の志献官となられます。元素の御力を用い、死せる元素に立ち向かい、この結倭ノ国を、世界をお救いください」
男は述べると、床に両手をついて深々と頭を下げる。七瀬もぎこちなく真似をして頭を下げると、男はゆっくりと上体を起こした。
「気分はいかがですか? 痛みなどがあれば仰ってください」
先ほどとは少し調子を変えた男の声に七瀬は首を振った。気分は悪くない。身体に痛みもない。ただ、少しだけ違和感がある。しかし、その違和感を的確に表す言葉を探している間に、その感覚はすっと消えてなくなってしまった。
「遅れて異変を感じる場合があります。そのときは無理をせず、すぐに申し出てください」
「──分かりました」
七瀬が頷くと、男は無駄のない動きで立ち上がり、出口へと向かっていく。
七瀬はほう、と小さく息を吐いた。知らぬ間に緊張していたらしい。無事に賦活処置が終わった安堵でようやく周りを見る余裕ができた。
最終賦活処置を行うこの部屋は、防衛本部の奥にある賦活処置室のさらに奥。隠し扉の中にあった。
白い小さな部屋だ。窓もない。けれど、どこからか明かりが滲んで仄明(ほのあか)るい。天井には雲の透かしの入った飾りが施され、正面には祭壇があった。一番高い位置に置かれた鏡が太陽のように狭い部屋を見霽(みはる)かしている。
その下の段には数多くの試験管が並べられていた。その並びは、七瀬が養成所で教わった元素周期表の並びに酷似している。よく見れば空の試験管もあるが、ほとんどの試験管には先ほど七瀬が口にした"水"と同じ透明な液体で満たされ、厳重に封がされていた。
「凍硝純参位」
神秘的に淡く輝くその試験管をぼんやりと眺めていた七瀬は、呼ばれてハッとした。慌てて立ち上がり、出口へと向かう。先ほどの男が扉の前に下げられた御簾を持ち上げて待っていた。軽く頭を下げて御簾をくぐれば、ふっと空気が変わったのが分かった。
賦活処置を行った御簾のあちら側の空気は清浄でありながら重々しく、まるでたくさんの目に見られているような感覚があったが、御簾一枚通り過ぎたそこは、いつもと変わりのない空気になる。
「凍硝純参位。ご武運を──どうか、ご無事で」
ずっと温かみのない口調だった男の声に、最後の最後で感情が滲んだ。それがどんな感情かは七瀬には分からなかったが、ひとつ深く頷いて扉を開けた。
「七瀬!」
「兄さま?」
隠し扉の前で待っていた予期せぬ人の姿に七瀬は目を見開いた。賦活処置を受けることは急に決まったため、栄都にも伝えていなかったからだ。
「七瀬......」
栄都は走ってきたように、肩で息をしていた。何かを言いかけて口を噤む。七瀬は栄都の顔を一心に見つめた。困り果てたような顔をしている。悪いことをしてしまったのだろうか。七瀬は急に心配になった。
「兄さま。ぼく、兄さまと同じ純参位の志献官になりました。窒素の志献官です」
栄都はぎゅっと口を結んだ。そして、出会ったばかりの頃にたまにしていた、どこか途方に暮れたような笑みを浮かべると、七瀬の肩に両手を置いた。熱い手だった。
「うん......そっか。そっか。すごいな、七瀬」
「これでやっと、兄さまのお役に立てます」
ずっとこの日を待ち望んでいた。
七瀬が栄都を追って燈京に来た後、栄都は養成所にも暇を見つけては頻繁に会いに来てくれていた。けれど、それだけでは寂しかった。周りは七瀬よりも年上が多かったからなおさらだ。養成所は学ぶことばかりで過酷な労働を強いられることはなかった。全く違う場所なのに、どうしてか労働施設を思い出して早く栄都に会いたいと、そればかりを考えていた。
栄都が純参位になると、彼は燈京外から燈京へと両親を呼び寄せた。栄都は元々寮暮らしだったが、七瀬を伴って実家に帰ることも多くなった。栄都が七瀬に会うため、度々養成所を訪れていると知った前の司令が、任務に支障のない範囲で、と家から通うことを特例で許可してくれたのだ。
もちろん、毎日ではない。栄都は寮にいることの方が多かったけれど、養成所と寮で別れていた頃に比べれば、格段に一緒にいられるようになった。
嬉しかった。けれど同時に、栄都と帰る安酸家は居心地が悪くもあった。
栄都の両親は優しくて──優しいのに、馴染めない。
自分の家だと思っていいと、栄都の両親は言ってくれたけれど、それでも七瀬の帰る家という実感は湧かなかった。栄都がいなければ、七瀬はきっとそうそうに逃げ出していただろう。実際、栄都が帰らなければ七瀬も行くことはなかった。
自分でも、どうしてそんな風に思うのかは理解ができなかった。あえて理解しようとも思わなかった。
栄都さえいればそれでよかったから。
そんなときだ。横浜がデッドマターに襲われ、栄都がその任務に向かったと聞いたとき、七瀬は怖かった。
自分は養成所に通っているだけの、力のない子供だ。兄さまと呼んではいるけれど、本物の家族ではない七瀬には、栄都がどうなったのかという報せは届かない。
栄都が戻ってこなかったらどうしよう、と七瀬はたまらず混乱の最中にある本部に忍び込んだ。そうしてやっと栄都を見つけたとき、七瀬は心の底から安堵した。すぐに帰されてしまったが、その日から、七瀬はずっと、自分の知らないところで栄都が二度と帰らなくなってしまうのではないかという恐怖に怯えていた。
でも、これでもう安心だ。七瀬も一緒に戦える。
「兄さまの願いは、きっとぼくが叶えます」
みんなが心から笑顔になれる世界を取り戻すこと。栄都の願いが、七瀬の願いだ。
「うん......ああ! 頑張ろうな!」
栄都が両手でかき回すように七瀬の頭をくしゃくしゃにした。突然のことに瞬きをしながら栄都を見上げれば、七瀬の大好きな温かな笑顔がそこにあった。
「そうだ! 七瀬、仁武さんのこと覚えてる?」
栄都が後ろを振り返る。少し離れた場所に、背の高い大人が立ち尽くしていた。いつからいたのだろう。最初からだろうか。栄都のことしか見ていなかったため、気がつかなかった。
七瀬はそっと栄都の背中に隠れる。確か、七瀬が栄都に会うため初めて防衛本部に来たときに会っている。
「鐵仁武純壱位だ。君を作戦部に歓迎する。凍硝七瀬純参位」
「......よろしくお願いします」
小さく頭を下げれば、仁武は少し困ったような顔で頷いた。
「それじゃあ七瀬、みんなにも挨拶しに行こう」
「はい、兄さま」
差し出された手を迷いなく握る。七瀬の手も昔より大きくなったはずだが、栄都の手はもっと大きくなって、大人の手に近づいている。
(よかった......)
今日からはもう、栄都が防衛本部に帰るからと手を離さなくてもいいのだ。栄都が知らぬ間にいなくなってしまうのではと怯える必要もないのだ。
そう思うと、ずっと寒かった心にぽかぽかと温かな火が灯る。
七瀬はぎゅっと栄都の手を握る手に力を込めた。
そのとき、ふと、胸を過った既視感に七瀬は小さく首を傾げる。しっくりくるようで、どこか違うようなこの感覚はなんだろう。何かが足りないような左手を、七瀬はじっと見下ろした。
「どうした? 七瀬」
「何でもありません」
七瀬は首を横に振る。何であろうと、今ここに栄都がいることが何よりも大切だ。
これからはずっと一緒にいられる。守られるだけではなく、待つばかりでもなく、共に戦える。
その事実だけが、七瀬のすべてだった。
(終わり)
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら