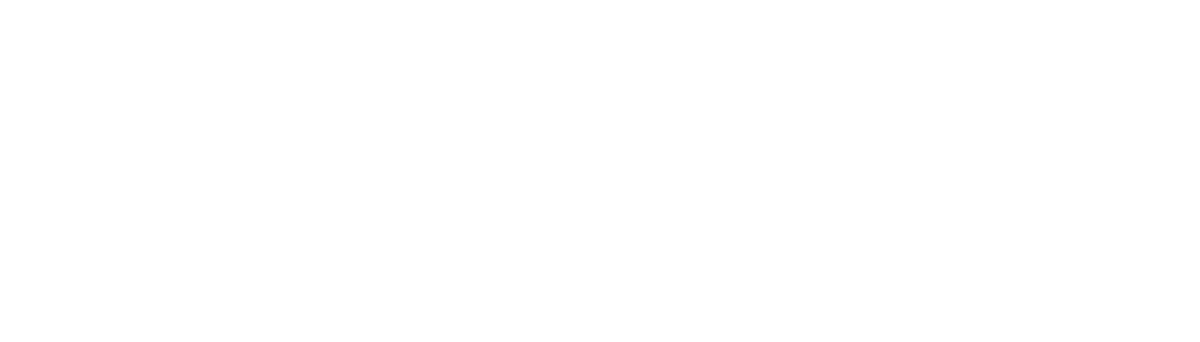INFO
24.09.29
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十一- 清硫十六夜の濁流(1)
著者:麻日珱
おちていく──。
四肢が空を掻く浮遊感。我が身ひとつで宙に放り出された頼りなさに、為す術もなく天を仰いだ。
晴天だ。息を呑むほどの。
眩しさに目を細めた先に黒い人影がひとつ。
胸を押された衝撃の余韻が唯一、罪人を指し示す。
遠ざかっていく黒い人影に眼がふたつ。
月に似た光を放つ黄色い瞳が、目蓋の裏に隠れて消えた。
(ああ──あれは、俺だ)
ならば、これは、夢だ。
絶叫も上がらぬ口元に、ゆるりと笑みが浮かんだ。歪な笑みだ。
耳元で風が泣いている。あるいは、嘲笑っているのかもしれない。
落ちていく。
墜ちていく......。
──グシャリ。
ああ、命の潰える音の、なんと残酷なことか。
「お兄ちゃん!」
キンと響いた少女の声に清硫十六夜はハッと目を覚ました。どっと汗が噴き出し、呼吸が粗く乱れる。ドクドクと心臓が脈打って、喉へとせり上がってくるようだ。
「おにぃ! いつまで寝てんの? 列車に乗り遅れるよ!」
ドタドタと足音を鳴らして近づいてきた少女は、布団に仰向けになる十六夜の顔をのぞき込んだ。
「なぁんだ。起きてるじゃん」
「──茜(あかね)?」
三つ年の離れた妹の茜は、ぱっと花咲くように笑顔になると、十六夜の手を掴む。
「寝ぼけちゃってさぁ。そんなんで燈京でやってけるのかなぁ」
まるで大根でも引っこ抜こうとするように茜は十六夜の手を引っ張った。十六夜は、そんな妹をぼんやり見つめる。
気の強そうな顔立ちに、あどけなく染まる紅色の頬。髪は十六夜の黄色よりも赤みが強い。その髪を高い位置で括るのは、誕生日にねだられて贈った藍色のリボンだ。動く度に元気にぴょこぴょこと跳ねる様子が、本人の性格をよく表している。
「もー、起きてってば! お兄ちゃんおっきいから、重たいんだよー!」
あまりにも起床に非協力的な兄に頬を膨らませながら文句を言っていた妹の顔が、次第に曇っていく。
「どうしたの? お兄ちゃん」
心配そうにぎゅっと握られる手に十六夜は息を止めた。
これは現実だろうか?
少女の小さな手のぬくもりも、握る力の強さも、心配そうに呼ぶ声も。
「おにぃ?」
十六夜は一度その手を握り返してゆっくりと身体を起こし、ぐるりと辺りを見回した。見慣れた部屋だった。十六歳で実家を出るまで使っていた部屋と何ひとつ変わらない。
「......調子悪いんだったらさ、なら、燈京なんて行くのやめなよ」
茜は、十六夜の手を握りながら傍らで俯いていた。
「ずっと家にいればいいじゃん。志献官になんてならなくってもさ、いいと思うな」
俯きながら拗ねたように口をとがらせ、十六夜の手を弄ぶ。不安そうにチラチラとこちらを窺うような視線に目を細め、十六夜は空いている方の手で顔を覆った。
「......そうしよっかなぁ」
「え!?」
チラリと指の隙間から妹を覗けば、大きな目をまん丸に見開いている。パクパクと口を開閉させた茜は、飛び上がるように立ち上がって部屋から出て行った。
「お、お父さぁん、お母さぁん! お兄ちゃんが変になったぁ!」
来たときと同じ、ドタバタとした足音が遠ざかっていく。
「おまえが言ったんだろー」
小さく笑っていると、遠くでまくし立てる少女の声の合間に父と母の声が漏れ聞こえてくる。
「──っ」
大きく吸い込んだ息も、深く吐き出した息も震えていた。顔を覆う手の下で涙がにじんだ。
(全部、悪い夢だ)
そう。何もかも悪い夢。
地獄へと堕ちていくような夢だった。
「十六夜ー? あんたホントに大丈夫ー?」
母が呼んでいる。十六夜は寝間着の袖で涙を拭い立ち上がり、居間へと向かう。
「十六夜、燈京に行かないって本当なの?」
忙しそうに朝食の準備をしながら母が言う。茜もそれを手伝いながら、小生意気にもしかつめらしい顔をして頷いていた。
「体調が悪いならいいんじゃないか? 一日、二日遅らせたって」
ひとり卓袱台の前に座っている父が言えば、母はその背中を通りすがりにばしりと叩いた。
「お父さんはもう! 切符だって買ってるんですよ。それよりも、のんびり座ってないでお箸くらい出してくださいな」
「ゲホッ! 母さん、もっと力加減をだね?」
「まあ! 力持ちにしたのは誰かしら?」
とほほ、と父が食器類を入れている戸棚に手を伸ばす。
バタバタと皆が慌ただしい。我が家の日常風景だった。
十六夜は再びこみ上げてきそうになった涙をあくびで誤魔化し、目をこすって腰を下ろす。座布団に無意識に触れて、懐かしさが込み上げた。
朝食は、白米に味噌汁。煮物は昨日の夕食の残りだ。焼き魚に卵焼きまでついている。
十六夜は、味噌汁から立ち上る湯気を目で追いかけ、味噌汁に手を伸ばした。
「それでどうするの、十六夜」
「......え?」
味噌汁の椀に触れる寸前で手を引っ込める。母へと顔を向ければ、怒っているような、困っているような顔で座っていた。いつの間にか、茜も父も座って卓袱台を囲んでいる。
「燈京よ。行かないの? 志献官になるの、あんなに楽しみにしてたじゃないの。昨日だって遠足前の子供みたいに興奮しちゃって」
「そうだけど......」
十六夜は口ごもった。"今日"は、燈京にある志献官の養成所へ向かう日だ。いつもよりも食事が豪華なのもそのせいだった。
「おにぃ、行く前からお家が恋しくなっちゃったんだねー」
ふふん、と茜が黄色い卵焼きを箸先で割りながら得意げに笑う。十六夜はそんな妹に向かって泣くように笑った。
「そうだよ」
恋しくて、恋しくて、仕方がなかった。
「あーあ。俺、志献官になるのやめよっかなぁ」
斜め上を見上げて笑う。こみ上げる涙でゆらゆら天井が揺れていた。
そんな十六夜を見て、家族が顔を見合わせている。
「ね? お母さん、お兄ちゃん変」
「ほんと、熱でもあるのかしら」
「どれ、父さんがひとつ防衛本部に連絡してやろうか」
腰を浮かした父の着物を母が引っ張って止める。あんたはもう、とバシバシと父の腰を叩いて、母が真っ直ぐに十六夜を見つめた。
「十六夜、本気で言ってるの?」
「......」
十六夜は目を伏せた。なんと答えていいのか分からなかった。
十六夜は小さい頃からずっと、志献官になりたかった。子供の頃の憧れは、分別が付くようになっても変わらなかった。そんな子供の頃の夢を天が聞き届けたかのように、十六夜には志献官の適性があった。しかも、適性検査の段階で純の志献官になれるほどの強い硫黄の因子があると判明したのだ。
だが、素直には喜べなかった。既に純の志献官として、硫黄の志献官がいたからだ。同時期に同じ元素で純の志献官にはなれないと、十六夜は適性検査の結果が出た段階で告げられていた。
そんな十六夜の前にはふたつの道が提示された。そのまま混の志献官として防衛本部に入り、混の志献官の業務に従事しながら地道に実績を積んでいくか、将来的に純の志献官になることを視野に入れた志献官の養成課程に進むか。
十六夜は迷ったが、防衛本部の強い勧めもあって後者を選んだ。今はなれないとしても、いつか自分に役目が回ってくる日があるかもしれない。そのときになって慌てるよりも、確かな力をつけたい。どうせ、役目が回ってくるまで混位として働かなければならないのなら、養成所に行く方がいいと判断したのだ。
いつか自分の力でデッドマターから結倭ノ国を取り戻し、家族に安全な暮らしをさせてやる──そんな夢を全て語ったことはないが、家族は皆、十六夜がどれだけ志献官になりたかったか知っている。実際、十六夜が適性検査の結果を持ち帰った日はお祭り騒ぎだった。"昨日"までは待ちに待った燈京へ行く日が来たのだと、十六夜自身も胸を膨らませていたのだ。
(でも......)
"悪夢"を、見てしまったから。どうしても今は、家族の側を離れたくなかった。
「──もし、本気だって言ったら?」
「ダメだよ」
「え?」
口を開いたのは茜だった。完全に食事の手を止めて、真っ直ぐに十六夜を見つめている。
「ここにいちゃダメだよ。お兄ちゃん」
「ど、して......」
言葉をつまらせる十六夜に、茜はにっこりと笑った。父も母も微笑んでいる。
「お兄ちゃんは行かなくちゃ。デッドマターをやっつけるんでしょ?」
十六夜はぶるりと震えた。風景が光に飲まれるように白くなっていく。部屋が消え、卓袱台も、そこに乗っていた朝食も消えた。ただ光が一家を包んでいる。
「まっ......て」
喉がカラカラだった。父の、母の、妹の輪郭が消えていく。
「イヤだ......イヤだ! 待って。父さん、母さん、茜!」
十六夜は手を伸ばし叫んだ。その手の小指にするりと茜の細い指が絡まる。
「約束。ね?」
屈託のない笑みを残して妹が消えていく。
「イヤだ、置いていくな! 俺もそっちに──」
消えゆく光の残滓を追いかける。指先から消える家族のぬくもりに、十六夜は縋った。
『お前はまだだろ』
低い声が耳朶を打ち、ドンと胸に衝撃があった。
世界は一瞬で闇に飲まれ、全身を包む浮遊感に十六夜は絶望した。
上下も前後も左右もない。闇の中に放り出され、為す術もなく墜ちていく。
呆然と見開いた十六夜の目には、白く浮かび上がる人影がひとつ。
不自然に首が折れ曲がった男が、生気のない目で十六夜を見つめていた。
(おまえは──)
舌が痺れたように言葉は声にならず消え、十六夜は遠ざかる男を見つめ返した。
落ちていく
おちていく......。
──どこへ?
ここはもう、地獄じゃないか。
※ ※ ※
「──っ!」
身体が大きく跳ねて覚醒する。同時に体中に広がった痛みに十六夜は低くうめき声を上げた。
「ぐっ......ぅあ......っ」
息をするだけでも全身が鈍く痛む。浅く速く呼吸を繰り返しながら視線を素早く走らせれば、無機質な天井が目に入った。
(ここは......?)
唐突な目覚めに心臓が早鐘を打っている。状況が分からず混乱していれば、ひょいと小さな影が視界の端にちらついた。
「あ! 起きました? 起きましたね? 十六夜さん」
ぴょんぴょんと視界の端で跳ねているのは、白いキャップを被ったモルだった。作戦部医療班所属の看護モルだ、と数拍おいて気がついて、十六夜は深く息を吐き出す。どうやら、医務室の寝台に寝かされているらしい。
「っ......」
再び走った痛みに身体を強ばらせていれば、枕元にやって来た看護モルが心配そうに十六夜を覗き込んだ。
「酷い怪我でした。心臓も何度か止まりかけたんですよ。純の志献官じゃなかったらとっくに死んでました」
十六夜は慎重に身体から力を抜いた。
「俺は、どうして......?」
「覚えてません? デッドマターと戦って大怪我をしたんです」
「デッドマター......?」
そうだったか、と記憶を探る。ぐちゃぐちゃと思い出が絡まり合って、頭の中が混乱していた。
「今って、何年......?」
「はい? 新和四年の十二月ですよ」
「──ああ」
そうか、と十六夜は嘆息した。
ならばあの光景はやはり夢だったのだ。
家族との最後の温かい思い出は、もう二年半以上も前のことになる。
「大丈夫です?」
看護モルに問われて十六夜は返事の代わりにゆっくりと瞬きをした。記憶が混乱していたが、徐々にデッドマターと戦ったことが蘇ってくる。死ぬつもりはなかったが、死んでも仕方ないとは思っていた。
「今回助かったのは奇跡だって、お医者さんは言ってました。でも......その......傷が」
看護モルはもごもごと呟く。申し訳なさそうな看護モルの言葉を要約すると、志献官の治癒力をもってしても治らない傷が体中に刻まれているそうだ。傷跡の方はデッドマターに負わされた傷ではなく、十六夜の武器である縄鏢でついた傷だ。硫黄で作った縄が身体に張り付いて治療もままならず、なんとか剥がしたものの、皮膚ごと剥がれたせいで痕が残ってしまったのだという。
「どうしてそうなったかは分からないんです。本来、身に宿した元素は本人を傷つけませんから......」
「うん」
十六夜には理由が分かる気がしたが、それをこの小さな存在に言う必要はないだろう。
看護モルは心配そうな顔をしていたが、重い空気に耐えられなくなったのか医者を呼んでくると逃げていった。
その姿を目の端で見送って、十六夜は溜め息をつく。
(──生き延びちまったのか)
体中包帯だらけだ。寝返りを打つこともままならない。ただ明瞭になってくる意識だけが、頭の中を走り回るように忙しない。
(なんで、あんな夢......今更)
十六夜の家族は、夢に見た門出の日のちょうど一年後、故郷ごとデッドマターに飲まれて消えてしまった。養成所を出て、これから志献官としてやっていくのだと希望を胸に抱いた日。一度実家に戻って喜びを伝えようとしていた矢先の出来事だった。
もしもあと少し、志献官になるのが早ければ。デッドマターが来るのが遅ければ、家族を救えていたのだろうか。
もう誰もいないと分かっているのに、十六夜はまだ、どこかで家族が生きているような気がしている。
純の志献官になって侵食された故郷を見に行っているのに。
侵食領域の中で崩れかかったまま時を止めた、空っぽの我が家を目の当たりにしているのに。
(みんな......頑張れって、言いに来たのかな......)
死を覚悟した十六夜の、心の底で早く家族の元へ向かいたいと願う背中を押し返すために現れてくれたのだとしたら、なんて優しくて残酷な夢だろう。
(あいつも......)
夢の中で暗闇へと突き飛ばしたのは十六夜の同期だ。養成所時代からの付き合いで、一緒に純の志献官になった友人だった。
彼は鉄塔から落ちて死んだ。
養成所を出てデッドマターと初めて対峙した同期は、恐怖と絶望に呑まれた。防衛本部から逃げ出した同期を連れ戻したのは十六夜だった。
防衛本部からもデッドマターとの戦いからも逃げられないと知り、間もなく、同期は心を壊した。人類はデッドマターには勝てないと喚き散らし、こんな戦いは無意味だと暴れた。
『──残念だが、あれはもう使えない。このままでは防衛本部全体の志気にも関わる』
だから、殺せと。上司は冷徹に命令した。それが、十六夜のもうひとつの仕事だった。
国家防衛局舎密防衛本部には裏の顔がある。
デッドマターが沈静化したことで、平和な時代が訪れたからだ。
誰もがデッドマターによる蹂躙に終止符が打たれたと思った。あとはよくなるばかりだと、破壊し尽くされた文明を取り戻すために必死に足掻いた発展の時代──その平和な時代に、戦闘に特化した志献官の存在は容易く人々の脅威となった。
それこそ、今よりもなお過激に、特殊な力を持つ志献官は拒絶されたのだ。
反発のあまりの大きさに、防衛本部は再編を余儀なくされた。そのときに秘密裏に作られたのが、防衛本部の裏組織だ。
防衛本部の障害となる存在は人であれ、物であれ、情報であれ排除した。あるいは未だデッドマターの脅威は去っていないと情報を操作し、時には防衛本部の志献官の有用性を知らしめるように工作し、防衛本部の必要性を示してきた。
こうして裏の組織が暗躍する間に、デッドマターは再びじわじわと世界を飲み込み始めた。皮肉なことに、世界の危機が防衛本部の存在意義を改めて人々に突きつけたのだった。
一時は活躍した裏組織だが、今ではその存在感は薄れている。組織というほどの規模もない。そんな中で防衛本部にとって不都合な汚れ仕事を一手に引き受ける存在となったのが、硫黄の志献官だった。
燈京に来た当初、十六夜は硫黄の志献官の役目などなにひとつ理解していなかった。
養成所の課程を修了する直前に硫黄の志献官が任務で命を落としたと知らされ、純の志献官になるよう言われたときも、具体的な役目はまだ教えられていなかった。
だから、十六夜は純の志献官になれるのだという誇らしい思いだけを抱いて養成所を出た。硫黄の志献官として活躍するのだと、家族もきっと喜ぶだろうと期待に胸を膨らませていたとき、その悲劇は起こった。
故郷も、家族も失って──戦う理由の核を失って。
何のために戦えばいいのか分からなくなった十六夜に与えられたのが、硫黄の志献官という存在の裏の役割だった。
寄る辺を無くした十六夜は、差し伸べられたその手を取った。
それが、死神の手だとしっかりと理解していながら。
そうして初めて命じられたのが、同期の始末だった。
純の志献官は、ひとつの元素にひとりだけ。もしも同期がその元素を占め続ければ、次に同じ元素の志献官が立てない。なぜなら、その元素の賦活処置ができなくなるからだ。
初めての殺人命令に十六夜は震えた。どうにか同期を説得できないかと試みたが、全て無駄だった。追い詰められた同期は防衛本部の屋上から飛び降りようとして、止めようと羽交い締めにした十六夜もろとも落ちた。
十六夜は咄嗟に屋上の縁を掴んだ。ずしりとふたり分の重みが掛かった手がずり落ちそうになった。同期は十六夜にしがみついて縋り、十六夜を道連れにしようといびつに笑った。その狂気に染まった顔に恐怖が込み上げ、十六夜は咄嗟に同期を蹴り落としたのだ。
あ、と思ったときには、ドン、と重たい物が落ちる音が十六夜の耳に届いていた。
けれど──同期は死ななかった。無駄に丈夫な志献官の身体のせいで死ねなかった。
ヒューヒューと空気ばかりが漏れる口で、同期は言った。
殺してくれ、楽にしてくれと──。
だから、十六夜がトドメを刺した。そうするしかなかった。
それからだ。ポツポツと殺しの任務が与えられるようになったのは。
思ってみれば、同期を殺せという命令は、ある種の試金石だったのだろう。これから十六夜が裏の任務を継続できるかどうかの。
もしも殺せなかったのなら、十六夜はただの志献官でいられただろうか。
不意に浮かんできた考えにみぞおちの辺りがぎゅっと痛む。
「......っ」
十六夜は固く目を閉じて歯を食いしばった。
人を殺すために、志献官になったんじゃない。
人を守るために、志献官になったはずなのに......。
(いっそ、死んでりゃよかったんだ)
それでも、まだ、生きている。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら