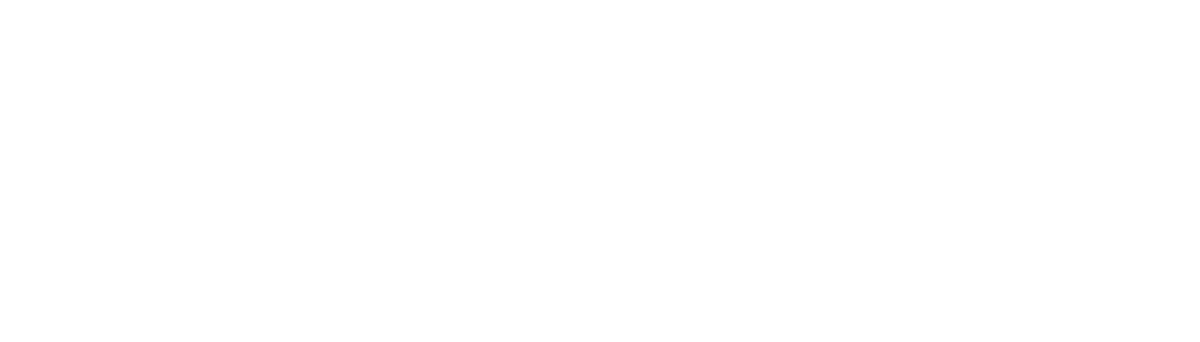INFO
24.09.18
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十- 舎利弗玖苑の結論(4)
著者:麻日珱
前回「断章-十- 舎利弗玖苑の結論(3)」はこちら
「あ、おんちゃん!」
「やあ、むっちゃん」
防衛本部に戻った玖苑のもとに駆け寄ってきたのは、炭素の志献官、有生陸稀純参位だ。
「探したー! お願いがあるんだけど、いい?」
「もちろんさ!」
らしくなく少し気持ちが下を向いていたから、陸稀の明るさに気分が上を向く。こっちこっち、と誘われるまま、玖苑は陸稀についていった。
「どこに行くんだい?」
「運動場! 今、元素術の訓練やっててさ」
「分かった。ボクにお手本を見せてほしいんだね?」
「さっすがおんちゃん、話が早ーい!」
パン、とハイタッチをして運動場へと向かう。
「でも、見せてほしいのおれじゃないんだよねー」
「そうなのかい?」
「うん。おれ、元素術ちょー得意」
にかっと笑う陸稀に、玖苑もニコッと笑みを返す。屈託がないのは陸稀のいいところだ。
「じゃあ、別の誰かに見せたいってことかな?」
「そう。得意だから、おれが碧壱に教えたいって言ったんだ。でも、なんと!」
陸稀はぐぐっと拳を握ると、キリリとした顔で言葉を溜める。
「おれ、教えるの上手じゃなかったー」
へにゃりと力を抜いた陸稀に玖苑は小さく吹き出した。
「むっちゃんは感覚派だからね。でも、仁武はどうしてるんだい?」
「うーん......なんか一回仁武が作った刀を碧壱に向けるって事件はあったんだけど、一応仲直りしたのかな? 一緒に訓練してるし。でも、やっぱりなかなか元素術がうまくできないみたいで......。おんちゃんの元素術見たら刺激になるんじゃないかと思ったんだ」
そんなことを話している間に運動場へと到着する。広い運動場には人気(ひとけ)がなかったが、ひとつだけ黒い上着を羽織る人影があった。
「彼かな?」
「うん。やっぱりまだいた......ちょっと思い悩んじゃってるみたいでさ。あいつ、肩から力抜くの、へたっぴなんだ」
距離がある上にこちらに背を向けているので顔までは分からないが、あれが碧壱なのだろう。
「よーし。ここは先輩らしく後輩を導いてやろうじゃないか!」
「ひゅー! おんちゃんかっこいー!」
いざ、と足を踏み出そうとしたところで、碧壱に近づいていく三人の志献官に気がついた。
「おや。彼らもボクの元素術の気配に惹かれてやってきたのかな?」
「もう? 察知能力ヤバヤバじゃん。でも違うと思う。アイツら、すっげーヤなヤツなんだ。止めないと──」
「待った」
玖苑は勇んで彼らの元へと向かおうとする陸稀の腕を掴んだ。
「おんちゃん?」
「どうするか見てみよう」
三人は何かを言いながら碧壱に近づいていく。自主練していた碧壱の肩を先頭にいた短髪の青年が小突いた。友好的な空気はまるでない。短髪の青年よりも上背のある碧壱は、小突かれた肩を患わしそうにはたく。慣れた様子だった。相手は三人だが、物怖じしている様子はない。
「おんちゃん」
「分かっているさ」
三人と対峙する碧壱はもちろん、あとから来た三人も玖苑と陸稀の存在には気付いていない。距離はあるものの姿を隠しているわけではないから、単純に獲物に狙いを定めて視野が狭くなっているのだろう。
「彼らは混の志献官みたいだけど、あれも新人かい?」
「そうだよ。純の志献官候補生。早く碧壱を助けに行かないと!」
「まあ、ボクに任せたまえ」
玖苑は軽やかな足取りで一団へと近づいていく。混の志献官たちは碧壱を罵ることに一生懸命なのか、玖苑が近づいていることにも気付かない。
「もっと気配に敏感じゃないと。こんな体たらくじゃデッドマターとは戦えないね」
呟きながら近づく玖苑の声は、多勢でひとりを責めることに熱中している青年たちの大きな声でかき消された。
「ハッ! 何が源だよ。名前だけじゃねえか」
耳障りな濁声(だみごえ)で嘲弄する。たっぷりと悪意を含んだ音は、聞くに堪えない雑音だ。
「ご立派な名家のお坊ちゃんのくせに、元素術のひとつも使えねえのかよ」
三人は駅裏のごろつきのようにゲラゲラと笑う。
防衛本部に属している者たちは生まれも育ちも種々様々で、ガラの悪い輩も少なくない。志献官になるための要件は"元素の因子を持つ男子"という一点だ。人品は問わない。性根が曲がっている人間が混ざるのも仕方ないことだ。
仕方ないことではあるが、だからといって現在の地位にふさわしい態度を取らなくていいという理由にはならない。
(何だか懐かしいな)
玖苑も入隊当初は度々因縁を付けられた覚えがある。戦闘訓練中、混位から上がってきた同期数人が結託して、玖苑の顔に傷を付けようと画策したこともあった。十六夜の助けで事なきを得たが、あの頃は玖苑も未熟だったこともあり、母譲りの美貌に取り返しのつかない傷がつくところだった。
(まったく、嫌になってしまうね)
一対一で立ち向かってくる度胸もないくせに、徒党を組むと自分が強くなったと勘違いをする。そういう輩に限って大した能力もなかったりするのだから始末に負えない。
「お前みたいな無能より、混のオレらの方が上手く元素術を使えるっての。なあ!」
真ん中で声高に罵っていた短髪の青年が、賛同を求めるように仲間に視線を向け──心の醜さが表れているような笑顔が、玖苑を捉えて引きつった。
「やあ! 盛り上がっているね」
「と、舎利弗純壱位!」
他の二人も悲鳴のような声を上げて飛び退る。これが今年の純の志献官候補生か、と玖苑はあからさまにじっくりと眺めた。十六夜が以前言っていたように、本当に"賦活処置を受けられるだけ御の字"の実力しかなさそうだった。
ふと、チクチクと刺さるような視線を感じてそちらを見やれば、さっと目が逸らされる。混の志献官たちよりも苛烈な眼差しを向けていたのは、初対面の碧壱だった。
「うん?」
助けに入ったのになぜ睨まれたのだろう。首を傾げていると、今度は混の志献官の報が声高に喚いた。
「お前、有生!」
「何だよ」
短髪の青年は玖苑の隣に立つ陸稀に指を突きつけた。陸稀はといえば、こちらも鼻息荒く胸を張って仁王立ちしている。どうやら混時代の知り合いらしい。
「お前、舎利弗純壱位を呼んだのか!」
「違いますー。馬鹿が馬鹿なことしようとしてるから罰が当たったんですー」
べぇ、と陸稀が子供のように舌を出す。ぴったりと玖苑の隣にいるため、陸稀に掴みかかることも出来ないのだろう。三名の混の志献官たちは苦々しげに顔を歪めていた。玖苑はそんな三人の表情をじっくりと眺めて微笑んだ。
「ずいぶん楽しそうにしていたじゃないか。キミの大きな声が遠くまで響き渡っていたよ」
「......」
三人は気まずげに目配せし合う。玖苑を目の前にして逃げ出すことも出来ず、肩を竦めて俯くばかりだ。
玖苑は改めて碧壱の方を見た。なぜか迷惑そうに眉を寄せている。身につけている元素記章は『H』。水素の志献官だ。
「おや。いつの間にか水素の志献官がいたんだね」
「......っ」
玖苑が意外そうに言えば、碧壱が目を見開いて絶句する。陸稀も驚いたような顔で、恐る恐る聞いてきた。
「おんちゃん......もしかして、碧壱と会ったことない? 同じ作戦部なのに?」
「あったかな? 覚えてないや」
新人の指導は仁武が行っているそうだし、玖苑はほとんどひとりで任務をこなしている。廊下ですれ違ったことくらいあるかもしれないが、玖苑に声を掛けてくれる人やモルは大勢いるから、その中のひとりのことをいちいち覚えてなどいない。
「それよりも、キミたち。どこに行くつもりかな?」
玖苑はそろりそろりと逃げようとしている三人に笑みを向けた。もう顔は割れているのに、なぜそんな無駄なことをしようとするのだろうと心底不思議だ。
「ボクは階級で云々言うのは好まないけれどね。キミたちは混の志献官だろう? 純の志献官相手によってたかって、何様の立場から文句を言っているのかな?」
「いえ、自分たちは......」
もごもごと口元で言い訳にもならない言葉を呟いて俯く。ふたりはそのまま悄然と黙り込んだが、残る真ん中のひとりは小鼻を膨らまして一歩前へと出てきた。最も声の大きい短髪の青年だ。
不平と不満を全身に漲らせている。玖苑を睨み付けるようなその目には、自分が正しいと信じて疑わない傲慢さがあった。
「お言葉ですが、舎利弗純壱位。我々は彼に現実を教えてやっていたんです」
口調こそ丁寧だったが、語気はとげとげしく、瞳には玖苑に対する敵愾心が満ちている。正直、純弐位になった辺りからこんな風に張り合ってくる志献官がいなくて少し退屈していたところだ。
「へえ、現実って?」
「そいつは元素術も使えないくせに、源家ってだけで純の志献官を名乗っている。偽物なんです!」
「それは驚きだな。ボクには──」
玖苑はチラリと碧壱を振り返った。怒るでも、困惑するでもなく、ただ温度のない侮蔑の眼差しが混の志献官たちに向けられている。
「問題なく最終賦活処置が終わっているように感じられるけどね」
何か明らかな目印があるわけではない。口で説明するのは難しい感覚だが、最終賦活処置を施された者特有の感覚が、碧壱からははっきりと感じられた。
「あり得ません! 混の志献官にもなっていないのに!」
真ん中にいる短髪の青年が吠えると、俯いていた他の志献官たちもそうだと賛同するように頷いた。彼らは、目の前にいる玖苑を何だと思っているのだろうか。
「ボクも混の志献官だったことはないけど?」
「舎利弗純壱位は特別です!」
向かって右側にいる混の志献官が突如叫び、玖苑と目が合うと我に返ったように息を呑んで顔を伏せる。髪から覗く耳が真っ赤になっていた。
「ボクが特別なのは事実だ。けれど、混の志献官を経ていないのはボクだけじゃない。彼が偽物だって言う根拠はなんだい?」
そう問えば、真ん中の青年が目を剥いて言い募る。
「純の志献官なら、どうして元素術が使えないんですか。我々混四位だって、元素力を発現させる程度の元素術を使えます。そいつは、源一族ってだけで贔屓されたんだ。こんな不正があっていいんですか! そんなヤツに結倭ノ国を守る資格なんてありません!」
「──源一族?」
玖苑は碧壱を振り返った。冷ややかな視線ばかり混の志献官に送っていた碧壱が、すっと姿勢を正す。まるで誇らしげに。
「それが何だい?」
「......え?」
碧壱があっけにとられたように目を丸くする。混の志献官たちも言葉を失っていた。
「それが何だって......源一族ですよ。第一世代の志献官にも名を連ねる名門の......」
左側にいる混の志献官がおずおずと教えてくれる。
「ああ、そういえば聞いたことはあるかもしれないな。キミがそうなんだね」
碧壱は硬い表情で玖苑を見つめた。興味のないことは意識の外に放り投げてしまう玖苑だが、さすがに目の前に本人が現れたとなると少しばかり興味が湧いてくる。
「一族と言うけど、元素の因子は何でもいいのかい? それとも、特定の因子を受け継いでいるのかな? だとしたら、代々水素の志献官ということ?」
いったいどういう機序で元素の因子を繋いでいくのだろうか。志献官になるための元素の因子を持っているのは男子だけだという前提からすると、男系の遺伝子に因子の情報が乗っているのかもしれない。ただ、もしそうならば、結倭ノ国の男子全員にのべつ幕なしに適性検査を受けさせるよりも、因子を持っている適齢期の男子全員に子供を作らせてしまった方が、因子を持っている確率も上がるし、なにより効率的だ。しかし、そうはならなかったということは、元素因子は遺伝しないか、限りなく遺伝しづらいのだろう。それこそ、男子全員に適性検査を受けさせる方がマシだというくらいに。
「キミが志献官になったのも一族の意向で?」
「だから、不正なんじゃないか」
すかさず誰かがぼそりと呟いた。左右のどちらかだろう。碧壱は左側の志献官を真っ直ぐに見据えている。両脇で握られた拳には、かなり力がこもっているようだった。
「だから? 意味が分からないな。純の志献官になるのに、血筋に何の価値がある? ボクをごらんよ! 親類に志献官なんていないけれど、ボクほど完璧な志献官はいないじゃないか!」
「それは、舎利弗純壱位だから......」
「そうさ。みんなはボクじゃないし、この源一族の彼でもない。自分が持っていないからって、持っている者を僻むのは愚かなことだ。彼が純の志献官を辞めたって、キミたちが純の志献官になれるわけじゃないだろう? 人の事をとやかく言う暇があるなら自分を磨いたらどうだい? ところで、キミたちは純の志献官候補生だそうだけど、純の志献官にはなれないよ」
三人が絶句した。真ん中の青年がどうして、と絞り出すように口にする。目を血走らせ、突き刺す勢いで碧壱に指を突きつけた。
「オレたちが純位に上がれないのはこういうヤツが──」
「バカだなぁ。キミたちが純位になれないのは家柄でも、彼がいるからでもなくて、単純にキミたちに力がないからじゃないか」
「っ、純位だからって、偉そうに!」
「偉そう、じゃなくて偉いんだよ」
真ん中の混の志献官は、顔を真っ赤にしていても、殴りかかってこない程度の分別はあるようだ。
玖苑は青筋を立てる混の志献官に、にこりと笑ってみせる。三人の顔が別の意味で赤らんだのも意に介さず、玖苑は後ろで手を組んで講釈を垂れるようにゆっくりと歩き始めた。
「階級は実力の証だ。強い者、能力のある者が尊ばれるのは世の常だろう? それとも何かな? キミは自分が一番偉いと思っているの? 何を根拠に? キミはどうしてそんなに偉そうに出来るのかな? ボクよりも優秀なのかい? 能力もないのに偉そうにしているのは誰だって? キミたちが因縁を付けている彼の実力がどれほどのものかは知らないけど、少なくとも家柄はあるわけだ。キミは? キミには何がある? その偉そうな態度以外にさ。ボクに教えておくれよ」
「あ、あ......」
脂汗をかいて眼球をぐらぐらと揺らす青年に、玖苑は一歩ずいっと近寄った。その泳ぐ視線を至近距離で追いかけて目を細める。
「キミこそ現実を見なよ。空っぽじゃないか」
「っ!」
とん、と人差し指で胸を突く。真ん中の混の志献官はひぅ、と喉を鳴らし、膝の骨を失ったかのように崩れ落ちた。ひきつけでも起こしたように震えながらぼそぼそと何かを呟いている青年を見下ろして、玖苑は小首を傾げて他のふたりに微笑みを向ける。
「具合が悪いようだね。連れて帰ってあげたまえ」
「し、失礼しました!」
「二度とお手間は掛けませんので!!」
ふたりは青い顔をして、へたり込んだ混の志献官を引きずるように去って行く。その姿を見送って、玖苑は改めて碧壱に向き直った。既に陸稀が心配そうに声を掛けているが、碧壱の目は射貫くように玖苑を見つめていた。
「キミも災難だったね」
玖苑が声を掛ければ苛烈な視線はすぐに陰に潜み、碧壱は複雑そうな顔で目を伏せる。
「──ありがとうございます。でも、あのくらい自分で対処出来ました」
「そうだろうね。だから、ボクが助けたのはどちらかと言えば彼らかな?」
碧壱は眉間に皺を寄せると、ごろつきのような志献官たちが去って行った方に顔を向ける。横で陸稀が溜め息をついていた。
「助けたって......ぼっこぼこのべっこべこだよ。言葉のグーが見えたもん」
遠い目をする陸稀に玖苑はうん、と笑って碧壱を見やった。
「言葉くらいなんてことないさ。そうだろう? キミ、何を持ってるんだい?」
碧壱の右手が小さく動くのを、玖苑は見逃さなかった。さっと引かれるその手を掴んで掌を開かせる。
「おや。ピンだね。もしかして、これで彼らを撃退するつもりだった?」
「......訓練をしていたので持っていただけです」
離してください、と碧壱が玖苑の手を振り払う。
「ふうん? それがキミの武器なのか。随分小さいね。でも、志献官たる者、デッドマターに向けるべき武器を人に使おうとするのはどうかな?」
「碧壱......?」
陸稀が不安げに声をかけるが、碧壱は一瞥もしない。ただ、あからさまに偽物と分かる微笑を貼り付けてピンを見せてくる。
「お守りのようなものです。三人を相手にするんですから、そのくらいは許してください」
「そうかい? まあ、そういうことにしておくよ」
碧壱は嘘くさい笑みを浮かべた口角をピクリと震わせた。
「第一、彼らが言っていたように私はまだ元素力もろくに扱えない未熟者です。仮にこれを使ったとして、相手を逆上させるのが関の山では?」
玖苑は軽く肩を竦めた。これ以上言い合ったところで碧壱は認めないだろう。
お守りとは言うが、元素術すら未熟な彼が、戦技訓練場でもない武器を手にしている理由など、深く追及せずとも知れたことだ。
「なんであれ、ああいう輩には関わらないことだ。それと、キミも純の志献官になれたんだから、元素術が使えないなんてことはないはずだよ」
「──舎利弗純壱位はどうでしたか?」
貼り付けたような笑顔のまま、碧壱が聞いた。その目に映る真剣さだけは本物だった。
「もちろんボクはすぐにできたとも! 思ったよりも簡単で拍子抜けしたっけ」
賦活処置を施してすぐだった。まるで呼吸をするように自然に、玖苑は自らの元素力を自由に扱うことができたのだ。
「......さすが、噂に名高い舎利弗純壱位ですね」
「おっと。同じ純位だ。階級付きなんて、堅苦しい呼び方はなしだよ」
「遠慮させていただきます」
「遠慮しないで。ちょうど退屈していたところだったんだ。たまには先輩らしいことをしてみるのも楽しそうだし。安心していいよ。ボクが完璧に教えてあげるから。すぐに元素術を使えるようになるさ!」
「何を言って......」
碧壱は怪訝そうに眉根を寄せると、はっと陸稀を見た。
「陸稀、まさか」
咎めるように睨まれた陸稀はばつが悪そうに口を尖らせた。
「ビッグバンって感じが通じないから......」
「逆に何で通じると思うんだ」
「......」
陸稀は胸の前でぎゅっと両手で拳を作ると、深く頷いた。
「ぐっ、ぱっ、バーンだよ。碧ちゃん」
「碧ちゃんじゃない。適当なことばっかり......」
碧壱はひとつ深々と溜め息をつく。
「光栄ですが、舎利弗純壱位。私は鐵純弐位にご指導をいただいているので結構です」
「でもうまくいかないんだろう?」
「それは......」
「まあ、そうじゃなくても仁武はあまり教えるのに向いてないと思うけどね」
新人の頃、半年程度ではあるが一緒に訓練をして感じたのは、仁武も陸稀と同じように感覚派の人間だということだ。その上、今の仁武はまるで人が変わったように他人を寄せ付けないでいる。空木が何を考えて仁武に新人の指導を任せたのかは知らないが、誰かを教え導く状態でないことは確かだ。
「それでも結構です」
「ふうん?」
玖苑もどうしても教えたいというわけではない。まあいいか、と指導するという考えを手放して、そういえば、と碧壱に微笑みかける。
「キミの名前を聞いていなかったな」
「──っ!」
源一族の碧壱だというのはもう知っているが、それは他人から聞いた名前だ。ちゃんと自己紹介をしようか、という意味だったのだが、別の捉え方をされてしまったらしい。
見開かれた目の色が変わる。屈辱、怒り、劣等感──色々な感情が溢れるようにめまぐるしく渦巻き、一瞬で押さえ込まれた。
「源碧壱純参位です。......失礼します。舎利弗純壱位」
「あ。碧壱!」
碧壱は小さく会釈をすると上着を翻して去って行く。自制心は強いようだが、向けられた背中には抑えきれない怒りがにじみ出ていた。陸稀も碧壱を追っていき、運動場にぽつんと残されているのは玖苑の方になった。
「まったく。何を怒っているんだか」
さっぱり分からず、やれやれと首を振る。
「それにしても......ぐちゃぐちゃだなぁ、彼」
目は口ほどに物を言う。玖苑が思うに、碧壱は内側にはドロドロとした何かを抱えているような気がする。自制しきれずに浮かび上がってくる感情の複雑さは、ひと言で言って"ぐちゃぐちゃ"だ。
「いったいどうなるだろうね」
あのぐちゃぐちゃな新人を指導しているのが仁武だという。よくもこのふたりを合わせようと思ったなぁ、と玖苑は空木の采配に首を捻るのだった。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら