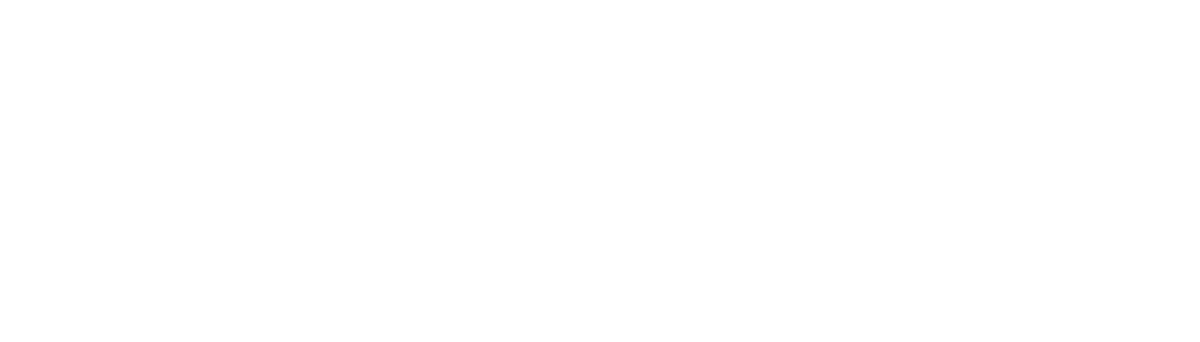INFO
24.09.22
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十- 舎利弗玖苑の結論(5)
著者:麻日珱
前回「断章-十- 舎利弗玖苑の結論(4)」はこちら
仁武と碧壱がふたりでいるのを見かけたのは、夏の暑さに秋の乾いた風が混ざり始めた頃のこと。
「おんちゃん! もうすぐ昇位試験が近いでしょ? 訓練付き合って!」
「いいとも! みんな、失礼するよ」
陸稀の頼みを快諾し、それまでお喋りしていた一団と別れて戦技訓練場へ向かっていたその道中だ。仁武と碧壱は買い出しを済ませてきたのだろう。たくさんの荷物を抱えている。少し距離があったためか、談笑しながら歩いていたふたりは、玖苑と陸稀には気付いていないようだった。
「最近の仁武、表情が柔らかくなったよね」
「そうなのかい?」
玖苑が首を傾げれば、陸稀は、まさか、と言わんばかりに目を見開いた。
「そうなのかいって、気付かなかった?」
「気にもしてなかったな」
「うわ。ハクジョーもん。同期なのに」
同期と言ったって、たかが入隊時期が同じなだけの他人だ。そもそも、向こうが玖苑を避けているのにいちいち気にしたってお互いに不愉快なだけだろう。
「おんちゃんってたまにそういうとこあるよねー? そうだ、聞いてよ! 仁武と碧壱って、ちょーちょー真面目な体力お化けの訓練バカ! おれが休憩しよ? って言っても『もうちょっと』って全然休憩しないし、もうやめよ? って言っても『まだまだ出来る』って全然終わらせてくんないし。もー、ついていけない! って言ったら、『陸稀......』ってふたりして溜め息つくんだよ。できの悪いわんこ見るみたいに! わんこ可愛いけどさ! フツーに傷つく!」
日頃の不満が爆発したのだろう。興奮して息を切らした陸稀だったが、すぐにしょんぼりと肩を落とした。
「おんちゃん、慰めてー」
「もちろんさ。ぎゅー、だ!」
腕を広げた陸稀をハグで受け止める。通行人がぎょっとした顔でふたりを見た。
「あは! いま、ざわってしたね......あ。仁武たちも気付いた」
おーい、と陸稀が大きく手を振る。仁武と碧壱はお互いに目配せをすると、そのまま軽く会釈をして、こちらに寄っても来ないまま通り過ぎていってしまった。
「うわ。近づかないでおこう、みたいな顔してなかった? ふたりとも。絡まれる前に行こう、みたいなさ。しっつれーなんだ」
むくれる陸稀に玖苑はクスクスと笑う。まあまあ、と肩を叩いた。
「それよりむっちゃん。完璧なボクに訓練を頼むのは当然だけど、空木さんには頼まなかったのかい?」
陸稀が最も親しい先輩志献官が空木であることは誰もが知るところだ。司令の補佐や作戦部の長として忙しい人ではあるが、陸稀の頼みを断る人ではない。
不思議に思って尋ねた玖苑に、陸稀はキリリと表情を引き締めた。
「漆理にはいーっぱい迷惑とか心配かけてるから、昇位試験は自分の力で頑張ろうって決めてんの」
「素晴らしいね!」
「でしょー? なのにあのふたりときたら......ま、いいけどさー。おんちゃんが付き合ってくれるし」
陸稀は歩きながら振り返る。仁武たちはすでに遠くにいるが、その姿は人混みに埋もれることがない。
「でもさ......仁武、本当に変わったよ。ずっと眉間ぎゅっとして、顎もぐっと食いしばって......みたいな怖い顔してたのにさ。や。変わったんじゃなくて、戻ったのかな」
「ふうん?」
「わ。興味ない感じ? 前まで仲良かったじゃん。なんでそんな無関心になっちゃったのさ」
何でと言われても。
玖苑は仁武に向けられた錆び付いた眼差しを思い出して顔をしかめた。
「だって、つまらなくってさ」
「つまらない? 何が?」
問われるがまま、燈京湾防衛戦後の出来事を打ち明ける。玖苑は玖苑であるだけなのに、勝手に卑屈になって玖苑を責めるような態度をとる仁武がつまらなく感じられたということ、そのせいで、任務にまで支障を来したのだということを。
大きな目をクルクルと動かしながら聞いていた陸稀は、悩むように唸った。
「──んー。よく分かんないけど......。ね、玖苑。それってつまんないじゃなくってさ、寂しいっていうんじゃない?」
「寂しい? 違うよ。ボクは仁武に失望したんだ」
愛情たっぷりに育てられてきた玖苑だって──愛情で育ってきたからこそ、寂しさくらい知っている。家に病気の母を置いて、行ってきますと家を出るときの、あの後ろ髪を引かれるような不安な気持ちが寂しさだ。母を失ってしまうかもしれないと思うと夜も眠れなくなるようなあの感覚が、玖苑にとっての寂しさだった。
けれど仁武に対して感じたのは、落胆と苛立ちだ。裏切られたという感覚さえあった。もうどうでもいいやと手放すことが、寂しさであるはずがない。
「そうかなぁ? おれはさ、玖苑に無茶振りされて慌てたり、困った顔したりする仁武も、そんな仁武を見て笑ってる玖苑も好きだったよ。また前みたいには戻れない?」
「さあ? 仁武次第じゃないかな?」
元の仁武に戻りつつあるのだとしたら、そう捨てたものではないのかもしれない。ただ、玖苑の方から歩み寄ったところで、またあの劣等感に塗れた錆び付いた目を向けられるのはごめんだった。
「うー......そっかぁ」
むむむ、と唸る陸稀は、パンパンと両手で頬を叩いた。
「脳内漆理が、他人の事情には軽々しく首を突っ込まないことって言ってるからこの話はここでやめ!」
「空木さんを脳内に飼ってるのかい?」
「困ったときの漆理頼みだからね。昇位試験に受かりたければしっかり訓練するように、とも聞こえてくるよ」
「もはやお告げかな?」
「絶対絶対受かるぞー! オー!」
高々と突き上げられた拳は、行き場もないまま落ちていった。
秋に行われた昇位試験で審査員として陸稀を審査し、落としたのは玖苑だった。
「空木さん......」
作戦部の事務室を訪ねれば、窓を背に事務仕事を処理していた空木が顔を上げた。
「......舎利弗君のそういう顔は珍しいですね」
どういう顔をしているのだろう。頬を撫でてみたが分からなかった。
「陸稀は落ちたでしょう?」
「うん......」
「そうだと思いました。陸稀は今?」
「医務室に連れてったよ。でも......どうして?」
試験のため侵食領域の中に入ったとき、陸稀の様子がおかしいとは思っていた。それでも大丈夫だという陸稀を連れて、しばらく侵食領域を進んでいった。陸稀の様子がどんどん悪くなっていくのは感じていたが、本人はやれると頑として譲らない。
けれど、デッドマター形成体と対峙したとき、陸稀は恐慌状態に陥った。呼吸も困難になった陸稀の気を失わせたのは玖苑だ。その後、玖苑は速やかに形成体を倒し、陸稀を背負って侵食領域を出た。目を覚ました陸稀はただ幼い子供のように「ごめんね」と謝るばかりだった。
空木は小さく溜め息をつき、ペンを置いた。
「舎利弗君は見たことがあるでしょう? 結合術を使ったとき、私の記憶で」
「......陸稀が、今回みたいに泣き叫んでいるところ?」
随分前のことを思い出した玖苑に、空木は深く頷く。
「ええ。あの子は志献官になる前、侵食領域に呑まれた両親が消滅するのを見ているんです。当時、しばらくは、夜にひとりになると恐怖で取り乱すほどでしたから」
「でも......純参位にはなれたのに」
「そうですね......」
空木は悲しげに微笑む。空木が陸稀を志献官にするために何か働きかけたのかと思ったが、続く言葉にそれも違うのだと悟る。
「なれてしまったんですよね。困ったことに」
「空木さん?」
「陸稀のことは私が対処します。侵食領域でのことは、なるべく他言しないようお願いします」
「......分かった」
「ありがとう」
空木の眼差しから、これ以上は話してくれないだろうと頷く。誰かに言いふらすような内容でもない。陸稀のいる医務室へ向かうと言う空木と別れて、玖苑はその場を後にした。
(......知らなかったな)
陸稀はいつも元気に笑っていたから、家族を失っているなんて思いもしなかった。玖苑も父と祖母を失っているが、まだ母がいる。その母を失うと考えただけで、怖くて悲しくなるのだ。実際に一瞬ですべて失った陸稀はどれほどつらかっただろう。
とぼとぼと廊下を歩いていると、昇位おめでとうございます、と声が聞こえた。混の志献官たちが、仁武と碧壱を囲んで賛辞を述べているようだ。
「......彼らは受かったのか」
照れ笑いを浮かべる仁武と、当然だと表情の中に喜びを隠しきれない碧壱の姿を見て、不意に陸稀の言葉が蘇る。
『最近の仁武、表情が柔らかくなったよね』
(あ、本当だ)
どうしてか、まるで違う世界の光景を眺めているような心地になった。
仁武は頑なに心を閉ざして純弐位に甘んじていたし、碧壱は卑屈な自尊心の高さが見え隠れしていた。どちらも完璧を目指しているのに、完璧とはほど遠い。ぶつけ合えば共に壊れてしまうようなふたりだった。少なくとも、玖苑はそう見えた。
それなのに、どうしてだろう。あそこで賛辞を受けるふたりは、揃ったことで完成したように感じられる。陸稀と空木が一緒にいるときと同じだ。
完璧じゃないのに、完成している。それが不思議だった。
「......なんでだろう?」
あの祝福の輪の中に入って、仁武と碧壱にどうしてか聞いてみたい衝動に駆られた。
いったい何が──碧壱の何が、あの十六夜さえお手上げだった、仁武の頑なな心を溶かしたのだろう。
一歩踏み出そうとして、結局、玖苑は踵を返した。たとえ、仁武が以前のような性格に戻ったところで、玖苑への態度まで元に戻るとは思えない。その証拠に、仁武はずっと玖苑を避けている。
燈京湾防衛戦で仁武の中に生まれたのは、己への不甲斐なさと玖苑への劣等感だ。碧壱といて何かが変わったところで、玖苑に向けられる感情は変わらない。そもそも、碧壱自身がなぜか玖苑に敵対心を抱いている。そんなふたりにとって、玖苑は招かれざる客でしかない。
「──つまらないな」
無意識に口からこぼれ出て、はたと足を止める。
『それってつまんないじゃなくってさ、寂しいっていうんじゃない?』
「......」
陸稀の言葉がまたよぎった。
「寂しい? ボクが?」
まさか、と首を振る。仁武や碧壱なんて、取り巻くたくさんの人たちのうちのたったふたりだ。彼らにこだわらなくても、玖苑を慕う人は数え切れないほどいる。防衛本部はもちろん、街中にだってたくさん。
玖苑が活躍すれば賞賛してくれて、微笑みかければ喜んでくれて、気がつけば周りを取り囲んで玖苑の話を楽しそうに聞いてくれるみんながいる。
みんなが。
(あれ......? みんなって、誰だろう)
玖苑はぽかんと立ち尽くした。玖苑を囲むのはいつだって、名も知らぬ人々だった。
「あれ?」
玖苑の人生の中で人とは寄せては返す波のようなものだった。賑やかな波音を立てて近づいては足をくすぐり離れていく。それをどうして惜しむだろうか。今来た波と次に来る波が違ったところで、なんとも思わない。思う方がおかしい。だって、それが当たり前だから。
顔も知らず、名前も知らない。寄せては返すばかりの波が何を言おうと玖苑を揺るがすことはない。賞賛は喜びと共に受け止めて、悪意は引いていく波を見送るように忘れるだけ。
『──あなたの独善はいずれあなたをひとりにする。今のうちに改めることをおすすめします』
いつかの空木の言葉が甦る。玖苑は確か、その言葉にこう返したのだ。
『ボクがひとりになるなんてあり得ませんよ。だってみんなボクのことが好きだろう?』
みんな──みんな?
(あの時ボクを見上げていた人たちは、どんな顔をしていたっけ)
玖苑は楽しいことが好きだ。楽しませることも好きだし、みんなが玖苑を見て笑顔になるのは単純に嬉しいし、満たされる。
けれど、その"みんな"が玖苑に背を向けたところで、つまらないと感じるだろうか。
おそらく感じない。引いていく波を惜しまぬように。
(みんなが完璧なボクに嫉妬や劣等感を抱くのは当然だ。だって、ボクじゃないんだから)
完璧な存在が目の前にいれば、悔しさのあまり感情をぶつけてしまいたくなるのも仕方がない。そんなこと、とっくに理解していた。つまらなさを感じるまでもない自明の理だ。
では、例えば十六夜や空木、陸稀ならば? 彼らが仁武と同じように背を向けたとしたら──きっと、同じような失望感を覚えるだろう。つまらないと拗ねる自分の姿が、玖苑には容易く想像できた。
彼らは、ただ寄せては返すだけの波などではないから。
「......なるほど、そういうことか」
「おや、玖苑殿。いかがなされましたかな?」
なんて素晴らしいタイミングで声を掛けてくれたのだろう。玖苑は見上げるおじいちゃんモルを、流れるように掬い上げた。
「モルG、これも"寂しい"だったんだね!」
「ほ?」
玖苑は胸の中に巣くっていた数年来のモヤモヤが晴れたような気持ちでモルGを両手に高く掲げてくるりと回る。
さっき感じたつまらなさや、以前も仁武に感じたつまらなさの正体は寂しさなのだ。
「やめてくだされ、玖苑殿ぉ!? 老体には酷ですぞぉ!!」
「"つまらない"が"寂しい"なら、"つまらない"を"面白い"に変えれば、寂しくなくなるってことさ!」
モルGは目が回ったように頭をグラグラさせながら、落ちかけた制帽を頭直した。
「よ、よくは分かりませんが......いつも以上に素敵な笑顔ですな、玖苑殿」
「ありがと。難問を解いたみたいにすっきりしているところだよ! 気分がいいから、モルGが行くところまで連れて行ってあげようじゃないか」
「ほほ。そうですか? では、お言葉に甘えて、碧壱殿のところに連れて行ってはもらえませんかな?」
「碧壱? さっきそこにいたから大した距離じゃないけど」
らしくもなくためらってしまったが、ああいう場には多少嫌な顔をされようと、飛び込んでみんなでお祝いするのが流儀だった。今からでも遅くないはずだ、と思って先ほどの場所に戻ると、既に祝いの集まりは撤収していた。おそらく、偶発的な集まりだったのだろう。
「もったいないなぁ。せっかくのお祝いなのに」
そうだ、と玖苑はモルGに微笑んだ。碧壱にモルGを届けるついでに、盛大に祝ってあげよう。
「ボクの勘では......」
あっちかな? と適当な方へと歩き出す。
(さて、碧壱はどっちだろうね)
居場所の話ではない。玖苑にとって寄せては返すだけの波か、それとも、そうではないモノか。
今のところはただの波だ。そもそも玖苑は碧壱のことをよく知らない。初対面の時、彼に絡んでいた本当に退屈な輩と大差ない存在だ。だが、あんなにも頑なだった仁武を、ただのつまらないモノがあそこまで変えたとは思えない。陸稀も気に掛けているくらいだ。きっと、何か特別な人間なのだろう。
「あ、いたいた」
司令室へと向かっているのだろうか。さっと視線を走らせたが、仁武はどこかへ行ったらしく姿がない。
玖苑はちょうどいい、と思いながら碧壱に声を掛けた。
「碧壱!」
「え?」
ぎょっとしたように碧壱が振り返る。表情を取り繕うこともできなかったのか、玖苑を見た一瞬、不愉快そうに眉が動いた。
「昇位試験に受かったんだってね。おめでとう!」
「ああ、はい。ありがとうございます。何か、ご用ですか?」
「モルGがね。キミを探していたよ」
玖苑はずいっとモルGを差し出す。鼻先にモルGを突きつけられた碧壱はぐっと身を引いた。
「司令がお呼びですとお伝えに来たんですが......どうやら、その必要はなさそうですな」
数歩下がって距離をとった碧壱は、ああ、と横目に司令室を見た。
「昇位試験が終わったら来るように言われていたから。舎利弗純壱位が何もなければこのまま報告に行きますが、構いませんか?」
「もちろん」
碧壱は終始怪訝そうな顔をしながら司令室に入っていく。静かに閉まる扉に向かい、玖苑はふうん、と鼻を鳴らす。
「どうかしましたかな?」
「いいや? モルGから見て碧壱ってどういう人?」
「碧壱殿ですか? よいお方ですよ。少々、やり過ぎとも思えるくらいの努力家ですな。我々モルにもお優しいですし」
「なるほどなるほど。じゃあ、"あれ"はボクにだけかな?」
「あれとは?」
玖苑はにこりと笑うと、シーッと口の前に指を一本立てる。
「秘密さ。まあ、少し様子見ってところだね」
碧壱が玖苑を見る目には、警戒心が滲んでいた。初対面の時と変わらない、あるいはそれ以上に卑屈な敵意。拭き取ったかのようにさっと消えていく感情は、半年前よりも隠すのが上手くなったなという程度の印象しか与えなかった。
(なるほどねぇ)
こちらは本物の"つまらない"かもしれないぞ、と思う。特に気にしたことはなかったが、混の志献官や職員、モルたちとのお喋りの中で碧壱に対する悪評が上ったことはない。おそらく、他の皆もモルGと同じような印象を抱いているのだろう。
(でも、胡散臭いな)
初対面の時に感じた"ぐちゃぐちゃ"を周りに悟らせないように生きているのなら大したものだが、本当にそうだろうか?
今まで興味がなくて意識にも引っかからなかったことが、一度関心を持つとやたらと視界に入ってくるのはよくあることだ。
例えば、仁武とよく一緒にいるのだろうと思っていたが、案外単独行動が多い。彼に話しかける混の志献官とのやりとりでは、上っ面で微笑んでいるだけで目の奥は冷たく冴え冴えとしていた。
玖苑がひとりでさっさと終えた侵食防衛に遅れて駆けつけたときなどは、玖苑が気付かないと思ってか、忌々しげに睨みつけていたこともある。
碧壱を気にする以前のことも案外記憶の片隅には残っていたようで、思い返してみれば「そういえば」と思うことは多々あった。
とはいえ、これらは偶然目撃したか、ふとしたときに気がついただけの"源碧壱"像だ。碧壱は基本的に玖苑のことを避けているし、仁武も同様だ。仁武をつまらないと切り捨てて放置している間に、面白いくらい何もかもが重ならなくなっていた。
「そういう風に組んでますからね」
「やっぱり空木さんか」
作戦部の事務所で事務仕事に徹している空木に聞いてみれば、しれっとそんな答えが返ってきた。
「舎利弗君はともかく、鐵君の能率が下がります」
「仁武ってば、あんな大きなナリして案外繊細だからね」
「ようやく元の鐵君に戻りつつあるんです。気をつけてください」
「いっぺんぶつかったらいいんじゃない? 喧嘩なんざ、顔会わせてみりゃなんてことなかったりするぜ?」
横から口を出してきたのは、モルが持ってきたお茶に手を伸ばしている十六夜だ。長期任務を終えたのが昇位試験前の夏頃らしいが、塩水流一那という子供を連れ帰ってきたことで俄に立ち上がった隠し子疑惑のあとしばらく姿を見かけなかった。春になって、冬眠明けのクマのように出てきたようだ。
「てか、お前さんたち、まーだ微妙な感じだったのか。てっきりとっくに仲直りしたと思ってたよ」
玖苑は小さく肩を竦めた。もしも"つまらなさ"の正体が"寂しさ"だと気付かなければ、今だってこんなに関心を持ってはいなかっただろう。
「少し様子見してるんだ。ボクには碧壱の何が仁武を元に戻したのか分からなくてね」
「ふうん? お前さんにしちゃ慎重だな」
「まあね」
仁武は玖苑に引け目を感じている。その上、側にいる碧壱も玖苑に対していい感情を持っていないとなれば、無理やりの正面突破はあちらの結束を固めるばかりだ。
手順を間違えれば、玖苑ばかりが悪者になる。悪者になるのは構わないが、またあんな"つまらない"思いはしたくない。
「まあ、気長にやるさ」
触媒の志献官を失ってからも、今ある戦力で何とか押しとどめてきた。志献官の数こそ減っているが、如月人工島以降の侵食はさほど壊滅的な打撃を与える脅威ではないため、なんとかしのげている。誰もがデッドマターに対して、日々どうにもならないもどかしさを抱えているが、それが結倭ノ国の日常だ。
だから──。
だから、あれほどまでに無謀な作戦が立てられたのかもしれない。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら