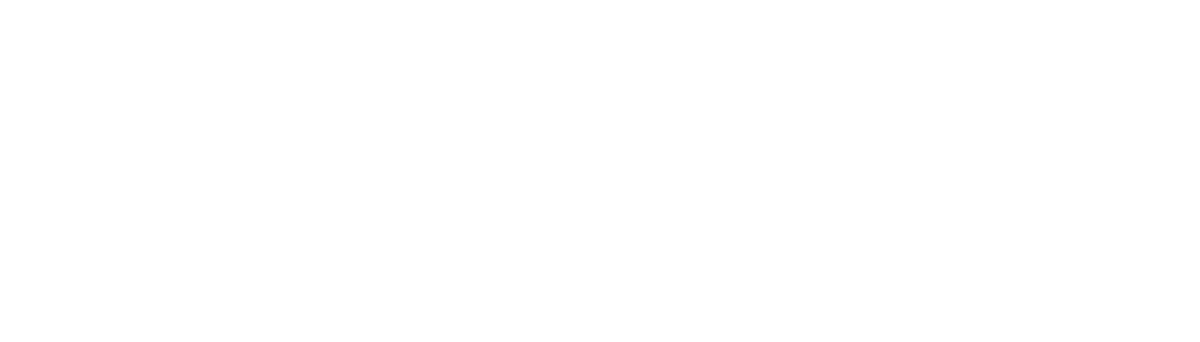INFO
24.10.06
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十一- 清硫十六夜の濁流(3)
著者:麻日珱
前回「断章-十一- 清硫十六夜の濁流(2)」はこちら
新和十一年──。
むせ返るような血溜まりを傍らに、紫煙を天井へと吐き出した。任務後の興奮が、落ち着いていく。物言わぬ死体を一瞥し、十六夜はその場をあとにした。
初めて人を殺してから数年、人を殺す感触にも、血の臭いにも、返り血を浴びない殺し方にも、もう慣れた。
防衛本部の害となる人間はどこにでもいる。次から次へとよくもまあ、湧いて出るものだと最近では感心するほどだ。
ヤツらを始末することは、結倭ノ国には必要なことだ。万に一つでも、志献官の使命が果たせないようなことがあってはならない。デッドマターから、結倭ノ国を、この世界を守らなければ、デッドマターに飲まれて死んだ数多(あまた)の命が報われない。
『約束。ね?』
タバコを挟んでいる右手の小指が小さく痙攣した。
妹とした約束が夢だったのか、現実だったのか、もうよく分からない。
十六夜は深くタバコを吸った。
どんなに汚れた仕事でも、誰かがやらなければならない。この世はきれい事だけでは回っていない。現実には目を背けたくなることだらけだ。だが──誰もがそんなものを直視しながら生きているわけじゃない。
見ない振りをして、なかった物として扱って。そうして沈んだ汚い物を知らんぷりして、上澄みだけを享受しているのが大半の人間だろう。
それでいいのだと、十六夜は思う。ただでさえ、いつ死ぬかも分からないご時世だ。誰も彼もが深刻な顔をして生きている必要はない。
ただ、十六夜はその皆が目を背けた汚い場所で生きているというだけで。
ふぅ、と吐き出した煙が月明かりを滲ませる。いやに眩しい月だ。煌々と輝いて、まるで十六夜の罪を暴こうとでもしているようだった。
ふと、近くの歓楽街の賑わいが風に乗って、誘うように肌を撫でた。
横浜の街の一角は、ともすればお行儀のいい燈京よりもよほど華やかだ。燈京からあぶれたけれど、そのほかに行くほど落ちぶれてもいない。そんな人間が集まる場所だ。酒もタバコも、この街で覚えた。せっかく来たのだからなじみの店にでも顔を出していくかと、十六夜は短くなったタバコを壁に押しつけて揉み消す。
闇が路地から抜け出るように静かに通りへ出た。明かりの灯された街灯の下、心地よい春宵に揺蕩(たゆた)うように酒に浮かれた若者たちが話に花を咲かせている。
平和な光景だった。脳天気に笑う自分たちの隣を、人殺しが歩いているなんて考えもしない。
「ね、お兄さん──」
「......」
甘ったるい香水の匂いを纏わせながら手を伸ばしてくる女を無言でかわす。名残惜しげな声が後を追ったが、気分ではない。十六夜が一瞥もくれないと分かると、悪態をついて離れていった。
そのまま吸い込まれるように、よく行く飲み屋ののれんをくぐる。喧噪と共に見知った顔が幾つも十六夜を出迎えた。タバコが煙たい店内では、酔っぱらいたちが陽気に酒を飲んで大声で笑っている。雑多な臭いは、鼻の奥に残る血腥さをかき消すにはちょうどよかった。
そこに埋もれるように身を置いて、出されたお通しを肴に酒を呷る。ふっと香り高い酒精が鼻に抜けていった。
その余韻に浸りながらタバコをくわえてマッチ箱を取り出せば、妙に軽い。振ったところで何の音もせず、開ければ案の定空っぽだった。
「誰か──」
火を貸してくれ、と言い切る前にポッと目の前に火が灯る。
「シケたツラしてるねぇ、いざちゃん」
六十歳に届くかどうかという年代の男が、目元にくしゃりと皺を寄せて笑っていた。近くの席に座っていた常連客だ。
差し出されたマッチの火をありがたく頂戴し、十六夜はタバコを吹かす。指に挟んだタバコをひらりとさせて、不敵に口角を上げた。
「そう見える?」
「見える見える。志献官が深刻そうな顔してると、ドキーッとしちまうよ」
常連客は怖い怖い、と首を振る。
「最近、横浜(こっち)の方にはあんまり顔出してないんだろ? みんな、いざちゃんが来ないって寂しがってるよー? 志献官ってなぁ、今そんなに忙しいんだ?」
表情や物言いは軽かったが、その目は至って真剣だった。当然だろう。横浜は燈京に次ぐ強度の元素結界で守られているが、あまりにもデッドマターの脅威が近い。それでも皆、デッドマターはどうなっているのだと直接聞くのが恐ろしいのか、遠回しに聞いてくることが多かった。
十六夜は冷え固まったような表情を豊かに動かして快活に笑う。
「いやいや。デッドマターなら相変わらずだよ。安心しなって。俺たち舎密防衛本部の志献官が結倭ノ国の暮らしを守りますってね」
十六夜の言葉に常連客は安堵したように相好を崩して敬礼した。
「若いのにご苦労様です、ってな。そうだ、いざちゃん、今いくつよ?」
「歳? この前二十五になったとこ」
「おや。おめでとさん。つか思ってたより若かったなぁ」
「ホントに? 俺、オッサンみたいに見える?」
この傷のせいかな、と十六夜は傷を撫でた。
「やぁ、何かみょーに達観した目ぇしてるもんだからさ」
「そりゃぁね。こんな仕事だもの」
落ちそうになったタバコの灰を灰皿に落とし、十六夜は酒を口にする。
「それに、飲んで吸う姿が堂に入ってる」
したり顔で言われて、十六夜はぷっと吹き出した。はは! と快活に笑って大いに頷く。
「そりゃ、こんな店にばっか来てるからさ」
「違いねぇ!」
周りでなんとなしにこちらの話を耳に捉えていただけの客たちも一斉に笑った。
あれを食え、これも食えと客たちが注文する料理に箸を伸ばす。任務の陰気な気持ちを一時忘れて腹を満たした。次から次へとやってくる相手と会話を楽しんでいれば、十六夜もあっという間に浮かれた酔っ払いの一員だ。
夜も更けていくにつれて、客たちは少しずつ減っていく。もう家に帰る時間だ。火が萎むように賑わいが消えていくのを感じて十六夜は席を立った。
「おっちゃん、お愛想」
財布をのぞき込み、入れていた札を数えもせずに無造作にぽんとカウンターに置いた。
「......」
これまでうるさい客たちの間でじっと黙って料理を作っていた店主は、眉根を寄せて無言で怪訝そうに十六夜を見上げる。今日食べた料理のほとんどは客たちの奢りだ。十六夜が支払う金は、最初の一杯の値段に過ぎない。多すぎる金だと、店主は思っているのだろう。
「今日の人たち、次来たら俺の奢りだっつっといて」
どうせ、使い道のない金だ。純壱位の給料に、危険手当、裏組織の報酬と、やたら入ってくるが、持っていたところで志献官など明日死ぬかもしれない身だ。だからぱぁっと使ってしまった方がいい。
「ごちそうさま、また来る──あ、やっぱり帰りの電車賃だけ返してもらうわ」
十六夜は締まんないねぇ、と笑いながら、ほとんど空っぽになった財布を懐に突っ込んで店を出る。癖でタバコをくわえてから、火がなかったと肩をすくめた。
ひやりとする夜風と散歩するように身を任せて歩いていれば、妙に滑稽な心地がして笑いが込み上げる。
「──狂ってんなぁ」
殺しの任務を請け負うようになった当初は、それは酷いものだった。殺しの直後は胃が痙攣するほど吐いたし、いつまでも感触が手に残り、血腥さが鼻にまとわりついているような気がした。肉を食うなどもってのほかだ。
罪悪感に苛まれ、悪夢ばかり見てろくに眠れもしなかったが、今はそうでもない。もうどこか壊れたか、麻痺してしまったのだろう。
けれど──のんきで平和なこの街や、燈京を護るためなのだと思えば、こんな狂い方のできる自分でよかったと思う。同期のような狂い方をしていたら、とっくに命を絶っていたはずだ。
そっと小指に何かが触れたような気がして拳を握る。
(──分かってるよ)
必ず、仇は取ってやるから。
たとえ、殺した相手の血で溺れ死んだとしても。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら