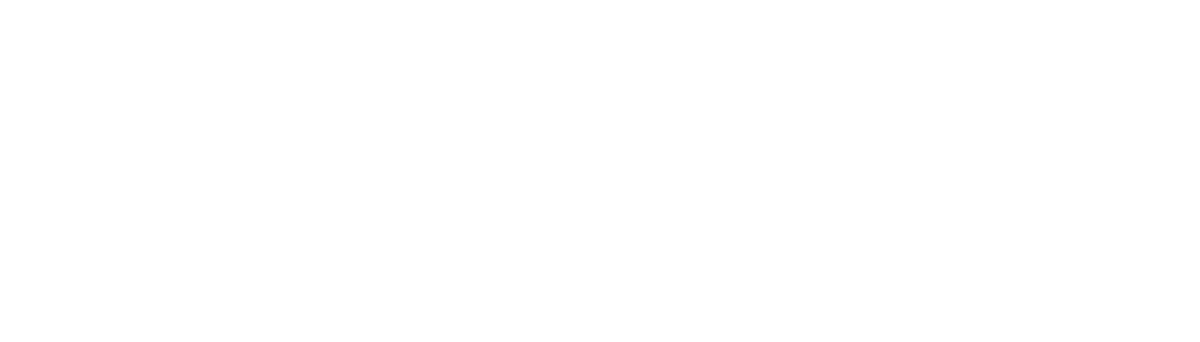INFO
24.10.09
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十一- 清硫十六夜の濁流(4)
著者:麻日珱
前回「断章-十一- 清硫十六夜の濁流(3)」はこちら
新和十三年──。
「新人教育? 俺がぁ?」
十六夜の素っ頓狂な声が、作戦部の事務所に響く。上からの指示を届けたモルは、小さな耳を両手でぎゅっと押さえた。
「近年まれに見る逸材だそうです」
そう言ったのは、同じく事務所にいた空木漆理純壱位だ。十六夜はぐるりと身体をそちらに向けて、三つ下の同僚に不満を露わにする。
「お前さんがやればいいじゃないの。空木。それか別の誰かとかさぁ」
透き通った夜のような濃い青い髪の青年は、書類に落としていた静謐な目を十六夜に向ける。
「やぶさかではありませんが......清硫さんは養成所を出られたと伺いました」
「そーね? それが?」
何やら訳知り顔をしている空木を促す。
「今回の新人の中には、混位からの昇位でない者が二名います。彼らにそこで得たことを伝授してほしいのだとか」
「はぁ? んなの、養成所にぶち込みゃいいだろ。俺ァ忙しいの。新人教育なんてやってらんないって」
確かに最近は少し裏の任務も落ち着いているが、だからといってここぞとばかりに新人教育に駆り出されてはたまらない。
空木はしれっとした顔で続けた。
「養成所も清硫さんがいた頃とは方針が変わったようです。大分優しくなったとか」
「ヤダヤダ。平和ボケしてんのかね?」
十六夜が養成所にいたのは十年も前の話だ。その頃はむしろ今よりもデッドマターの脅威は低かった時代だ。その時代よりも優しくなったというのは聞き捨てならない。
「どうりで養成所から純位に来るヤツが減ったはずだよ。お前さんも行かなかったもんな?」
目の前の空木は、いわゆる混位からの叩き上げだが、他の叩き上げの純位とは事情が異なっている。
空木も十六夜と同じく、適性検査で強い窒素の因子を持つと判明したが、既に窒素の志献官が活躍していた方の人間だ。そのため、空木にも養成所へ進むか、混の志献官として防衛本部で任務に当たるかの選択肢があった。
十六夜とは違って後者を選んだ空木は、死して交代する志献官には珍しく、混の志献官時代に同一元素の純の志献官から手ほどきを受けている。
空木は先代が突然死したのを受けて純位へと昇位したが、そのときには既に純参位ながら洗練された技術を身につけていた。そのせいで古参の純弐位、参位の同僚たちからは未だに複雑そうな視線を向けられている。
十六夜自身が養成所から作戦部に入ったため、新人の頃は先輩たちから扱いづらいなという空気を感じていたし、実際言われたこともある。
一応事前にそれなりの訓練を受けていた十六夜と空木ですらその扱いなのだ。養成所も混位も通っていないずぶの素人がいきなり純位になれば、思うところも大きいだろう。
「......無理か。他のヤツらじゃ」
「難しいと思います。混位を経た人間には」
それは実力的な話でもあるし、心情的な話でもある。十六夜は現在の純位の面々を思って溜め息をついた。悪いヤツらではないのだが、上下関係や礼儀に厳しく、混位歴が短い相手に対して妙に対抗意識を燃やしている。混位歴ゼロなんて新人が来た日には、敵愾心(てきがいしん)を炸裂させそうだ。
十六夜は仕事机に頬杖を突いた。
「その二名ってどんなヤツら? 元素は?」
「鉄の志献官の鐵仁武と、フッ素の志献官の舎利弗玖苑です」
「鉄ってのはあれだろ? この前死んだから補充で?」
鉄の志献官は寿命が短い。純の志献官として五、六年も過ぎれば身体が錆び付いて命を落とす。それが鉄の志献官の宿命だ。しかも皮肉なことに、鉄の因子は適合者が多いため、鉄の志献官には事欠かないという歴史がある。
「そんで、もうひとりがフッ素か......窒素のお前さんは元素的に相性よくないな?」
「それもあって、清硫さんに回ったんだと思います」
なるほどなるほど、と頷いて、十六夜は嘆息する。
「しゃーねえなぁ。一肌脱いでやりますかね」
上の方からは扱いづらいと少々煙たがられている十六夜だ。ここでひとつ新人を味方につけておくのも手かもしれない。扱いづらいのが三人なら、文句も分散されるだろう。
「あ。四人か」
「何がです?」
十六夜はにぃっと笑って自分と空木を指さした。
「俺と、おまえと、新人ふたり」
扱いづらい四人衆の完成だ。
空木は、あからさまに何を言っているんだというような怪訝そうな顔をしたが、深くは追及せずに小さく肩をすくめた。
「相手は十代後半の多感な若者たちですから、言動には注意してくださいね」
「......俺のことなんだと思ってんのよ。つか、若(わけ)ーな」
十歳前後年下というわけか──そう思って、十六夜はふっと笑った。
「若かったねぇ、俺も」
十七歳で純の志献官になった。それからあっという間の十年だ。表の任務でも、裏の任務でも、たくさんの死に触れた。今では仲間が死んだところで、心のひとつも痛まない。
酷い人間になっちまったなぁ、と遠い日の自分が嘲笑っている気がした。
数日後、果たして対面することになった鐵仁武と舎利弗玖苑は、十六夜があの頃捨てざるを得なかった全てを持って、そこに立っていた。
他の新人たちとは別に呼びだしたからか、両者ともどこか落ち着かない様子だった。
「鐵仁武純参位です」
「舎利弗玖苑純参位です」
片や緊張しているのか肩肘を張り、片や好奇心いっぱいの大きな目をキラキラと輝かせている。外見から性格まで、全てにおいて正反対そうな二人だ。
「今日からお前たちの指導を担当する清硫十六夜純壱位だ。つっても、俺のことは気軽に十六夜さん、とでも呼んでくれりゃいいから」
「しかし、他の先輩方は......」
「分かりました。十六夜さん」
いかにも真面目そうなのっぽな男前が鐵仁武。笑顔が眩しい華奢な別嬪さんが舎利弗玖苑。これだけ違えば、間違うこともないだろう。
「ま、いきなり純参位で右も左も分からんだろうから、あとで色々モルに聞いてくれ」
「モルに、ですか?」
「十六夜さんじゃなくて?」
仁武は戸惑い、玖苑はきょとんと小首を傾げる。その子供っぽいふたりの表情に目を細めながら、十六夜はニィッと笑った。
「そ。俺が教えんのは戦い方だ」
その瞬間、ふたりの表情が引き締まった。いい顔をするふたりだ。これは期待できるかもしれない。
「お前さんたちはいきなり純参位になった分、知識も経験も混位から上がってきた志献官たちと比べて圧倒的に足りない。そのことでブーブー文句を言うヤツも出てくるだろう」
「ブーブー......」
ふたりが同時にぽつりと呟いたのが妙に面白い。それぞれの顔をじっくりと見つめ、十六夜は三本指を立てた。
「三ヶ月」
十六夜はもったいぶるように一呼吸置いて続けた。
「三ヶ月で使えるようにしてやる。ついていけないなんて弱音は聞かない。死ぬ覚悟でついてこい」
もとより緊張していた仁武には固い意志が、悠然としていた玖苑には緊張感がみなぎる。
「ぐだぐだ言ってくるヤツは実力で黙らせろ。分かったな?」
「はい!」
ふたりの返事に十六夜は大いに頷いた。
「いい返事だ。そんじゃ、まずは──」
ゴクリとつばを呑み、ふたりがやや前のめりに十六夜の言葉に耳を傾ける。十六夜は鋭い眼差しでふたりを交互に見つめると、高らかに宣言した。
「豚まむしでも食いに行くか!」
「はい?」
「ぶたま?」
ぽかんと目を見開いた幼さの残る顔に呵々と笑い、十六夜はくるりと背を向ける。
「美味い店知ってんだよねぇ。あ、牛丼がいい? 好きな方でいいぜ。親睦会といこうや」
さっさと歩き始めれば、少し戸惑った間のあとで、ふたりがついてくる気配がした。
結論から言えば、仁武と玖苑のふたりは十六夜の予想を遙かに上回る速度で元素術を我が物にし、使える以上の志献官へと成長を遂げた。切磋琢磨する相手がいたからというのも大いにあるだろう。
三ヶ月と発破をかけてみたものの、正直なことを言えばそれほど期待はしていなかった。ふたりがどんなに強い元素力を持っていたところで、個人の技量は経験の上に成り立つからだ。その経験は、そう容易く得られるものではない。
しかし、仁武の方は武術の基礎があった上に真面目に自主練を重ねて堅実に力を付け、玖苑の方は天性の才能を見事に花開かせた。
当然、まだ至らない部分は多くあるが、現状でも弱い等級のデッドマター形成体ならばひとりでも問題なく光壊させられるほどには強くなっている。混位から上がってきた彼らの同期など、遠く足下にも及ばない。
「若者こわー。そう思わない?」
ブルブルと"それ"は首を振る。目は怯えてあちこちへと泳ぎ、歯は寒くもないのにカチカチと音を立てる。その顔にびっしりと浮かんだ脂汗がたらりとしたたり落ちていくのが、灯されている蝋燭にぼんやりと浮かび上がった。
「ホント、何でもすぐ吸収して自分のモンにしちゃうんだから。でもま、ああいう志献官が増えるのはいいことだよ。弱くてあっけなくやられちまうよりはずっといい」
うん、と頷きながら、十六夜は男の首に巻き付けた硫黄で作った縄をぐいと引っ張った。
「俺はさ、時々、志献官ってのはカミサマの気まぐれで選ばれてるんじゃないかって思うんだよ」
「な......なに、を」
「知らない? 天の神様の言うとおりって。どーれーにーしーよーうーかーな、で選ばれたのが因子持ち」
一部血統を継いでいる源家や浮石家という例もあるから、この仮説が的外れなのは重々承知だ。ただどうでもいいお喋りをして、相手を不安にさせるためなら、どんな話題だって構わなかった。
「適当に選んで、無責任に押しつけて、勝手に死ねってね。残酷なもんさ。ま、カミサマなんてそんなもんか」
傍観者め、と十六夜はいるかどうかも分からないモノに腹の内で毒づいた。
「志献官が受ける賦活処置ってのは二段階あってな? 一回目は子供のおままごとみたいなもんだ。自分の中の元素力を操れるようにするだけ。でも二回目は違う。二回目は身体の内に元素の神様を降ろすんだ。そうして、おれたち志献官は元素を宿した怪物になる」
「元素の、神様......?」
「ああ、もちろん比喩だよ。そんなもんいやしない。そんな非科学的なモンはさ」
けれど、そうとしか考えられないのも確かだった。
純位になるために行われる最終賦活処置では、それぞれの元素に対応した"水"を飲むことでデッドマターと戦う力を持つ。最終賦活処置を行ってしまえば、その力は、ただ戦いに特化する。デッドマターに侵され、ことが混の志献官にしか出来ないのはそのせいだ。
その"水"は、ひとつの元素につき、ひとり分しかない。対応する純の志献官が生存している間は当然使えず、その志献官が命を落とすとどこからともなく戻ってくる。そうすることで、たとえ純の志献官が姿を消したとしても、生死が分かる仕組みになっている。
「でもまあ、志献官ってのは研究の成果だ。一度出来たなら、もう一度"水"を作れる可能性だってある」
ガクガクと男の震えが大きくなっていく。十六夜は冷たい目で蒼白になった顔を見下ろした。
「なあ? 誰から聞いた? 研究資料が如月人工島にあるって」
ひぅ、と男の喉が細く鳴った。べったりとしたゴム状の硫黄が男の首に張り付いて絡まり、縮んでいく。
「機密のはずなんだがなぁ。あそこが旧防衛本部の研究施設だったってのは。だがまあ......閉鎖されて五十年も経っちゃいない。知ってるヤツは知ってるんだろうさ」
しかし、知っていることと、その情報を悪用する輩に流すのはわけが違う。
「盗んで来いって誰に頼まれた? 話してみろよ。おまえも命が惜しいだろ?」
「は、話す! 話すから!! い、命だけは、助けてくれ!」
十六夜は淡く笑んで言葉を促した。
「い、依頼主は知らない。だから、目的も......うぐっ」
「おいおい、嘘はいけねえな?」
「本当だ! 信じてくれ!」
「......」
十六夜は少し考えて頷いた。
「どうやって連絡を取ってるんだ?」
「指定された場所に指示書と金があって......」
「盗んだ資料は?」
「......もう、渡した」
「そ。お早いことで」
男がビクビクと上目遣いに十六夜を見る。もう話したのだから解放してもらえるだろうという希望と、このまま絞め殺されるのではないかという恐怖で顔が引きつり歪な笑みを作っている。
十六夜がそのまま無表情で黙っていれば、男は焦ったように口を開いた。どこに指示書が置いてあったか、そもそもの発端はある日届いた手紙だった、小舟で人工島まで行くのは大変だった──などと、聞いてもいないのにべらべらまくし立てる。
十六夜はしばらく相槌も打たずに男の話に耳を傾けていたが、やがて話すこともなくなったのか口を噤んだ男に薄く笑った。
「残念だったな。もらった大金もあの世に持って行けなくて」
「待て、待ってくれ! 知ってることは全部話した! 命は助けるって......」
「言ってねえよ」
首に巻いたゴム状硫黄を単斜硫黄に変化させて喉を貫けば、絶叫はすぐさま事切れる。
十六夜は死んだ男を一瞥もせず、身を翻した。
どこぞの研究者が裏で志献官を作る研究をしている、と言う話は昔からあったらしい。ただ、大抵は上手く行かずに立ち消えになっている。こちらが手を下さずとも勝手に潰れていくだけの小物など相手にする必要もないが、防衛本部の資料まで盗んだとなれば話は別だ。本腰を入れて調べてみる必要がある。
「面倒なことになったなぁ......」
十六夜はタバコを吹かしながらぼやく。裏の任務も殺しばかりではない。仁武や玖苑などの表のヤツらにはさせられない任務が次から次へと積み上がっていってうんざりする。
(だが──)
自分がやるしかないのだ。
十六夜はじっとりとまとわりつくような夏の宵を見上げながら、今日も元気に訓練に励んだであろう教え子たちを思った。
彼らが真っ直ぐに志献官としての責務を果たすために、汚れ仕事が必要ならば、全て引き受けよう。
いつか、彼らが自らの生き様を振り返ったときに、若かった日々を嘲弄せずに済むように。
──その年の秋、如月人工島にてデッドマターの侵食が発生し、触媒の志献官を含む五名の純の志献官が殉職。一名が命からがら帰還することになることを、十六夜はまだ知らない。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら