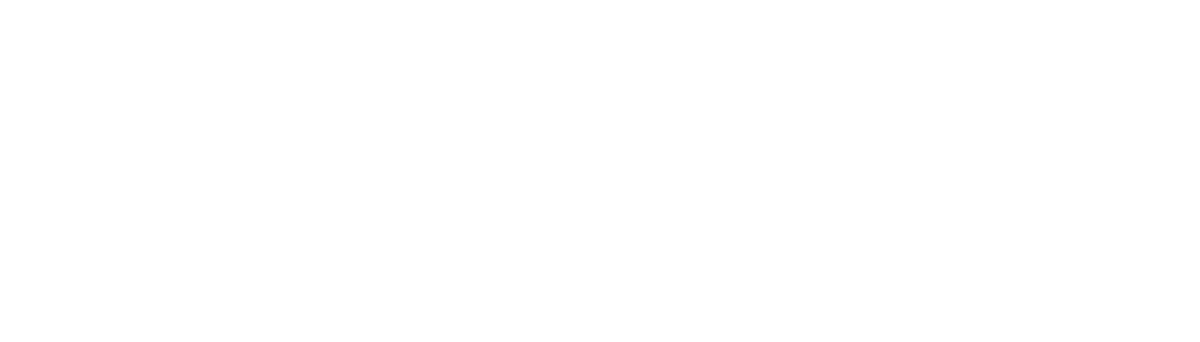INFO
24.10.13
結合男子 -Fragments from Dusk-:断章-十一- 清硫十六夜の濁流(5)
著者:麻日珱
前回「断章-十一- 清硫十六夜の濁流(4)」はこちら
新和十五年 春──。
ひやりとした風が吹く。山桜の美しさにうんざりするほど長々と山道を登っていた十六夜は、一旦足を止めてぐっと背中を伸ばした。
「ったく、なんでこんなとこ」
十六夜は事の発端を思い出して顔をしかめた。
十二年前に防衛本部を逃走し、おそらく前任の硫黄の志献官を殺害したと目される塩素の志献官の抹殺命令が下されたのだ。
「十二年も放って置いて、今更」
文句はごまんとあった。命令を下してきた裏組織の上司にも、十二年も山奥で隠遁生活を送っているという塩素の志献官にも。
「どのツラ下げて隠居してんだか」
今回の任務を受けてから、もう何度も考えている。話によれば、塩素の志献官はかなりの実力者であり、当時も今もなぜ失踪したのか分かっていないという。
チラチラと脳裏に自殺した同期がちらついて、十六夜は小さく舌打ちをした。
動機などどうだっていい。十二年前、塩素の志献官は失踪し、それを追いかけていった硫黄の志献官が死んだ。その後釜に据えられたのが十六夜だという事実は揺るがない。
もしも、十二年前の出来事がなければ、硫黄の志献官の席は空かず、十六夜は今も混の志献官として鉄塔で見張りでもしていただろう。故郷と家族がデッドマターに飲み込まれた無念を晴らす術もなく燻(くすぶ)っていたかもしれない。
だが、少なくとも家族に顔向けできなくなるような人間にはならなかっただろう。
失意の中で選んだ選択とはいえ、自分で歩んできた道だ。いまさら、本当は嫌だったんだ、などと駄々をこねるつもりはない。それに、この力があるから仁武や玖苑のような後進を育てられるし、デッドマターと戦うこともできる──そう頭では理解していても、恨む気持ちが泡のように浮かんでは、恨みをまき散らしながら弾けていくのを止められない。
塩素の志献官は──力を持ちながら山に逃げ込み、同僚を殺して防衛本部の戦力を著しく削いだ男は、今何を思ってのうのうと生きているのだろう。
今回の命令は、今の十六夜ならば塩素の志献官を始末できるだろうという判断が下されたからだが、個人的にも興味があった。
「──ここか」
ようやく山間の人里に辿り着き、十六夜は一息つく。一服したいなと思いながら村の中を歩いたが、不気味なことに人影がない。そうかと思っていれば、覇気のない連中が笛や太鼓を鳴らしながら、神輿を担ぎぞろぞろと列を成して練り歩いている。
異様な空気を感じてそっとついていけば、通りに並ぶ茶屋で客と老人が話をしていた。
「あの子供は、デッドマターに飲まれた女の胎(はら)から産まれた怪物なんですよ」
面白い話が聞けそうだ、と十六夜が話を聞いたところ、先ほどの行列が担ぎ上げていた神輿には、"生き神様"と呼ばれている子供が乗っていたらしい。
(生き神様、ねぇ......)
お喋り好きな茶屋の老人は、十六夜が聞くまでもなくペラペラと話してくれた。
なんでも、十二年前に里をデッドマターが襲い、そのとき犠牲になった妊婦の腹の子だという。その子供はデッドマターを退ける力を持っていたため、"生き神様"として崇められているのだとか。
(崇めてる、か。物は言い様だな)
老人の話を聞いた後、十六夜は子供が住む家を訪ねた。生き神様だという割には、暮らす家はあまりにも質素で、里の中心からは離れている。都合のいいときだけ神様、神様と持ち上げているのだろう。
(だが、どういうことだ?)
話を聞いた限り、子供が持っているというデッドマターを退ける力は、間違いなく志献官の力だ。賦活処置を受けていない子供に、なぜそんな力があるのだろう。
(里がデッドマターに襲われたのは八月って言ってたよな)
老人の話が確かならば、十二年前に失踪した塩素の志献官は、そのときの戦いで命を落としている。だが、塩素の志献官が失踪してから今日まで、塩素の志献官が死んだとは見做されていなかった。つまり、塩素の志献官の"水"は、この十二年間一度も防衛本部に戻ってきていないのだ。
それは、なぜか。
(塩素の志献官の力が、胎児に移った、とか?)
十六夜は皮肉に笑った。
こうなってくると、いよいよ何を基準にして因子が出るのか分からなくなる。
「ハッ──本当に、"天の神様の言う通り"って?」
カミサマとやらの気まぐれで志献官が作られるなら、それこそオカルトじみている。生まれもせずデッドマターに呑まれた胎児を哀れんだ誰かが、赤ん坊に塩素の志献官の力を与えて生かしたのだとしたら、荒唐無稽だが辻褄は合う。
だが、誰が? まさか、デッドマターが、などとは言うまい。
十六夜は考えを振り払うように首を振った。
天然の志献官というものがいるという話を聞いたことがある。賦活処置を受けずとも、志献官の力が使える者のことだ。正直、眉に唾を付けて聞いていたが、あの子供はまさしく"天然の志献官"なのだろう。
家の前で子供が戻るのを待っていたが、結局、子供との接触は叶わなかった。子供の母親──義理の母親だろう──に、憎しみさえ向けられて追い払われてしまったのだ。
仕方がないので泊めてくれるという茶屋に戻ったところ、話し相手ができたと言わんばかりに老人は嬉々として話して聞かせてくれた。
「村がデッドマターに襲われる半年くらい前かなぁ。志献官さんとこに別の志献官さんが訪ねて来られて。しばらくいなくなったと思ったら......」
老人は左腕をぶらぶらとさせた。
「そんひと──元々いた方の志献官ですがね。片腕無くして帰って来なさったんですよ。訪ねてこられた方の志献官さんはどこに行ったのか分からないけどねぇ。もしも両腕残ってたら、あの人もデッドマターとの戦いで死なずにすんだって話で」
なるほど、と十六夜は思った。尋ねてきた別の志献官、というのが、先代の硫黄の志献官だろう。そのときに返り討ちに遭って殺されたのだ。
あの義母にとっては、今回の訪問は当時を彷彿とさせるものだったに違いない。だから、過剰なまでに反応したのだ。
「──ところで、あの子供のことだけど」
「子供? ああ、生き神様。一那様ですか?」
十六夜は食事を世話になりながら老人に聞いた。外はまだ寒く、熱い汁物が体を温める。
「生き神様って言う割には、雑な扱いじゃないか?」
老人はしわに埋もれそうな小さな目をパチパチと瞬かせて首をかしげる。いっそ、無垢なほどの眼差しだ。
「雑、とは?」
「神だと祀るんなら大切にするだろうって話さ」
「怪物なのに?」
十六夜はぎゅっと眉間にしわを寄せた。老人は意外そうに十六夜を見返す。
「怪物ですよ。ありゃぁね。けど、怪物と神様に何の違いがあります? 人に牙剥きゃ怪物で、人によくすりゃ神様だ。そんなもんの違いでしょう」
「雑に扱えば祟るのが神ってもんじゃないのかい?」
「はあ、まあ、そうかもしれませんけど」
随分とぼんやりとした反応を返してから、老人はしばし考え込むように黙り込んだ。これではせっかく出された食事も不味くなる。そう思いながら十六夜が箸を置くと、老人がおもむろに口を開いた。
「──アレは」
「......うん?」
てっきりそのまま黙りかと思っていた。十六夜が聞き返せば、老人は表情の抜け落ちた顔で十六夜をじっと見た。
「アレは、幼い頃暴れたんですよ。まだ、四つにもならない幼子さ。初めてデッドマターを追っ払えるって分かったときでした。デッドマターを追っ払うついでに、暴れて、暴れて──大勢死んだ。アタシの連れ合いも死にました」
「......」
「あの子は覚えちゃいないでしょう。そんくらい小さかった。誰も口に出しゃしません。殺すべきでしたか? 閉じ込めておくべきでしたか? 外からなら何でも言えるでしょうよ。でも、アタシらは、神様だっつって目をそらすことに決めたんです。だって、神様は見えないもんでしょう?」
「デッドマター相手に命を張らせて?」
「怪物だもの。償ってもらわなくちゃぁ、割に合いません」
さも当然と言わんばかりに老人は笑った。十六夜はゆるりと首を振る。
「ごちそうさま。ここら辺で失礼するよ」
「おや。泊まっていかないんですかい?」
先ほどの不気味な笑みなどなかったかのように、老人はきょとんと十六夜を見上げた。
「ちょっと用事を思い出してね」
「そうですか。山に入るんだったらお気をつけください。ここら辺は熊も出ますんで」
そんな言葉を背中に聞きながら家を出る。
すっかり暮れた空には満天の星が瞬いていた。肌寒さにぶるりと身震いをして、十六夜は懐からタバコを出す。火を付けたマッチを振り消しながら、紫煙をくゆらせた。
「怪物、か」
もしもあの子供が本当に塩素の元素力を持っているのならば、因果が過ぎると十六夜は思った。塩素の志献官が硫黄の志献官を殺し、十六夜が新たな硫黄の志献官となって、再び塩素の志献官を殺しに来た。けれど、そこにいたのは何も知らない、ただ力だけを受け継いだ子供だ。
任務を与えられたときから、十六夜の心の中には復讐心にも似た八つ当たりの感情があった。だが、ぶつけようと思っていた塩素の志献官がとっくの昔に死んでいたとなれば、恨みのやりどころが分からない。いったい誰に、この恨みを誰にぶつければいい。
「──いっそ、あのガキを殺しちまうか」
そうすれば、塩素の志献官を作るための"水"は防衛本部に戻り、適合者がいれば新たな塩素の志献官を立てられる。それで任務完了。この村で見聞きしたことを報告するかは十六夜次第だ。
「......」
ふぅ、と煙を吐き出し、十六夜は目を細めた。何にせよ、何も知らない子供を手に掛けるなど、後味が悪いのは確かだ。
(だが──これを使わない手はあるか?)
じわりと染みが浮かび上がるように黒い考えが浮かんだ。
志献官も有限だ。仁武や玖苑、空木のように戦える者となるとさらに数が少ない。あの子供にもう何年もひとりでデッドマターを退けるほどの力があるのならば、鍛え上げれば本物の"怪物"になるだろう。怪物ならば、飼い慣らして連れ回すのもまた一興。
口元を覆った手の下で、口の端に笑みを浮かべる。
「いいねぇ、それ」
狂っているのは誰だろう。
デッドマターの中で産声を上げた子供か。
怪物を生き神様と持ち上げながら利用する村人か。
それとも、あの怪物をどう飼ってやろうかと考える自分か──。
「報いだな」
苦悶に歪む村人の無残な骸を見下ろして、十六夜は無感情に呟いた。
怪物を生き神様と嘯(うそぶ)き、自分たちの都合よく使うから罰が当たったのだ。
一切の生物が死に絶えた里には、塩素の臭いがうっすらと立ちこめている。風が粗方のガスを吹き飛ばしてくれたおかげでこうして歩けているが、逃げる間もなかった村人はひとたまりもなかっただろう。
(デッドマターの方が綺麗に殺す)
転がっている死体は筆舌に尽くしがたいほど無惨だ。対して、デッドマターに呑まれた人間は、跡形もなく消滅する。
十六夜の家族も消えた。痛みはなかっただろうか。苦しまなかっただろうか。
もう、家族の顔も、うまく思い出せない。約束、と絡まった指の感触すら、夢かうつつかも分からないまま消えていった。父を、母を、妹を──思い出してやれるのは自分しかいないのに、両手を真っ赤に染める自分を見ないで欲しいと願うあまり、十六夜の中から家族の姿が薄れていく。
(でも、それでいいのかもしれない)
裏の仕事に手を染めて、もう十年以上経つ。最初の頃は無理やりやらされているのだ、不本意なのだと思っていたが、今ではもうそんな感情も湧いてこない。
これは、必要悪だから。
泥を啜ろうと、地にまみれようと、誰に批難をされようと、誰にも評価されないとしても。
自己憐憫は、陶酔を呼ぶ。これは自分にしかできないことなのだという思いに、酒のように酔ってしまえば、脳の奥が麻痺して、皮肉な笑いばかりが浮かんでくる。
闇の中に身を潜め、血の匂いを嗅ぎながら、一服するタバコの紫煙がぐるりぐるりと巻き付いて、十六夜を肯定する──青空の下で、そんな己の姿を夢想した。
どこにいても、何をしていても、明るい場所などもはやない。
「──見つけた」
子供は、惨めに地面を這いつくばっていた。村人を皆殺しにした怪物には相応しい姿だ。
塩水流一那、と子供の名前を教えてくれた茶屋の老人も、どこかで死んでいるだろう。報いだよ、と十六夜はもう一度胸中で呟いた。
十六夜は這いつくばる子供の前に立つ。一那は絡繰り人形のようにぎこちなく十六夜を見上げた。その虚ろな目にはどんな感情も浮かばない。
呆けたように十六夜を見つめる一那は、まだあどけない顔をしていた。わずかばかり良心が痛んだ気がしたが、そんな感傷はすぐさま脇へと押しのける。
一那にいくつか言葉を掛けて、十六夜は気付いた。
茫然自失としている一那には、自我がないように見える。まるで空っぽだ。
そのとき感じたのは落胆だった。
せっかく怪物を手に入れるために、子供を殺さず村人を見殺しにしたというのに。
十六夜は内心で小さく舌打ちをした。心を壊した子供など、到底使えない。
「はー、やれやれ。困ったもんだ」
ここで母親と一緒に殺してやるのが親切だろうが、その前に本当に使い物にならなくなったのか試してみる必要がある。
十六夜は少年を肩に担ぎ上げた。少年は一切抵抗せず、まるで壊れた木偶人形のようにされるがままだ。十六夜は山に分け入って、山をじわじわと侵食している侵食領域に子供を放り込んだ。
死ぬなら死ねばいい。それが子供の運命だ。
けれど、生きて戻るようなら、そのときは──十六夜はにやりと笑う。
怪物にふさわしい地獄へと、連れて行ってやろうじゃないか。
⇒続きはこちら
※断章-壱-~断章-五-までのエピソードは、アプリ「マンガUP!」にて配信中。
※「断章-六- 鐵仁武の責任」は書籍版のみの掲載となっております。
▶書籍版購入は こちら